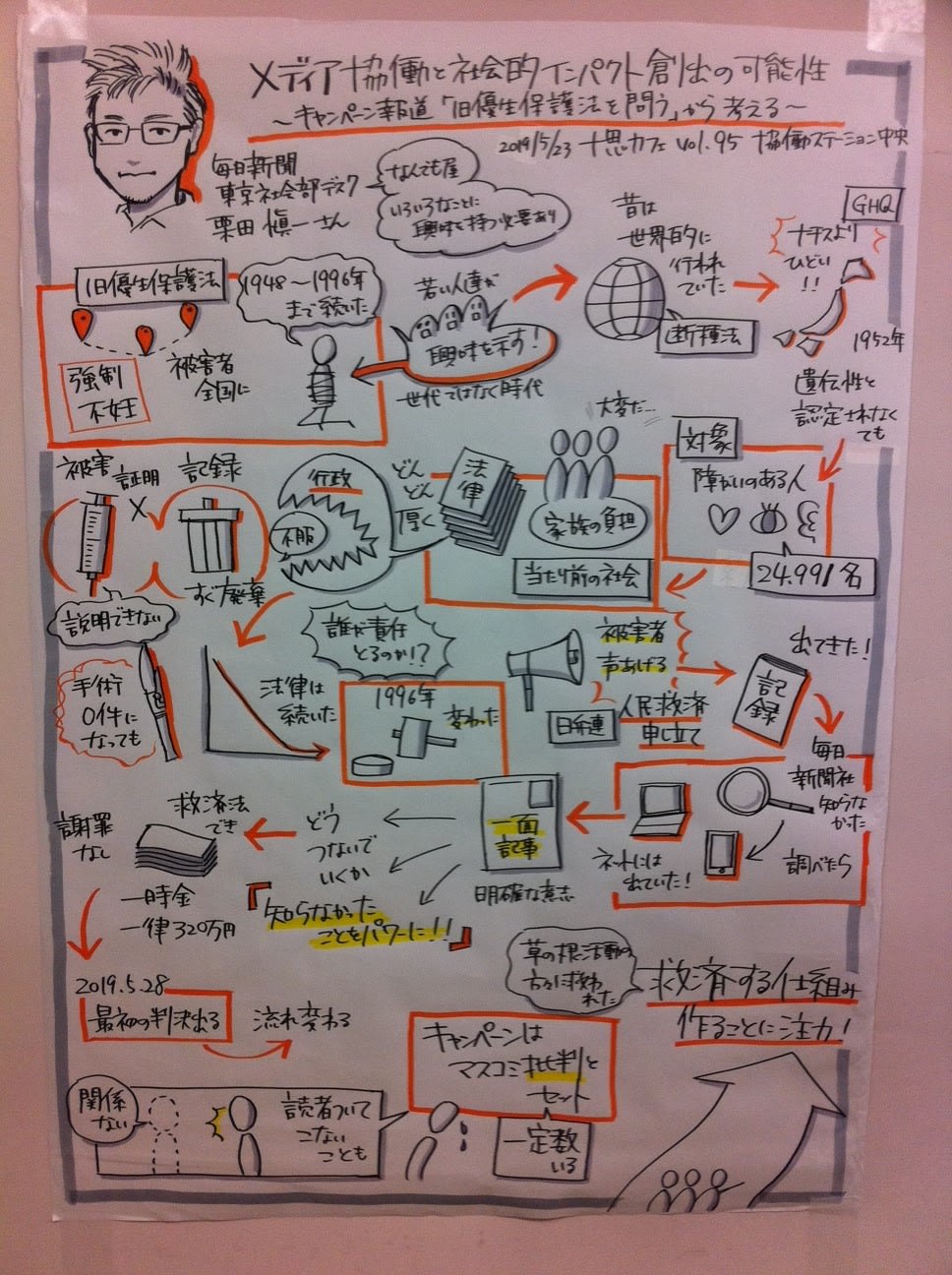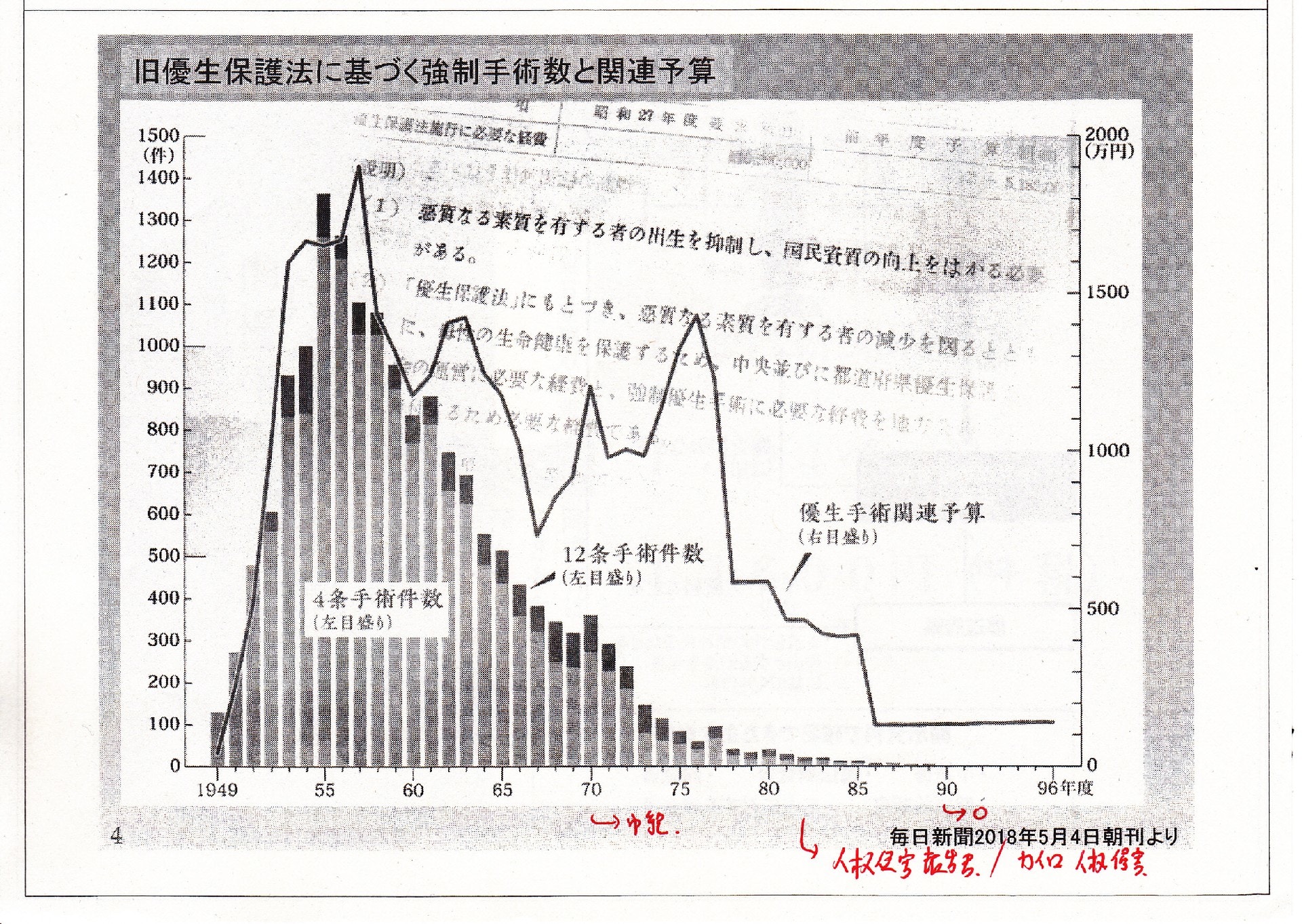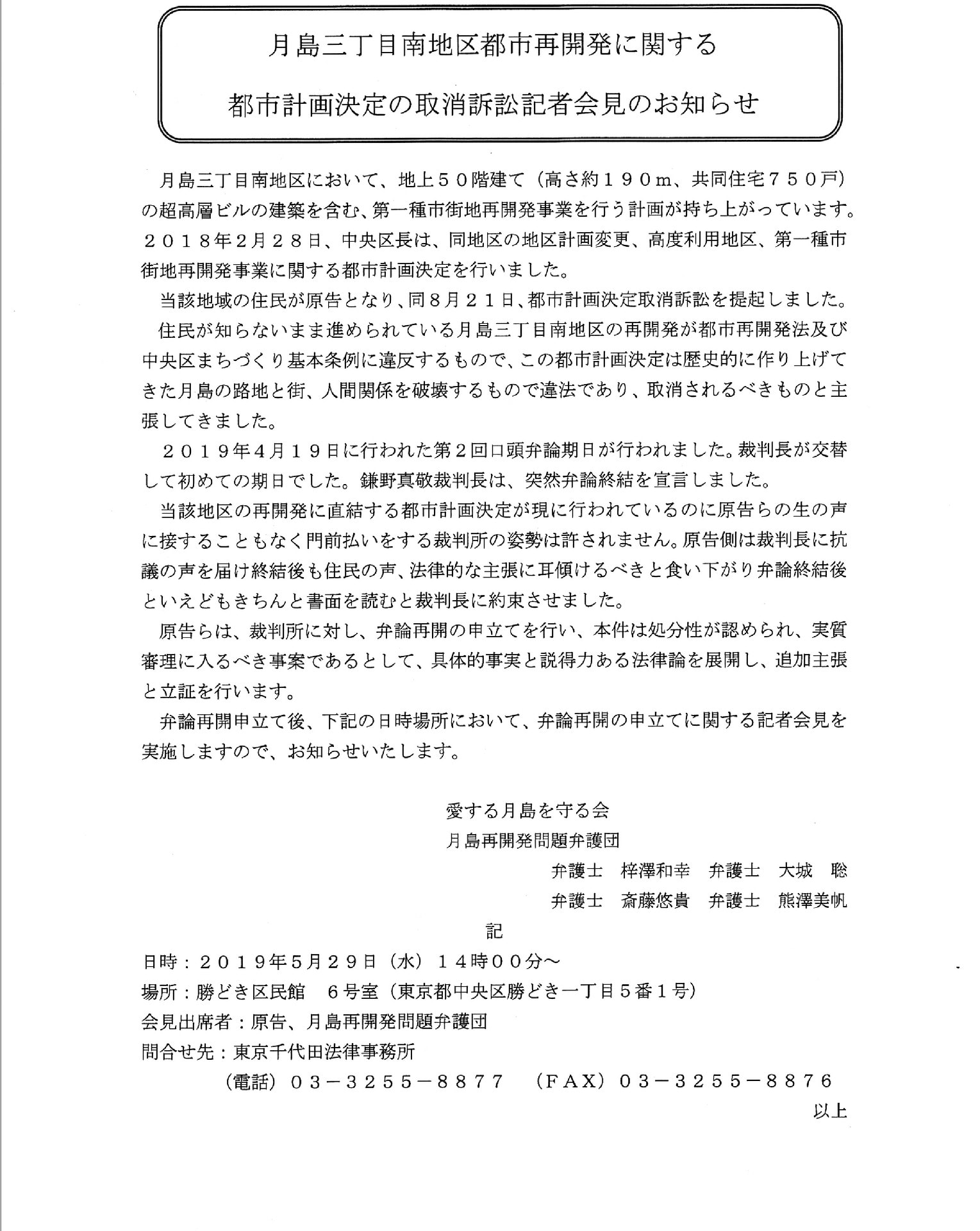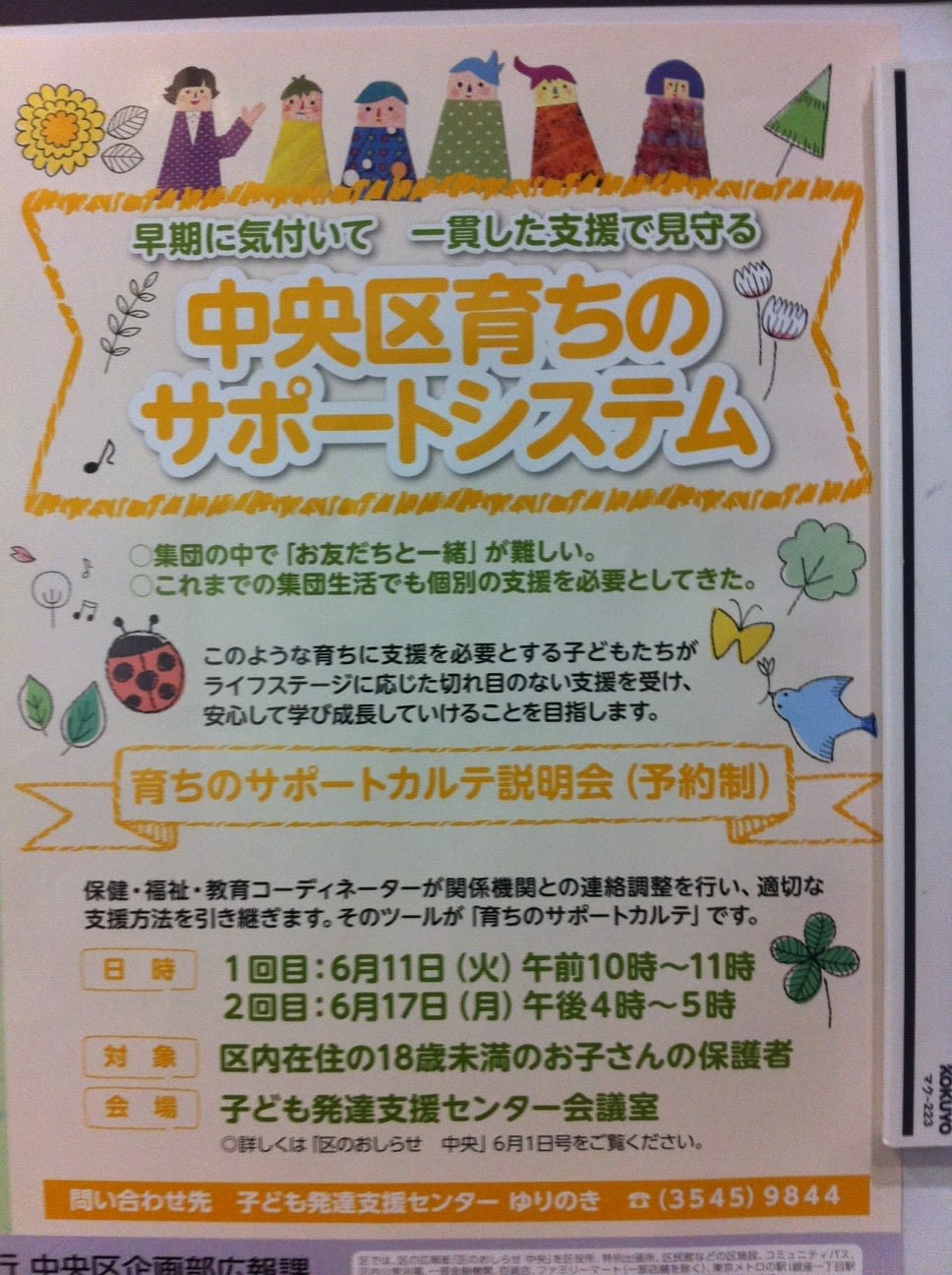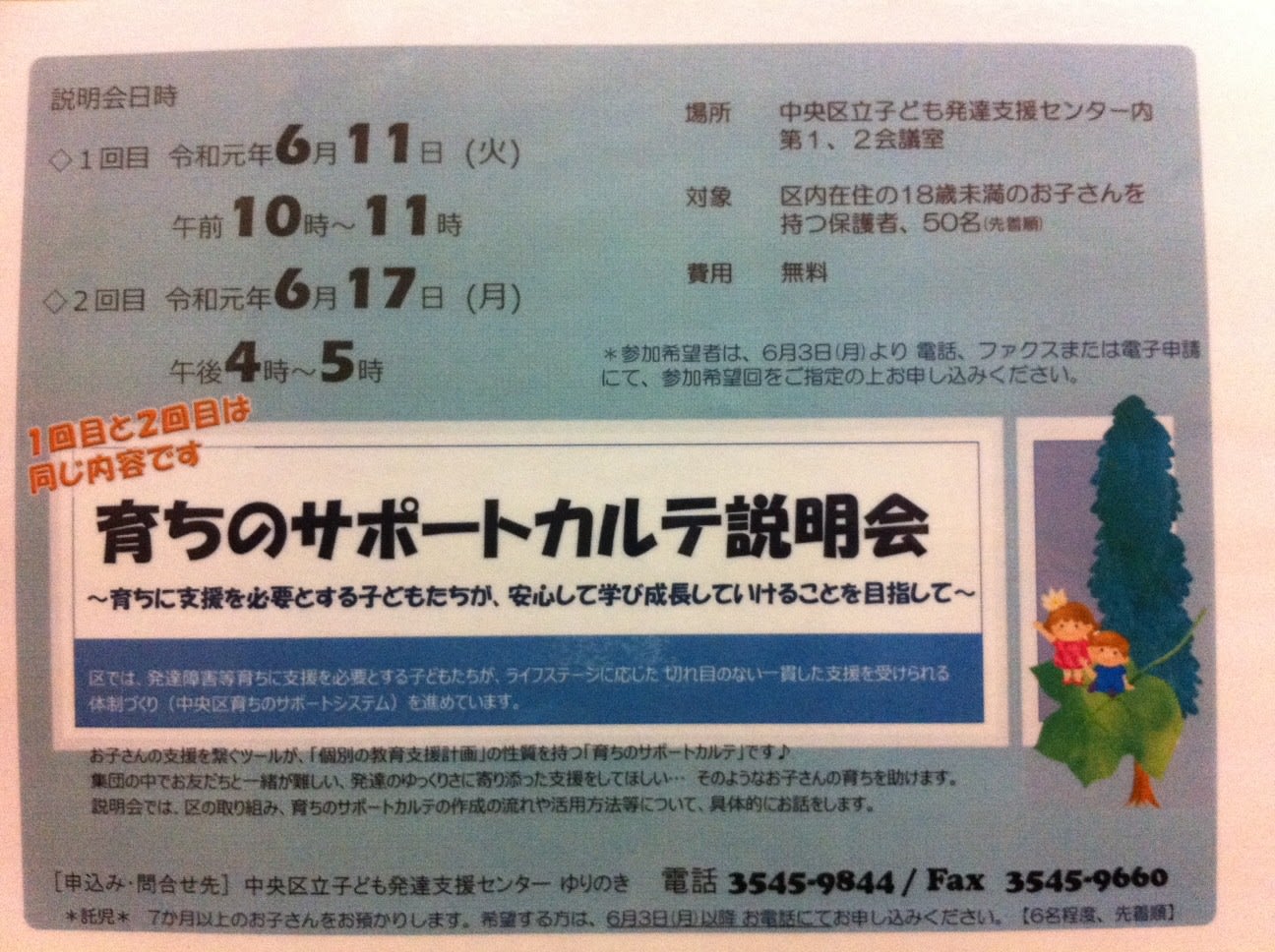判決文全文は入手できておらず、新聞からのまた聞きで書きます。
昨日の強制不妊判決は、棄却であったものの、旧優生保護法が、憲法13条の幸福追求権のひとつ「生み育てることを自らが判断して決定する権利」の侵害で、違憲とし、社会が一歩前進した判断がなされました。
同じ過ちを繰り返さぬことを、そして、強制不妊を受けられたかたの救済がなされることを見守って参ります。
********朝日新聞2019.5.29*******
https://digital.asahi.com/articles/ASM5W7HWZM5WUTIL052.html
強制不妊判決「8合目までいって落ちた」 請求阻んだ壁
杉原里美、徳島慎也 山本亮介、申知仁 2019年5月29日05時00分
旧優生保護法で不妊手術を強制された人たちが国を訴えた一連の裁判で、仙台地裁は28日、初めて「法律は違憲」と判断した。自らの意思で子どもを産み、育てることは憲法が保障する権利と認めたが、損害賠償の請求は棄却。政府関係者には静観する見方が広がった。
「山の8合目までいって、下りてきてしまったような印象だ」
判決後の記者会見で、原告側の新里宏二弁護団長は仙台地裁判決をこのように表現した。
「8合目まで」とした理由の一つは、判決が「子どもを産み育てるかどうかを意思決定する権利は、幸福追求権などを規定した憲法13条によって保障される」と判断したためだ。原告側の訴えの根幹部分で、日本の裁判所で明確に認めたのは初めて。判決は、不妊手術を強制した旧優生保護法を明確に「憲法違反」と断じた。
判決や原告側などによると、この権利は「性と生殖に関する権利(リプロダクティブ・ライツ)」と言われる。1994年にカイロで開かれた国連の国際人口・開発会議で提唱され、人々が身体、精神、社会的に健康な状態で、子どもを持つか、持つならば、いつ、何人持つかを自ら決定する権利のことをいう。95年に中国で開かれた世界女性会議でも合意された。
日本は両会議に加わり、障害者への強制不妊の項目を削除する96年の優生保護法改正の契機にもなった。しかし、欧米を中心に、宗教的な理由で避妊や人工妊娠中絶の権利が制限され、訴訟などでも激しく争われてきた状況と異なり、国内では判例が積み重なることはなかった。
この日の仙台地裁判決は性と生殖に関する権利について、「子を産み育てることを希望する人にとって幸福の源泉。人格的生存の根源にかかわるもので、憲法上保障される個人の基本的権利だ」との考えを示した。
その上で、旧優生保護法については「優生上の見地から不良な子孫の出生を防ぐという理由で不妊手術を強制し、子を産み育てる意思を持つ人の幸福の可能性を一方的に奪い去り、個人の尊厳を踏みにじるものだ」と厳しく非難した。(杉原里美、徳島慎也)
訴えを阻んだのは
訴えを8合目で阻んだのは、何だったのか。
不法行為に対する損害賠償の請求権は、発生してから20年の「除斥期間」が経つと消滅するとされている。最高裁が89年に「被害者の認識を問わず、一定の時の経過によって法律関係を確定させる」ためとして判示した。これまで、訴訟で例外が認められたのは、予防接種の後遺症で訴訟を起こすことが不可能になったり、殺人事件の遺族が、事件発生すら知らなかったりした場合だけだ。仙台地裁も「特別の規定」がなければ、除斥期間を適用しなければならないという前提で検討した。
判決は、旧法が96年に改正されるまで長年存続し、同法が広く推し進めた「優生思想」が国内に根強く残っていた現実などに着目。本人らが手術を裏付ける証拠を入手するのも難しく、「手術から20年経つ前に提訴するのは困難で、国会が立法措置をとることが必要不可欠だった」とまで述べた。
ただ、立法をしなかったことは、直ちに違法となるわけではない。判決は具体的にどんな賠償制度を設けるかは「国会の合理的な裁量に委ねられている」と述べたうえで、国内では「リプロダクティブ・ライツ」をめぐる法的議論の蓄積が少なく、司法判断もない状況を検討。立法措置を怠った責任を国会に問えるほど、明白な問題ではなかったと結論づけた。
ベテラン民事裁判官は「除斥期間は『20年』という長期間を確保し、法律上の紛争に区切りを付けるもの。それを超えて賠償を認めるのはなかなかハードルが高い」と、請求棄却の判決に一定の理解を示した。一方で、「旧優生保護法を明確に違憲・無効と述べた判決には十分な救済が必要だ、との思いが込められているのでは」と話した。
新里団長は「憲法判断しながら、『蓄積がなかった』と逃げるのは、優生被害に向き合えていない」と批判する。「今後の裁判でクリアできる論点。控訴審できちんと反論したい」と述べた。(山本亮介、申知仁)
菅官房長官「主張が認められた」
判決を前に、政府や国会議員の間には、賠償を認めるような「厳しい判決もあり得る」との見方も出ていた。それだけに、内容が伝わると「オーソドックスな判決だ。他の国賠訴訟に影響が出る内容ではなかった」(与党幹部)との受け止めが広がった。菅義偉官房長官は、判決直後の記者会見で「国の主張が認められた」。4月に成立した一時金支給法を踏まえ、今後の対応については「着実な一時金の支給に向けて全力で取り組んでいきたい」と述べるにとどめた。
与野党は判決次第で国会の意思を明確にするため反省とおわびの決議をすることも検討していたが、与党は請求棄却の判決を受けて見送る方向だ。
一方、「旧法は違憲だとの判断は重い」(田村憲久・元厚生労働相)との声も。支給法や、成立時に発表した安倍晋三首相の談話は旧法の違憲性をあいまいにしており、違憲だったとする判決との整合性を問われる可能性もある。
社会に大きな問題提起 名古屋学院大の加藤雅信教授(民法)の話
不妊手術の強制が憲法違反だと裁判所が判断した点は、市民も法律家も納得するだろう。1996年に旧優生保護法が改正され、不妊手術の規定が削除された際、原告らの損害賠償を求める機会を確保する法律を作らなかったことが違法とは言えないとした点も、無理のない判断ではないか。当時の日本には「生殖に関する自己決定権」の議論や蓄積がなかったからだ。もし一時金支給法の立法がなければ、判決が「救済立法の必要性」を説いた可能性もある。原告は自身の被害回復は果たせなかったかもしれないが、社会に大きな問題提起をしたと思う。
責任を被害者に追いかぶせた 立命館大学副学長の松原洋子教授(生命倫理)の話
旧優生保護法の対象とされた障害者のリプロダクティブ・ライツが憲法で保障されると司法が判断した波及効果は大きい。一方、原告の請求を退ける根拠として「法的議論の蓄積が少ない」「司法判断が今までなかった」という論法を立てたことにやりきれなさを感じる。障害者にとって訴訟を起こすのは困難という大前提があるにもかかわらず、提訴しないと始まらないのか。人権侵害については長年、被害者や支援団体が声を上げ続けており、厚生労働省や国会も問題を認識していた。提訴や法的議論がなかったことの責任を被害者に負わせるのはおかしい。
プロダクティブ・ライツ、改めて議論を 明治学院大学の柘植あづみ教授(医療人類学)の話
日本でも1990年代には、リプロダクティブ・ライツを施策に反映させようと検討されていた。にもかかわらず、2000年ごろから、国会などで性教育への批判や、性差別をなくそうとして使われたジェンダー・フリーという用語への反発が広がり、この言葉もほとんど使われなくなった。その結果、日本はリプロダクティブ・ライツをめぐっては国際社会から取り残された。
今回の判決は、本人の意思に関係なく、国家が子どもを産めなくするのを強制したことが個人の権利を侵害していると認めた画期的なものだ。これを機に、リプロダクティブ・ライツについて改めて話し合われることを期待する。
********毎日新聞2019.5.29*******
https://mainichi.jp/articles/20190528/k00/00m/040/254000c
強制不妊訴訟仙台地裁判決 救済遅れの責任問わず
毎日新聞2019年5月28日 22時09分(最終更新 5月28日 22時42分)
旧優生保護法を巡って初めて下された28日の仙台地裁判決は、旧法の違憲性を明確に認めた一方、少なくとも現時点では立法措置が必要不可欠だったとはいえないとして賠償請求を退けた。結果的に主張が認められる形となった国は安堵(あんど)するが、原告らは違憲判断を背景に引き続き国に謝罪を求める構えだ。
「議論少なく」で国免責
判決は、原告の人権侵害を正面から捉え、憲法13条に規定されている幸福追求権から「新たな人権」を導き出し、旧優生保護法が憲法に反していたと明確に指摘した。しかし、立法措置を講じなかった国の責任についての判断では、一転して慎重姿勢をみせ、敗訴判断を導いた。
原告側は訴訟で、不妊手術を強制させた旧法の規定が「子を産み育てるかを決める権利(リプロダクティブ権)」を侵害したと訴えていた。憲法は、13条で幸福追求権を規定している。裁判所はこれまでも社会の変化や時代の要請に基づいて、この規定から人格権やプライバシー権をはじめ、憲法が明記していない具体的な権利を導いてきた。
今回、地裁は「子を産み育てることは幸福の源泉となり得る。人格的生存の根源に関わり、憲法上保障される個人の基本的権利だ」と言及。「優生手術を受けた場合、一生涯にわたり救いなく心身ともに苦痛を被り続ける。権利侵害の程度は極めて甚大だ」と指摘し、リプロダクティブ権に基づいて、裁判で救済を求めることを認めた。初の判断とみられる。
判決は続いて、立法措置を講じなかった国の立法不作為を検討した。原告側は、手術を受けた当事者を救済する法整備を国会が怠ったと主張し、国には国家賠償法に基づく賠償責任があるとした。
立法不作為を理由とした国の賠償責任が認められるのは、かつて「容易にしがたいような例外的な場合に限る」とするのが裁判所のスタンスだった。
しかし、2001年に熊本地裁がハンセン病患者への強制隔離政策を違憲と認定し、国会の立法不作為の責任を認めた。最高裁も05年、在外邦人の選挙権行使を制限する公職選挙法の規定を違憲とし、立法措置を長期間講じない場合は賠償責任を負う場合があるとの判断を示した。司法は、国会の怠慢が極めて重い事案に限っては、救済の道を開いてきた経緯がある。
今回の判決で、地裁は、手術を受けた人が賠償を求めることができる制度を立法する必要があったことは認めた。さらに、旧法によって、優生思想が国民の間に根強く残り、当事者が賠償を求めるなどの声を上げにくかった可能性にまで言及した。
ところが判決は、こうした事情からリプロダクティブ権を巡る法的議論が深まらず、旧法規定が憲法に違反するかどうかの司法判断がなされてこなかったとし、「国会が立法措置をとることが必要不可欠で、明白だったとは言えない」と原告の主張を退けた。
ある現役裁判官は「1996年の改定前の早い時期から、旧法の問題性は指摘されていた。原告が権利行使できない特別な事情があったと認めているのだから、原告を救済する方向で考える余地もあったかもしれない」と指摘する。
今回の判決が、他の訴訟に与える影響は不透明だ。ただ、仙台訴訟は、手術当事者に一時金などを支払う内容の救済法が制定される前の今年3月に結審したため、救済法の妥当性などが考慮されないまま言い渡された。他の訴訟の判決では新たな論点として加味されるため、今後、救済法への評価が加わって異なる司法判断が示される可能性はあるとの見方もある。【服部陽】
救済法見直し否定的
政府・与党や国会は、今回の判決を楽観していたわけではない。訴訟の進行は原告側寄りとの見方が強く、国側は仙台地裁から旧法の憲法適合性の意見を求められても「当時は合憲」と強気の主張はせず明言を避け続けていた。救済の議員立法作りに関わった与党幹部は「救済の遅れや立法不作為がもっと糾弾されると思っていた」、厚生労働省の幹部も「負けるかもと覚悟していた」と語る。
それだけに、請求棄却の結論には安堵(あんど)感が広がっている。菅義偉官房長官は28日の記者会見で「国家賠償法上の責任の有無に関する国の主張が認められたものと聞いている」と述べた上で、4月に成立した救済法に触れ「着実な一時金の支給に向けて全力で取り組んでいきたい」と語った。
国側にとって、被害者に一律320万円の一時金を支払う救済法が既にある意味は大きい。判決が不作為を認めなかった被害救済の立法を先取りしたとも解釈できるからだ。超党派議員連盟にいた与党議員は、他地裁の判決がまだ出ていないことを踏まえ「(救済法の)見直しはない」と断言。事務局長を務めた福島瑞穂参院議員も「今回の結果は個人的に残念」としつつ、救済法は「全会一致で成立している」と維持するのが妥当との認識を示した。
立法過程では、謝罪を盛り込んだ国会決議を今の通常国会に提出する動きもあったが、動きは与野党とも鈍い。「今、決議を出しても、救済法の範囲は超えない。責任は国会、政府にあると明確にしており、大きな事情の変更がない限り難しい」(与党幹部)との声もある。
ただ、救済法は、前文で被害者への「反省とおわび」を示しているものの、旧法の違憲性を認めた内容ではない。立法の与党ワーキングチーム座長を務めた田村憲久・元厚労相は「(判決が)どの時点で違憲となったのかよく分からない」としながらも「違憲判決が出たのは地裁とはいえ重い」とも指摘する。
原告弁護団長の新里宏二弁護士は判決後の記者会見で「リプロダクティブ権の侵害が違反と認められたのは大事」と違憲判断を評価した。敗訴では「賠償金や謝罪(を求めるの)は難しい」とする一方で「(救済法は)不十分な制度で被害者が使いやすくない。申請も伸びておらず、名前が特定されている人にきちんと情報が届いていない」と救済制度の改善を訴えた。【阿部亮介、高橋克哉、岩崎歩】
慶応大教授・小山剛氏(憲法学)
裁判長が「憲法判断を回避しない」と述べたことから注目された判決は、原告の請求を棄却した一方、旧優生保護法を「個人の尊厳を踏みにじるもの」として違憲・無効であると断罪した。請求が棄却されたことに原告は不満だろうが、明確に違憲と断じ、立法府に対応を促した判決の意義は大きい。被害者救済法にも大きく影響を与えることになるだろう。
適切な被害救済を怠ってきたとする国の立法不作為については、「立法措置をとることが必要不可欠」と言及しながらも、国会にとってその必要性は明白ではなかったとの理由で「少なくとも現時点」では違法と評価できないとしている。このことは裏返せば、今後も救済立法の不作為を国が漫然と継続した場合には、将来、同様の国家賠償請求が認められうることを示唆している。
この判決によって、ボールは再び立法府に返された。4月下旬に施行された被害者救済法は、旧法が合憲であるとの前提に作られたもので、給付金の趣旨や金額、救済制度を積極的に周知する仕組みなどの面で立法府には再検討が求められる。【聞き手・安達恒太郎】
立教大教授・関礼子氏(環境社会学)
旧優生保護法の違憲性を認めながら、それを推進してきた国の賠償責任も立法不作為も認めなかった。司法の判断は、「悪法も法なり」との観点で、差別が正当化された社会の中で声を上げられなかった弱い立場の人たちの置かれた状況を全く踏まえていない。障害のある人もない人も共生できる社会を目指す「ノーマライゼーション」の理念が広がりつつある今、司法は時代と呼吸していないと言わざるをえない。
人権救済の点で、権利を行使するにはあまりにも弱い人たちと、国との力関係には歴然とした差がある。そうした弱者の声を積極的に拾うことが国や司法にも求められるのではないか。
多くの人は、旧法が人権感覚から大きく逸脱していると考えると思う。ただ、時代錯誤な法律がつい20年ほど前まで存在し、今回の判決によって声を上げても報われない弱者が存在することが浮き彫りになった。こうした弱者の声に耳を傾けてこなかったのは私たち自身でもある。どこにでも潜む差別や人権侵害の芽を摘むには、私たち自身も、すぐそこにある「歴史」について議論することが大切だ。【聞き手・二村祐士朗】