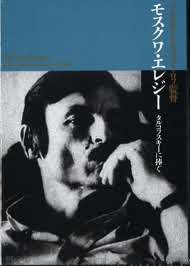1945年夏とタイトルが出るので、戦争が終わる頃だとはわかるが、その前なのか後なのかは必ずしもはっきりしない。
木下は念願だった「戦場の固き約束」の準備中で、戦争が終わったことですべて済んだように見えるのを避けたかったのではないかと思える。
菅原文太は1961年に倒産した新東宝から移ってきて67年に東映に行くまで松竹にいたのだが、ここでは村の有力者の息子でヒロイン岩下志麻に目をつける戦争犯罪者という仇役で登場、のちの「人斬り与太」シリーズのようなワルぶりを見せる。
文太の中国での蛮行を鋭い横移動撮影と省略法で暗示的ながらはっきり描くフラッシュバックは、「固き約束」の一種の予行演習のようなつもりもあったか。
残念ながら映画化は実現しなかったが。
ここがあるので、文太が目をつけた岩下志麻を長い一本道でいったんすれ違った後引き返して追ってくるサスペンスが効いてくる。
雷鳴の使い方、豪雨の効果なども秀逸。
おしなべて横移動の使い方、カッティングの適切さなど、これだけ名人芸的に上手い演出というのがあったのだなと思わせる。
北海道を舞台にしていることもあって、広大な土地を馬が闊歩し、ライフルを撃ち合う風景はまるで西部劇。
先住民と後から来たよそものとの対立というのは、実は西部劇でも「シェーン」「天国の門」などで扱っていたが、日本の旧弊な体質は北海道という開拓地でも変わっておらず、さらに戦争による歪みが大幅に影響して、昔の西部劇的な勧善懲悪の爽快さはおよそない。
音楽にアイヌの口琴ムックリを使っているが、アイヌ自身は出てこない。
どこまで作り手が意識していたかわからないが、先住民=開拓者たちも近代日本の拡大政策に乗ってきたわけで、その延長上に大陸侵略があったことも伺わせる。











 - YouTube
- YouTube