おはようございます。お盆の頃、出掛けた京都の旅日誌も遅れにおくれ、ようやく最終盤に入ります。旅行の楽しみの一つは、お食事。ぼくはこれにお酒が加わりますが(汗)。思い出のお食事、ちょっと振り返ってみましょう。
京都の夏といえば、川床料理。暑い暑い日だったけど、夕方、貴船の”真々庵”の川床に座ったらびっくり。ひんやりするほどの川風が吹いている。もうこれだけで、お腹がぐー。はやくも特等席で、食事をはじめていた男と女がいた。夫婦にはみえなかった、お忍びか(爆)。
京懐石風料理。ビールで乾杯。
先附けが出てくる。
籠をとると・・・みたこともないお料理!鱧の子白線寄せ、小倉蛸、大和芋、煎り銀杏。
そして、第二弾は御造り。鱧の落としほか。京都の夏は鱧!冷酒一本、おねがいします!
楽しい、おいしいお料理が次々と出てきて、いよいよ、さよならご飯。湯葉茶漬け。
貴船の夜は更けていったのだった。
こちらは、大徳寺三門。二層目を千利休が寄進し、金毛閣と名付け、自身の木像を安置した。秀吉に、利休の下をくぐらせたといちゃもんをつけられ、切腹の遠因となった。
山門近くの塔頭、大慈院内で精進料理を頂いた。

すべて、食べ終わると、お椀をこうゆうふうに重ねることができる。
大徳寺前の商店街には大徳寺納豆や一休こんぶのお店が並んでいた。

あとひとつは次回に。




























 普通、丸いつぼみの状態で見かけることが多いので、線香花火みたいだと、
普通、丸いつぼみの状態で見かけることが多いので、線香花火みたいだと、



 早く、取りに来て!
早く、取りに来て!

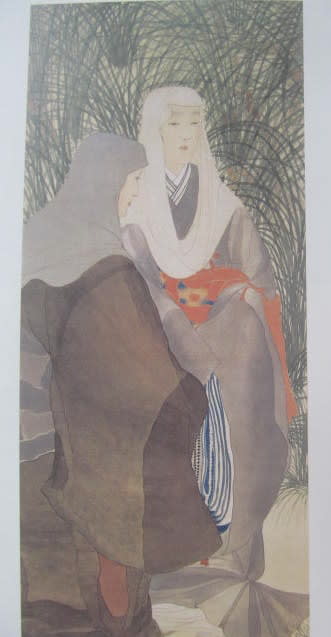
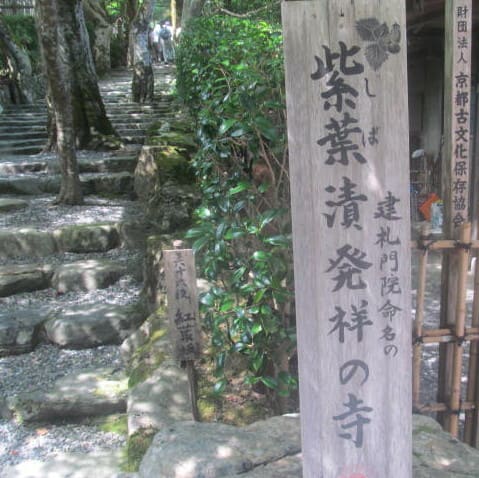





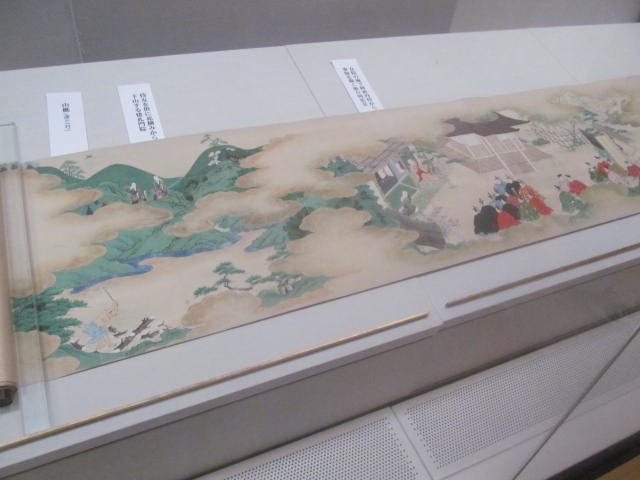
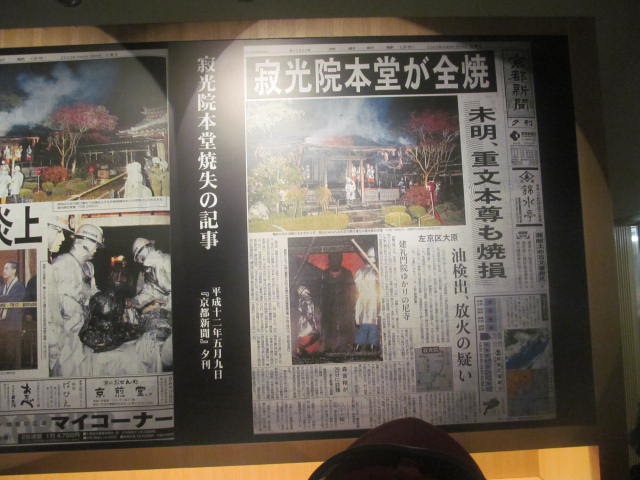
















































 遊びの神様、ありがとうございます。
遊びの神様、ありがとうございます。


















