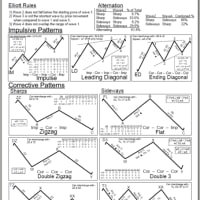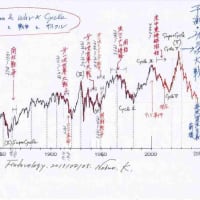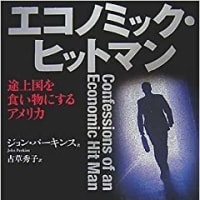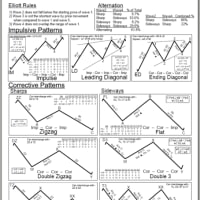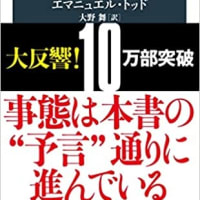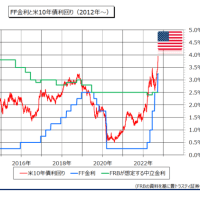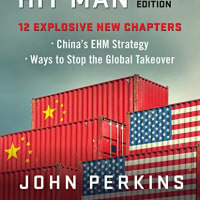1000人を看取った緩和ケア医、45歳の死 がんに侵されながらも「自分らしさ」貫いた最期の日々
神戸市灘区にある関本クリニックは、がん患者の在宅ホスピスケアに取り組み、24時間体制で医師の訪問診療、看護師の訪問看護などを行っている。関本剛さんはその院長を務め、約1000人の看取りに携わってきた。だが、自らもがんに襲われ、今年4月に息を引き取った。45歳の若さだった。
病が判明してから2年半、体の限界まで緩和ケア医として勤務し、患者とその家族に寄り添い続けた。8月14日、高校時代の同級生が企画したお別れ会には、人柄をしのんで国内外から約250人が集った。
剛さんの母関本雅子さんは、日本ホスピス在宅ケア研究会理事を務め、緩和ケアの先駆者として知られる。親として、先輩の医師として息子の闘病を見守り続けた雅子さんに、剛さんの生涯を振り返ってもらった。
■「余命2年」
剛さんは神戸市東灘区で生まれ、兵庫の緩和ケア医療をけん引してきた母親の背中を見て育った。小学5年の時、脳梗塞で祖父と死別。寝たきりの延命治療に衝撃を受けたことが、終末期医療への道を志す原体験となった。
関西医科大を卒業後、消化器内科医として同大病院に勤務。その後、母親も勤めた六甲病院(同市灘区)で緩和ケア医として一歩を踏み出した。2015年、母親が開業した関本クリニックへ。3年後、院長に就いた。
だが翌年10月、末期の肺がんが見つかる。検査の結果、脳にも転移しており「余命2年」と宣告された。雅子さんは「医師だけに病状は理解していたけれど、すぐには受け入れられずに苦しんでいた。相当時間を費やした」と打ち明ける。
特に、妻と小学生の子ども2人の将来を気にかけていたという。せめて教育費や生活費を残そうと、体が続く限り仕事を続ける決意を固める。それが結果的に医師としての成長につながった。
■亡くなる1カ月前まで診察室に
抗がん剤治療を受けながら、亡くなる1カ月前まで診察室で患者を診た。自らが末期がんであることを告白。医師と患者の立場を超え、共感し合う境地に至った。
「同じ立場で抗がん剤治療のつらさ、不安を理解しながら寄り添っていた」と、雅子さんは指摘する。
剛さんはもともと消化器内科を専門としていた。抗がん剤治療についても熱心に研究しており、詳しかった。その薬剤を投与された時に「副作用のきつさを実感した」と雅子さんに語っている。抗がん剤がどんなものか、患者の立場で理解できるようになったのだ。
診察で同じ抗がん剤投与を受けている患者に出会うと、どんな時にどんな症状が出るのか、理論を越えたレベルで理解できた。患者の訴えを最後まで聞き、発する「しんどいね」の一言は、ひときわ相手の心に響いた。
20年9月には、著書「がんになった緩和ケア医が語る『残り2年』の生き方、考え方」(宝島社)を出版し、大きな反響を呼んだ。
■自宅で最期を
クリニックは、住み慣れた自宅で家族に囲まれて臨終を迎える環境づくりに力を入れる。剛さんも自宅での最期を望んだ。
ただ脳腫瘍が進行すると、痛みやまひに加え、怒りっぽくなるなど人格に大きな変化が生じる懸念がある。母子は議論を重ね、一つの計画を立てる。精神状態が不安定になれば病院で、穏やかならば自宅で最期を迎えるというものだった。
剛さんは家族との時間も大切にした。闘病中、何度も家族でスキー旅行に出かけた。趣味のトロンボーン演奏も続けた。「おとなしくしなさいと注意するほどでした」と雅子さん。
亡くなる直前に容体が急変して入院、難手術に臨んだが、心配された人格の変化はなかった。雅子さんは病床の息子にささやいた。
「表情はとても穏やかよ。おうちへ帰ろう」
剛さんは死生学の権威で、上智大の故アルフォンス・デーケン名誉教授の言葉を座右の銘にしていた。〈人間は死ぬ瞬間まで成長し続けることができる〉 「最期は、医師として、親として、私を超えた」と雅子さん。まさに目標とする死生哲学を体現した人生だった。
■生前に撮ったビデオメッセージ
8月14日のお別れ会は、母校の六甲学院中学・高校(同市灘区)の講堂で開かれた。
舞台には遺影や、故人が趣味で演奏していたトロンボーンが飾られた。恩師、同級生、友人らが代わる代わるあいさつに立った。そしてスクリーンに、剛さんが生前収録していたビデオメッセージが流された。
収録は亡くなる1年半前、2020年10月10日に行われた。通夜、葬儀でも上映されたという。
「最高の人生でした」と、剛さんは生涯を振り返っている。高校の時に目標とした緩和ケア医になれたこと。サッカー、スキー、バンド演奏と趣味を堪能できたこと。宴席で友人らと盛り上がったこと...。「希望の職業に就き、スポーツや好きな趣味を楽しめた。家族、友人、先輩、後輩、同僚に恵まれた」と、感謝の言葉を伝えた。
一転して、「後悔があるとすれば...」と、言葉を続ける。「若い妻、幼い子どもを残すことだけが心残り」と打ち明けた。
「私がいなくなった後も、これまで通り、遊びに行くことや、寄り合う機会があれば家族を誘ってほしい。できれば私の代わりに見守ってほしい」。ビデオの視聴者に向かって、頭を下げた。
そして、ユーモラスに締めくくった。
「私は皆さんより先にあちらの世界に行き、先輩たちと再会して酒席の日々を送ります。皆さんは急がなくていいです。でも遠い将来、お越しになった時に備えて、あちらでのおいしい居酒屋を探しておきます。だから安心して、楽しみに、ただしゆっくり来てください」
■「威風堂々」のメロディーに送られ
恩師や同級生は、それぞれの視点から剛さんの人となりをしのんだ。
同級生の会社員上原琢嗣さん(45)=芦屋市=は、「剛ちゃんにがんを告白された時は信じられなかった。でも最後まで何も投げ出さなかった。仕事、家庭、それから同窓会の役員も全てやり遂げた。その姿に感動しています。友人として誇りです」。
神戸市立医療センター中央市民病院の西本哲郎医師(45)は、剛さんが生前「医師の仕事は臨床、研究、教育の三本柱が大切」と話していたことを紹介。「大阪で緩和ケアの勉強会を開き、仲間を誘ってはアドバイスをしていた」と明かした。
バンド仲間も駆け付け、ジャズやクラシックを演奏。最後の曲は、エルガーの「威風堂々」だった。本人が生前希望していたという。勇壮なメロディーが会場に響く。使命を果たし、胸を張って旅立つかのようだった。
死期が迫る中で、大切な人たちに別れを告げる方法にも目を向けていた剛さん。緩和ケアの可能性を最後まで追究した人生だった。(津谷治英)