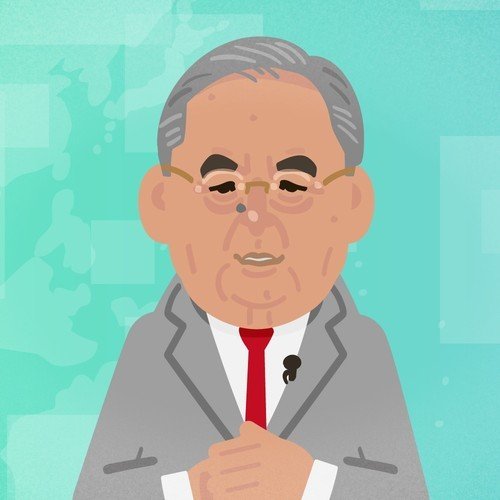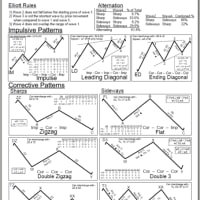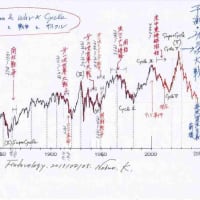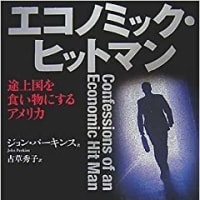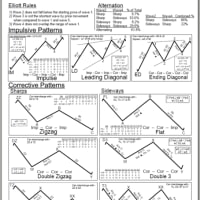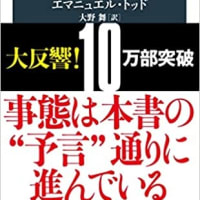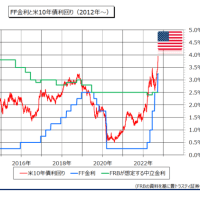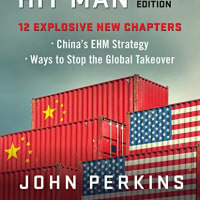- 旧南部のシンボルが消えた
- 米国の歴史そのものの見直しへ
- 「米国版文化大革命」の行きつく先は・・・
旧南部のシンボルが消えた
米国から、奴隷制度を肯定した旧南部のシンボルが姿を消した。
ミシシッピ州議会は28日、旧南部連合の軍旗を一部に取り入れた州旗を廃止する法案を下院で91対23、上院で37対14で可決し、同州の旗は別のデザインのものに代わることになった。
赤地の正方形に青色のX字型の縞が重なりその中に旧南部連合の州を意味する13の星をちりばめた南部軍旗は、南北戦争終了後も南部諸州の歴史的伝統として廃止することに抵抗する勢力が少なくなく、ジョージア州でもそのデザインを一部に取り入れた州旗を2001年まで残していた。

同年ミシシッピ州でも旗の正当性をめぐって州民投票が行われたが64%が存続を求め、2016年にも州民投票の訴えが起きたが議会で多数を占める共和党保守派がストップした。
それが今回一転して州旗の廃止が決まったのは、いうまでもなく全米に吹き荒れている「黒人の命も大事だ」運動の力だ。

米国の歴史そのものの見直しへ
南部連合のロバート・リー将軍の銅像も撤去され、人種差別に関わる象徴はすべて排除しようという動きの中で、南部軍旗の命運も尽きるのは当然だった。

全米最大の自動車レースNASCARは先月この旗をレース場から排除することを決めた。NASCARはもともと南部で誕生した経緯からレースカーに南部軍旗をデザインしたり、観客が同じデザインで横長の「反逆の旗」を打ち振るのがそれまでは見慣れた光景だった。
さらに、カントリーソングの女性グループでグラミー賞も受賞した「ディクシー・チックス」も「ディクシー」が南部の総称で、南部連合軍の行進曲も同名だったことからこの際グループ名を「ザ・チックス(かわい子ちゃん達)」だけにに変えると発表したり、旧南部を彷彿させる名称やシンボルが一掃されることになった。

しかし、人種差別の歴史を否定する動きはそれだけにとどまらず、米国の歴史そのものの見直しにまで迫り始めている。
「米国版文化大革命」の行きつく先は・・・
サンフランシスコで19日、人種差別に抗議するデモ隊がゴールデンゲート公園に設置してあったフランシス・スコット・キーの銅像にロープをかけて引き倒した。

キーは、独立戦争の最中にボルチモア港で英国の軍艦の砲撃に耐えた砦に星条旗が翻っている様子を詩に詠い、それが後年「星輝く旗(星条旗)」として米国の国歌に採用された人物だ。
キーが奴隷の持ち主だったということがその理由だが、歌詞にも問題があると言われ始めている。
「おお、見えるだろうか。夜明けの光の中、一際輝くその姿に我々が誇り高く大声で叫ぶ。
その太い縞模様と輝く星印は、夜を徹する危険な戦闘の間も砦の上に雄々しく翻っていた。
大砲が火を吹き、砲弾が破裂する中、我々の旗は夜通しそこにあった。
星輝くその旗はまだなびいているのだ。自由の地、勇者の故郷に」(著者訳)
この最後の「自由の地」はあくまでも自由な白人の土地のことで、自由を否定された奴隷は無視されているので国歌として相応しくないというのだ。
アメリカンフットボールのNFLなどで、試合開始前の国歌斉唱の折に黒人選手が膝まづいて抗議の姿勢を示す動きも広がっており、国歌を愛唱歌「アメリカ・ザ・ビューティフル」などに変えるべきだという声も高まっている。
こうした歴史を否定する動きについて、中国共産党の英語紙「グローバル・タイムズ」紙は「米国版文化大革命」と評したが、この「文革」どこに行きつくのだろうか。
【執筆:ジャーナリスト 木村太郎】
【表紙デザイン:さいとうひさし】