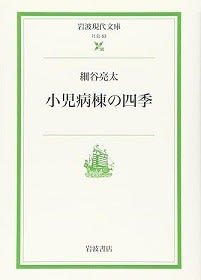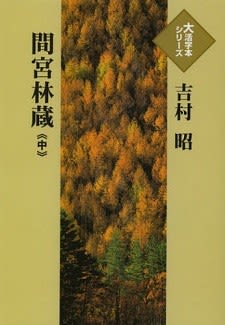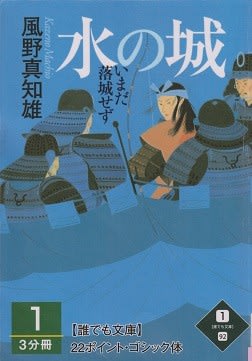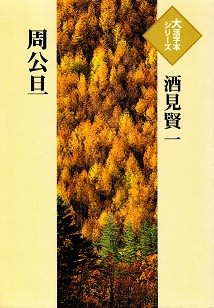テレビでもお馴染みの歴史学者磯田道史氏の著書『無私の日本人』を図書館から借りて読んだ。丁寧に史料にあたって、それを平易な文章で小説に仕上げており、読後に満足感が得られた。
内容は、三話に分かれており、江戸中期から後期、明治にかけて実在した人々を時代背景とともに物語ってゆく。第一話は穀田屋十三郎で、伊達藩仙台近くの貧しい宿場町吉岡に生まれた商人。第二話は中根東里で、江戸時代を通じて空前絶後の詩才の持ち主ながら、栄達を求めず、極貧のうちに村儒者として死す。第三話は大田垣蓮月で、津藩家老の娘として京都の花街に生まれながらも家庭に恵まれず、一流の歌人であったにもかかわらず、尼僧として京都郊外に庵をむすび貧しい者の世話をした。
それぞれが、私利私欲にとらわれることなく、貧しい生活にあえぐ人々のために「無私」の活動をした人達。わたしは知らなかったが、この作品の中の穀田屋十三郎の話は2016年5月に『殿、利息でござる!』として映画化されており、その原作でもある。
武士の時代であった江戸期の「民生」については、なかなか理解しにくい。今の戸籍簿にあたる「人別帳」は寺の管轄で、寺は戸籍役場でもあり、婚姻や生死に関わる記録・管理は僧侶がになっていた。そのあたりまでは分かるのだが、さらに、庶民の教育や福祉といった、今の厚生労働省や文部科学省の仕事は誰が担っていたのだろう。それが、ずっと疑問だったが、この本を読んで少し理解できたように感じた。早い話が、篤志家達に頼っていた、ようだ。ボランティア活動の様なもので、他人の困難を自分のこととして世話をする人達が確かにいて、その方たちが本来幕府がなすべきことを代わりに担っていたらしい。あるいは、そのあたりが江戸という時代の抱えた大きな矛盾だったのかもしれない。

こちらは、ネットから借用した画像。

こちらが、わたしが図書館から借りて読んだ大活字本。
閑話休題ーわたしが社会人になったのは昭和の50年代だったが、その頃「株式会社」というのは社員のために存在する、という社会通念が残っていたように思う。社員の生活が第一で、株主に配る配当金は「おこぼれ」と言っては言い過ぎかもしれないが、後回しだった。投資家の多くが、良い会社だから配当は少なくても投資しよう、としていた。それが、いつの間にかアメリカから来た株主優先の社会通念に変化してしまった。株式会社は、投資した株主に利益を還元するために存在するもので、従業員はそのための手段にすぎなくなった。「新資本主義」とも言われるが、金を投資という名で動かしてゆくことが最優先されている。バブル期のころだが、仕事の先の社長が証券会社に勤める友人から「金を転がせばいくらでも儲かるのに、何で汗して働いてんだ?」と、言われたという。IT技術の進歩は、さらにそれを加速し、生産するよりも、資金運用することに重点を置く社会になってしまった。汗して何かを作る人間よりも、パソコンの前で投機する者の方に金が集まってゆく。特に問題なのは、外国為替市場における差額レートを利用したFXと言われる取引だ。本来は、労働者に配分されるべき利益が吸い取られてゆく。これで、人心が荒廃しない訳がない。多くの人がその点を危惧しているが、悲しいことに人は目先の利に惹かれてしまう。「トリクルダウン」など夢のまた夢。格差は広がり、アルバイト感覚で犯罪に走る若者が増える一方だ。このままでは「負のスパイラル」に陥るように思えてならない。「無私」の精神から遠くなってゆくばかり。あるいは、悲観が過ぎるかもしれず、杞憂なのかもしれない。自分でも、過度な心配、であれば良いと思っている。
内容は、三話に分かれており、江戸中期から後期、明治にかけて実在した人々を時代背景とともに物語ってゆく。第一話は穀田屋十三郎で、伊達藩仙台近くの貧しい宿場町吉岡に生まれた商人。第二話は中根東里で、江戸時代を通じて空前絶後の詩才の持ち主ながら、栄達を求めず、極貧のうちに村儒者として死す。第三話は大田垣蓮月で、津藩家老の娘として京都の花街に生まれながらも家庭に恵まれず、一流の歌人であったにもかかわらず、尼僧として京都郊外に庵をむすび貧しい者の世話をした。
それぞれが、私利私欲にとらわれることなく、貧しい生活にあえぐ人々のために「無私」の活動をした人達。わたしは知らなかったが、この作品の中の穀田屋十三郎の話は2016年5月に『殿、利息でござる!』として映画化されており、その原作でもある。
武士の時代であった江戸期の「民生」については、なかなか理解しにくい。今の戸籍簿にあたる「人別帳」は寺の管轄で、寺は戸籍役場でもあり、婚姻や生死に関わる記録・管理は僧侶がになっていた。そのあたりまでは分かるのだが、さらに、庶民の教育や福祉といった、今の厚生労働省や文部科学省の仕事は誰が担っていたのだろう。それが、ずっと疑問だったが、この本を読んで少し理解できたように感じた。早い話が、篤志家達に頼っていた、ようだ。ボランティア活動の様なもので、他人の困難を自分のこととして世話をする人達が確かにいて、その方たちが本来幕府がなすべきことを代わりに担っていたらしい。あるいは、そのあたりが江戸という時代の抱えた大きな矛盾だったのかもしれない。

こちらは、ネットから借用した画像。

こちらが、わたしが図書館から借りて読んだ大活字本。
閑話休題ーわたしが社会人になったのは昭和の50年代だったが、その頃「株式会社」というのは社員のために存在する、という社会通念が残っていたように思う。社員の生活が第一で、株主に配る配当金は「おこぼれ」と言っては言い過ぎかもしれないが、後回しだった。投資家の多くが、良い会社だから配当は少なくても投資しよう、としていた。それが、いつの間にかアメリカから来た株主優先の社会通念に変化してしまった。株式会社は、投資した株主に利益を還元するために存在するもので、従業員はそのための手段にすぎなくなった。「新資本主義」とも言われるが、金を投資という名で動かしてゆくことが最優先されている。バブル期のころだが、仕事の先の社長が証券会社に勤める友人から「金を転がせばいくらでも儲かるのに、何で汗して働いてんだ?」と、言われたという。IT技術の進歩は、さらにそれを加速し、生産するよりも、資金運用することに重点を置く社会になってしまった。汗して何かを作る人間よりも、パソコンの前で投機する者の方に金が集まってゆく。特に問題なのは、外国為替市場における差額レートを利用したFXと言われる取引だ。本来は、労働者に配分されるべき利益が吸い取られてゆく。これで、人心が荒廃しない訳がない。多くの人がその点を危惧しているが、悲しいことに人は目先の利に惹かれてしまう。「トリクルダウン」など夢のまた夢。格差は広がり、アルバイト感覚で犯罪に走る若者が増える一方だ。このままでは「負のスパイラル」に陥るように思えてならない。「無私」の精神から遠くなってゆくばかり。あるいは、悲観が過ぎるかもしれず、杞憂なのかもしれない。自分でも、過度な心配、であれば良いと思っている。