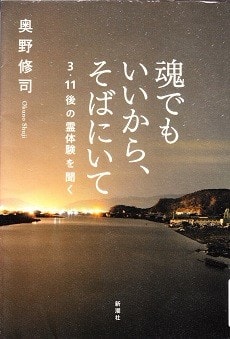図書館から借りて読んだ本を一冊。

昨年12月23日に66歳で亡くなった著者の、これは遺作とも云える作品になるだろう。
内容は、直木賞受賞作の『蜩の記』の続編で、著者の出身地である九州に設定した羽根(うね)藩シリーズの完結作となる作品。比べてはいけないのかもしれないが、やはり藤沢周平の海坂(うなさか)藩を舞台とした作品群がどうしても頭に浮かぶ。話に引き込む力では、勝るとも劣らない。が、人物の心象風景の描写に今ひとつもの足りなさを感じざるを得なかった。66歳という年齢は、今では若くして亡くなった、と言えるだろう。仕事をし過ぎたのだろうか。もう少し長く生きて、深みのある作品を残して欲しかった。残念だ。ご冥福をお祈りしたい。
余談だが、わたしも長くフリーランスで仕事をしてきて、依頼されたものを断る怖さは身に沁みて分かっている。実際に、依頼された仕事があまりに遠かったために断らざるを得なかったことがあり、その後にはペナルティーとして暫く仕事を回してもらえなかったこともあった。横暴といえばそうなのだが、仕事を握っている方が圧倒的に力が上であり、下は耐えるしかないのが資本主義社会の法則なのだ。それを逆手に取る方法も無いことはない。水面下で仕事を依頼してくれる取引先を増やしておけばよいのだ。言うは易く行うのは簡単ではないが、その不安定さを楽しむ位の気持ちで事に臨めばけっこう生き延びていける。まあ、わたしの場合は巡り合わせが良かった、とも言える。仮に今だったら、そう楽観していられないだろう。それでも、無理に仕事を受けて体を壊しては元も子もない。実際に、何人かの仕事仲間が若くして体を壊し、その内の何人かは命を落としている。その中には、わたしよりも若い人が数人いた。気持ちを落ち着けて、やれることをしっかりやっていきたい。

昨年12月23日に66歳で亡くなった著者の、これは遺作とも云える作品になるだろう。
内容は、直木賞受賞作の『蜩の記』の続編で、著者の出身地である九州に設定した羽根(うね)藩シリーズの完結作となる作品。比べてはいけないのかもしれないが、やはり藤沢周平の海坂(うなさか)藩を舞台とした作品群がどうしても頭に浮かぶ。話に引き込む力では、勝るとも劣らない。が、人物の心象風景の描写に今ひとつもの足りなさを感じざるを得なかった。66歳という年齢は、今では若くして亡くなった、と言えるだろう。仕事をし過ぎたのだろうか。もう少し長く生きて、深みのある作品を残して欲しかった。残念だ。ご冥福をお祈りしたい。
余談だが、わたしも長くフリーランスで仕事をしてきて、依頼されたものを断る怖さは身に沁みて分かっている。実際に、依頼された仕事があまりに遠かったために断らざるを得なかったことがあり、その後にはペナルティーとして暫く仕事を回してもらえなかったこともあった。横暴といえばそうなのだが、仕事を握っている方が圧倒的に力が上であり、下は耐えるしかないのが資本主義社会の法則なのだ。それを逆手に取る方法も無いことはない。水面下で仕事を依頼してくれる取引先を増やしておけばよいのだ。言うは易く行うのは簡単ではないが、その不安定さを楽しむ位の気持ちで事に臨めばけっこう生き延びていける。まあ、わたしの場合は巡り合わせが良かった、とも言える。仮に今だったら、そう楽観していられないだろう。それでも、無理に仕事を受けて体を壊しては元も子もない。実際に、何人かの仕事仲間が若くして体を壊し、その内の何人かは命を落としている。その中には、わたしよりも若い人が数人いた。気持ちを落ち着けて、やれることをしっかりやっていきたい。