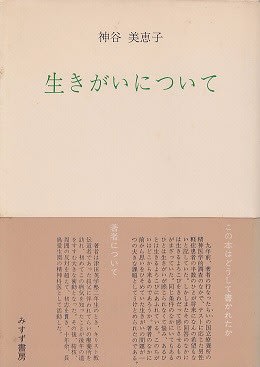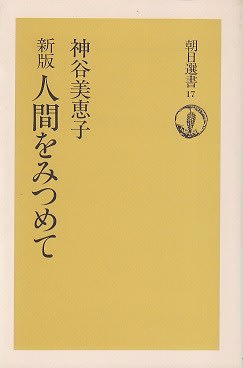ミシシッピー・ジョン・ハート。ブルースファンには今ひとつ人気がないが、「フォーク・ミュージック」と言われるジャンルでは、とても影響力が強いミュージシャンだ。実際、ギター奏法に関してはプリ・ブルースとも言え、素朴で叙情性に富み、低音弦側のタメの効いたリズムの取り方はラグタイムの要素も含んでいる。後に、この人から影響を受けたフォークシンガーは日本にも多いが、オリジナルの底深い泥臭さは失われている。そのあたりが、ブルースファンに誤解されて「軟弱」と取られている様な気もする。あえて喩えると、音楽史の流れから見てロバート・ジョンソンが後のロックに通ずる最重要プレーヤーだったのと同じで、ミシシッピー・ジョン・ハートはブルースからフォークソングに至る中での最重要プレーヤーという見方もできる。
改めて聴きなおしてみると、声の出し方があまり強くなく「語り」の要素が強い。が、ギターで低音弦を強くはじきながら高音側を絶妙のタイミングでからめてゆく奏法はすばらしい。やはり、ブルースマンだなあ、と感じる。この人の、そういったブルースの要素をしっかりと受け継いだプレーヤーをわたしは知らない。後にフィンガーピッキングと言われるジャンルで「インストラクター」の役割を果たしているステファン・グロスマンも、ミシシッピー・ジョン・ハートが好きだそうで、教則レコードにもハートの曲が取り上げられている。興味のある人は、グロスマンの演奏とジョン・ハートのそれとを聴き比べてみると勉強になるだろう。本質的な所で、全く違う音楽になっている。ただし、どちらが良いか、という問題ではない。聞き手が大切に思えることを、しっかりと聴きとるとこが肝要だ。
生まれは1893年7/3ミシシッピー州ティオック(Teoc)、亡くなったのは1966年11/2同州グレイナダ(Grenada)。1928年2月にメンフィスで2曲、同年12月にニューヨークで11曲録音して、その後は忘れられた存在だった。

初期の録音13曲を収録したCD『ミシシッピー・ジョン・ハート キング・オブ・ザ・ブルース4、PCD-2259』。ただ、CDジャケットの写真は若い頃のものとは思えない。録音当時の写真が無いので、年を取ってからのもので代用せざるを得なかったのだろう。
この中に『Avalon Blues』という曲が入っている。内容は「ニューヨークは良い街だけど、俺の故郷はやっぱりアバロンさ」と続く自分の故郷を歌った詞だった。ミシシッピー州の田舎から、はるばる大都市ニューヨークに行き、即興で歌ったと思われる。そのあたりは、「ソングスター」とも呼ばれる所以で、休日にギターを抱えて町の人達を楽しませた芸人の真骨頂だ。ちなみに、おそらく当時はニューヨークまで汽車で何日もかけての長旅だっただろうし、座席も白人と有色人種で分離されていただろう。
この録音の後、1963年に再び見いだされれたとき、この曲で出てくる地名アバロンから探し出されたらしい。そこは、地図にも載っていないような田舎だったという。

キングレコードから出ていた2枚組LP『The immortal Mississippi John Hurt』。1964~1965年頃の録音25曲。元は、VanguardのLP、VSD-79220と79248だったのをカップリングして発売されたもの。

こちらもキングから出たCD『The best of Mississippi John Hurt plus』。1965/4/15、Oberlin Collegeでのライブ収録21曲に1曲おまけの全22曲。