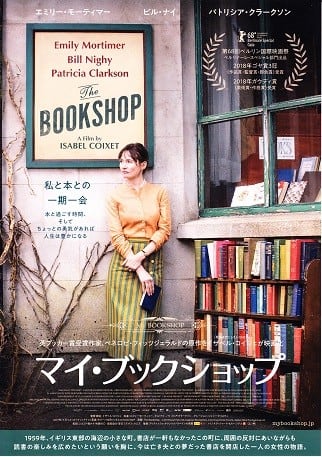ロバート・ピート・ウィリアムス(Robert Pete Williams)は、1914年3月14日にルイジアナ州ザチャリー(Zachary)で生まれ、1980年12月31日に同州ローズデイル(Rosedale)で亡くなっている。独自のスタイルでアコースティックギターを弾く、オンリーワン・ブルースマン。ルイジアナ州はフランス領だったこともあり、ザディコやケイジャンなど特有の音楽が存在する地域で、ここ出身のブルースマンは少数派とも言える。それだけに、この人の独自な音楽はもっと注目されても良い様に思うが、今では忘れられた存在なっているようだ。
その生涯は、波乱に満ちたものだったようだ。1956年に殺人罪でルイジアナ州の刑務所(Angola State Penitentiary)に収監される。42歳頃のことだろうか。当人は正当防衛を主張していたらしい。銃社会のアメリカでは、こういう事態は珍しくないらしい。たとえば、ペグ・レグ・ハウエルは、義弟に脚を撃ち抜かれている。喧嘩した相手が銃を手に持ち迫ってくる、そんなことは珍しくは無い、ということだ。さて、そのルイジアナ州の刑務所に1959年、ハリー・オスター(Harry Oster)という人がフィールドレコーディングにやってくる。オスターは、収容所に収監されている者の中で音楽を演奏出来るものを選び、地域の歴史的音楽を残そうとしたようだ。その中に、ロバート・ピート・ウィリアムスが入っており、後にLPレコード化に繋がることになる。1959年12月には、オスターが保証人になり仮釈放され、農場での作業などに従事し、1964年には完全に自由の身になったという。
もともとプロのミュージシャンでは無い為か、録音に関しては出来の良いものは少ない、という印象がある。本来ミュージシャンとしての才能も力も併せ持っている人なのだが、やはり白人を前にしての演奏には戸惑いと過度な緊張があったのだろう。下にある5枚のLPレコードの中でも、残念ながら、実力を発揮しているものは限られている。なので、過小評価されているようにも感じる。我が家には、ルイジアナのウィリアムスの家で撮影された映像などもあるが、むしろそれらの方が余計な力が抜けていて良い演奏に感じる。

ARHOOLIEの2011。これと下のLPが、1959~'60にかけてオスターがルイジアナ州の刑務所で録音した音源。これは1959年の分で、ウィリアムスの他に、ホッグマン・マキシー(Hogman Maxey)とギター・ウェルチ(Guitar Welch)という人のフィールドレコーディングも入っている。12弦ギターも使っているが、おそらくは録音者のオスターが持参したものと思われる。

同じくARHOOLIEの2015。1959~'60にかけての録音分で、ロバート・ピート・ウィリアムスだけでの演奏9曲を収録。個人的には、これが気に入っている。写真は、上のものと同じに見えるが、着ているのは囚人服らしい。

BLUES BEACONというドイツのレーベルのLP、631000。ジャケット裏には、1972年3月にドイツのスタジオで録音となっている。スライド奏法中心の演奏。

WolfというオーストリアのレーベルのLP、120.919。1974年マイアミ大学でのライブ盤。写真を良く見ると分かるように、アコースティック・ギターにデアルモンドらしきピック・アップを装着している。音はエレキギターに近くなっているが、あえて言うと、どっちつかず。ギターの音の増幅というのは簡単にはいかないもんだね。

サン・ハウスとのカップリングLPで、1966年のライブ録音。周囲がざわついていて落ち着かない雰囲気。緊張している為か、リズムに本来の深さが欠けているように聴こえる。ミュージシャンは、苦労が多いよなあ・・ほんとに。