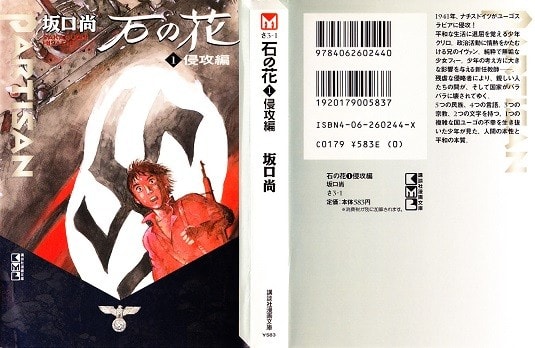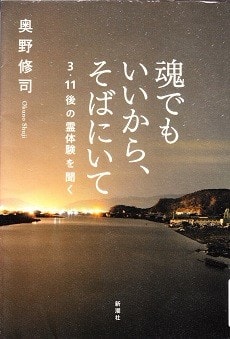かつて、地方出版が隆盛をみた時代があった。神田のすずらん通りには、1976年から2007年まで地方出版を専門に取り扱う「書肆アクセス」という書店もあり、全国の小さな出版社から出た本が所狭しと並べられていた。出版部数が少ないために1冊あたりの価格はどうしても高めだったが、各地の歴史や現在の実情を知る上で貴重な資料を提供していたものだった。その「書肆アクセス」も無くなって久しく、各地方出版社も数を減らしていった。
そんな中でも、千葉県流山市にある崙(ろん)書房出版は、県内の歴史に関する証言や小説を中心に出版を続ける貴重な存在となっていた。しかし、その崙書房出版も経営難のため七月三十一日に業務を終える、という。1970年に初代社長の小野倉男さんが創業したというから、半世紀近くがんばってきた、と云える。実際、その出版指向は、「売れる本」ではなく「良い本」を出す、という品質重視なものだった。正直、こんな本ばかりで商売が成り立っているのかな、と感じることも多かった。おそらく、「すぐれた本を市場に供給する」という信念で続けてきたに違いない。頭が下がる思いだ。ささやかだが、長年の労苦に対する称賛をここから送りたい。
というわけで、わたしの蔵書の中から崙書房によるものを2冊。

2015年刊『永遠の平和―千葉の「戦後70年」を歩く』。東京新聞の千葉版の記事を同千葉支局が編集したもの。文庫サイズで1500円は少し高いが、内容はそれ以上のものがある。

2016年刊『古文書で読む千葉市の今むかし』。幕末期を中心に、現在の千葉市周辺の江戸期の歴史を生で感じ取れる古文書の読み取りと解説。千葉市史編さん担当者による編集。地道な研究の成果といえる。
そんな中でも、千葉県流山市にある崙(ろん)書房出版は、県内の歴史に関する証言や小説を中心に出版を続ける貴重な存在となっていた。しかし、その崙書房出版も経営難のため七月三十一日に業務を終える、という。1970年に初代社長の小野倉男さんが創業したというから、半世紀近くがんばってきた、と云える。実際、その出版指向は、「売れる本」ではなく「良い本」を出す、という品質重視なものだった。正直、こんな本ばかりで商売が成り立っているのかな、と感じることも多かった。おそらく、「すぐれた本を市場に供給する」という信念で続けてきたに違いない。頭が下がる思いだ。ささやかだが、長年の労苦に対する称賛をここから送りたい。
というわけで、わたしの蔵書の中から崙書房によるものを2冊。

2015年刊『永遠の平和―千葉の「戦後70年」を歩く』。東京新聞の千葉版の記事を同千葉支局が編集したもの。文庫サイズで1500円は少し高いが、内容はそれ以上のものがある。

2016年刊『古文書で読む千葉市の今むかし』。幕末期を中心に、現在の千葉市周辺の江戸期の歴史を生で感じ取れる古文書の読み取りと解説。千葉市史編さん担当者による編集。地道な研究の成果といえる。