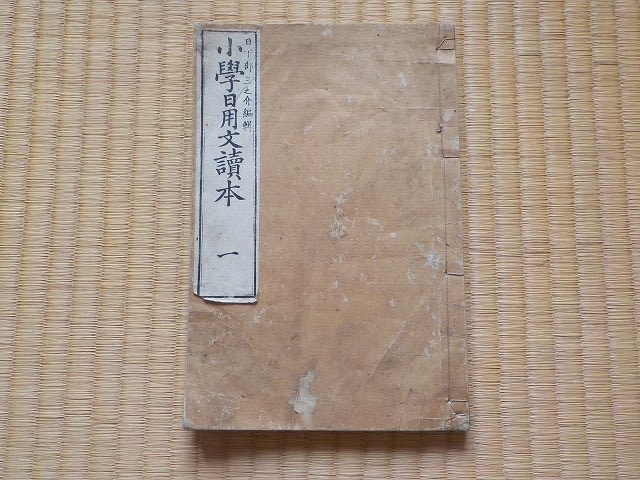またまた昔々の話です
明治十二年生まれの祖母の話です。
祖母の父が、つまり私の曽祖父が若い時の話だと言うから、江戸時代の末期の頃だろう。
道楽者と言うか、洒落者と言うかその時代には珍しく、釣りも嗜んだと言う。
百姓仕事も一段落した初夏。岩魚が多く棲むという評判を聞き、
馬籠と呼ぶ馬の餌の草を背負うための、大きな籠を背負い、弁当を持ってその川を目指した。
釣り始めたら、大きな岩魚がいくらでも釣れる。
持って行った餌も尽き、川虫を探して餌にし、釣り続けた。余り夢中で釣っていて、油断した。
気が付くと、大きな山の下にたどり着いた時は、
日が沈む頃になっていた。それから、帰ったのでは、危険な場所を手探りで帰るしかない。
豪胆な曽祖父は、そこで動かずに朝を待った。
日が昇ると同時に、やっとの思いで帰宅した。
背中の馬籠一杯に背負った岩魚は、腐り始め一匹も食べられなかったそうだ。
(続く)