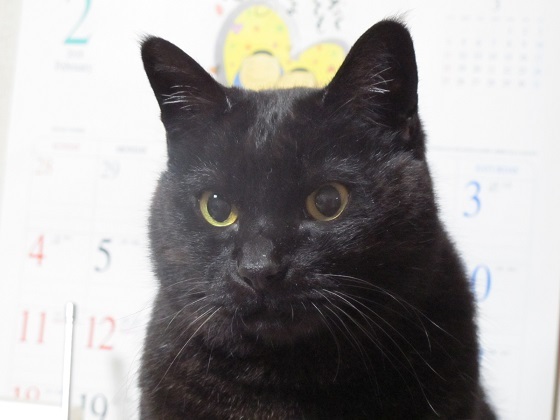北陸本線木ノ本駅から湖西線に乗り継いで、
山科で下車して、地下鉄に乗り換えて、
ひと駅の御陵(みささぎ)で下車。
ネット(駅の案内にも)では2番出口と書いてあったり、
4番出口と書いてあったりするけど、
4番出口の方が地上に上がった時、
左手に案内板があってわかりやすいかも。
案内板のすぐの右手に細い路地があり、
まっすぐ進むとT字路に突き当たる、
それを左に行くと、この辺りは閑静な住宅街。
山科疎水に出るので、橋を渡るとそこが目的のお寺。
橋を渡らず右に行くと、天智天皇陵がある。
本堂は一般開放されていないので、
寺務所に声をけて、入らせていただく。
山門右側の庭に、
半円形で歯車のような形をした石造が2つ並んでいる。
これは、本堂の天井の



龍図の続きとして作られた、石造の背びれと尻尾だそう。
上手く表現できないけど、
まだ、背びれや尻尾は地上に残り
胴体の一部は地中を潜って、
天井に顔と胴体が現れたといった、
天井画の龍と庭の石造りの龍尾は一体ということらしい。
相当大きな龍だね。(@_@;)
本堂は平成8年(1996年)に再建され、
その時に天井一面に日本画家の安藤康行氏により
昇り龍「大間天井龍図」が描かれたのだそう。
久し振りの龍を満喫。
帰りは、山科より、京都駅の方が
席を取りやすいだろうと、
地下鉄で烏丸御池で乗り換えて、京都駅へ。
一日で青春18きっぷの元を取りました。(*´з`)
※このお寺、御朱印はないそう。
青春18きっぷだから、
この際、
北陸本線で近江塩津まで行き、
湖西線に乗り換えて、
琵琶湖を1周した。
琵琶湖を間近に見ながら、走るのかなと思ったら、
たまに、遠くから見えるぐらいで、
少し期待外れ。
湖岸に沿って、走ったら素晴らしいだろうに、残念。
小谷城址の河毛駅。
魚籃観音や向源寺の十一面観音像の高月駅。
メタセコイヤの並木のマキノ駅。
ザゼンソウの近江今津駅。
菊御膳坂本の秋の味覚や、
日吉大社の節分祭の比叡山坂本駅等等。
車窓から何ヵ所か白い砂浜が続き
海水浴場があるようだ。
海水浴をしている様子も見えた。
調べてみたら、何ヵ所か海水浴場があるようだ。
塩水ではないので、ベタベタしなくていいそう。
電車に限らず、車で巡ったりと、
琵琶湖周辺は面白い。
長年の夢で、湖畔に住みたいと思っているのだけど、
高齢になって、持ち家を手放さないほうが良いと聞く。
そんなわけで、中々、思い切れない。
だれか、別荘を安く貸してくれないかなぁ。
ここは2回目。
手水舎の蛇口、竜の口といって、
龍の蛇口が一般的ですがここの蛇口は蛙。
いわれはこちら→木之本地蔵。
22日~25日には木之本地蔵大縁日、
25日には大花火大会があるようです。
静かな北国街道が賑わうんでしょうね。
木之本地蔵大縁日・木之本大花火大会 | 長浜・米原・奥びわ湖を楽しむ観光情報サイト (kitabiwako.jp)
事前に『すし慶げんさん』のことを調べて、
蔵ギャラリーがあることを知って、
食事後に、お店の人に尋ねて、
蔵ギャラリーを見学させてもらった。
この蔵、「役所」・「税務署」・「江北銀行」・「江北図書館」などを経て、
昭和51年から、すし慶げんさんに受け継がれたのだそう。
その名残が、上の写真の柱の〇に、
開店と同時に入ったので、まだ客は3組でしたが、
2組は蔵を見学せずに、帰られた。
何回目かの来店で、すでに、見ておられたのかもしれませんが・・・・・
ギャラリーには賤ケ岳合戦図があって、見応えあり。
七本槍の武将がどれかわからなかったのが、残念。
わかるように、ケースのガラスの上から、
それぞれ名前を付けて欲しいな。(*´ω`*)
江~姫たちの戦国 観光案内 近江牛すき焼き鯖寿司専門店 すし慶げんさん (sushikei.com)
『すし慶げんさん』に行かれたら、
是非、是非、蔵ギャラリーをご覧下さい。
青春18きっぷを使って、
鯖寿司を食べに、木之本へ。
北国街道沿いにある、
創業大正元年(1912年)、112年の歴史がある、
『すし慶げんさん』で、
鯖棒すし、近江牛のすき焼き、
ビワマスのお刺身、赤こんにゃく、モロコの佃煮、鴨ロース、
スジエビの煮豆、焼鯖そうめん。
住茂登 以来。
近江や琵琶湖の食材を堪能した。