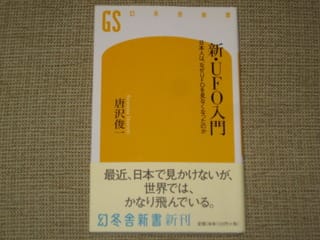泉昌之 1998年 扶桑社文庫版
きのうのつづき、泉昌之の短編集。
泉昌之は、読めばおもしろいんだが、単行本を買うまでいってなくて。
長いこと『ダンドリくん』くらいしか持ってなかったんだけど、かの有名な『夜行』が入ってるんで、この文庫を買ったんだったかな。持ってるのは2000年の第2刷。
『夜行』は、夜行列車のなかで、ハードボイルド風をきどる男が、駅弁を食べるっつーだけの話。
おかずとご飯のバランスとか、細っかいことにこだわりながら、ひとり真剣に弁当を食う。
何の役にも立たないことを大げさかつ大マジメに描かれてんのを、「そうだ」とか「ある、ある」とか喜べるひとには、面白く読めるんぢゃないかと思いますが。
コンテンツは、以下のとおり。
ちなみに「最後の晩餐」ってのが、本のタイトルにあるスキヤキに関する話。同じ鍋を囲んでる同士のなかで、いかに肉ばっか狙ってるかのように見せずに、それでいてちゃんと肉食うかって、またしょうもないこだわりを描いたもの。
「夜行」
「ロボット」
「花粉」
「スーパーウルトラジャイアントキングG」
「ARM JOE」
「最後の晩餐」
「POSE」
「THE APARTMENT HOUSE vol1 MIDNIGHT DANCING 4 1/2」
「THE APARTMENT HOUSE vol2 蚊が来る」
「THE APARTMENT HOUSE vol3 大形平次捕物帳」
「THE APARTMENT HOUSE vol4 ゴージャスの人」
「THE APARTMENT HOUSE vol5 だってアトミックLOVE」
「ウルトラLOVE」
「耳掘り」
「プロレスの鬼」
「パチンコ」
「ズミラマ館」
「すもも太郎」

きのうのつづき、泉昌之の短編集。
泉昌之は、読めばおもしろいんだが、単行本を買うまでいってなくて。
長いこと『ダンドリくん』くらいしか持ってなかったんだけど、かの有名な『夜行』が入ってるんで、この文庫を買ったんだったかな。持ってるのは2000年の第2刷。
『夜行』は、夜行列車のなかで、ハードボイルド風をきどる男が、駅弁を食べるっつーだけの話。
おかずとご飯のバランスとか、細っかいことにこだわりながら、ひとり真剣に弁当を食う。
何の役にも立たないことを大げさかつ大マジメに描かれてんのを、「そうだ」とか「ある、ある」とか喜べるひとには、面白く読めるんぢゃないかと思いますが。
コンテンツは、以下のとおり。
ちなみに「最後の晩餐」ってのが、本のタイトルにあるスキヤキに関する話。同じ鍋を囲んでる同士のなかで、いかに肉ばっか狙ってるかのように見せずに、それでいてちゃんと肉食うかって、またしょうもないこだわりを描いたもの。
「夜行」
「ロボット」
「花粉」
「スーパーウルトラジャイアントキングG」
「ARM JOE」
「最後の晩餐」
「POSE」
「THE APARTMENT HOUSE vol1 MIDNIGHT DANCING 4 1/2」
「THE APARTMENT HOUSE vol2 蚊が来る」
「THE APARTMENT HOUSE vol3 大形平次捕物帳」
「THE APARTMENT HOUSE vol4 ゴージャスの人」
「THE APARTMENT HOUSE vol5 だってアトミックLOVE」
「ウルトラLOVE」
「耳掘り」
「プロレスの鬼」
「パチンコ」
「ズミラマ館」
「すもも太郎」