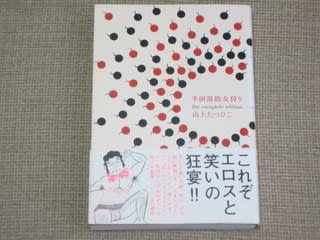乗馬に行く。
朝は曇ってるけど、30度まで上がる予報。
蒸し暑くなるのかな。前日まで北海道にいて、寒っとか言ってた私、なんか血圧でも上がりそうな気がする、こんな差があると。
きょうの馬は、メイショウダイクン、すごいひさしぶり、二回目。

私なんかが乗るような馬ぢゃないんぢゃなかったっけ。
もうひとりの人も「この馬たしか初めて」とか言ってる、だいじょうぶかな私ら。
んぢゃ、馬装できたら、行きますか。
前回乗ったときのノートを見といた、人が安定しないと動いてくれないよね、きっと。
ウォーミングアップ、なんか心許ないな。
脚への反応たしかめるだけぢゃなくて、馬の上で姿勢をいろいろ変えてみて、どこかに動かすスイッチないか探してみたりする。
ぢゃあ、4頭で部班。この馬では遠慮したいなと思ってんのに、先頭に立たされる。
軽速歩中心で蹄跡をクルクルと。フワンフワンして、前進してる感じしない。
「もっと動かして、もっと前出して」と何度も言われる。脚ドン、脚ドン。
「もっと動いて」「隅角で遅くならない」 んー、動かない、手綱はゆるゆると持ってんだけど、なんかジャマしてるかね?
「アタマの位置気にしない、動いてくればおさまるところに落ち着く」ということで、とにかく動かす。
ときどき巻乗り、「巻乗りに入るとき遅くならない!」ということで、動かせてない、あいかわらず。
キックぢゃなくて、はさんでしぼるようにギュッと脚を使えって。
まっすぐ前に出すようにして回転する。がさつな手の開き方をしてはいけない。
肘から手綱でつくる面ではさむボックスのなかに馬をおいて、そのなかで操縦するイメージ、そこからはみ出ると馬が動きづらそうで止まってしまう感じ。
前に出る勢いが弱いから隅角で内に入ってきてしまうんだろうか、とにかく前に進んで遠心力で外行っちゃうくらいの勢い欲しい。
輪乗り、何度も「両手はそろえてまっすぐ」と言われる。むやみに手綱を引っ張らない、前に出すこと優先、接線の方向に進むつもりで、内へ引っ張り込まないようにする。

んぢゃ、駈歩。あら、出ないよ。出たけど、パランパラン、動いてこない。
その馬駈歩出にくいんで、と言われて、列の最後尾にまわらされる。
あー、動かないなあ、人間が身体揺すっても逆効果なんで、ジッとして馬が動いてくるのを待つ。
輪乗りから蹄跡に出て、歩度を伸ばせと言われると、おっとガツンとギアが入った感じ。
遅れないように、ジャマしないように、馬を前において乗っていくイメージでいく。
手前を替えて、また輪乗りから駈歩。こんどはスムーズに出ていく感じある、よしよし、やる気に火が点いてくれたかな。
でも、どっちかっていうと右手前のほうが内に倒れるかな。そこでジタバタしても動き止めちゃうだけだから、前に出すこと優先、勢いで突破しちゃえ、ちっとくらいの傾きなんか。
あと、ときどき直線上でも、馬のカラダが斜めになるような気がする、斜め向いて前に進んでくのは、いつかコースアウトしちゃいそうで、ちょっとこわいものある。
はい、ぢゃあ常歩、手綱伸ばして。
手綱伸ばしたまま、常歩で輪乗り。手を使わずに、シートと脚で、馬を自分の思うように輪のうえ歩かせなさいと。
できないって、そんなこと。もぞもぞと馬の上で動く。
内に入ってきちゃいそうになったら、内の脚で圧す。おっと、その前に脚でまず前に出す、前進気勢ないから入ってくるんだから。
外行き過ぎたかと思ったら、外の脚を少しだけ後ろにひいて馬の後ろ半分が外へ流れてっちゃわないようにおさえる。
なんか、ときどきできる気がする。シートがまだ使えてないけどね。
手綱伸ばしたまま、常歩で三湾曲くりかえす。
ひとつめの弧を描いたあと、いちど真っ直ぐにして、左右の姿勢入れ替える。おっとっと、そうしようと思ってんのに、斜めにダラダラ進んでっちゃうよ。
くりかえすけど、馬は前の馬にくっついてってるだけだな、こりゃ。せめて蹄跡に接するところだけは内に入らないように押し込む。
かなり長いこと常歩でそういうの繰り返して、うまくいかないまま、練習は終了。
最後のほうは、脚つかうと速歩になりかけるくらい、馬のやる気は出てきたけれど、肝心のコントロールは納得いくようにはできなかった。

終わったら、手入れして、リンゴやる。
ふつうに食うんだけど、なんか無口ーな感じだよね。もっと表情にだして喜んでよ。
朝は曇ってるけど、30度まで上がる予報。
蒸し暑くなるのかな。前日まで北海道にいて、寒っとか言ってた私、なんか血圧でも上がりそうな気がする、こんな差があると。
きょうの馬は、メイショウダイクン、すごいひさしぶり、二回目。

私なんかが乗るような馬ぢゃないんぢゃなかったっけ。
もうひとりの人も「この馬たしか初めて」とか言ってる、だいじょうぶかな私ら。
んぢゃ、馬装できたら、行きますか。
前回乗ったときのノートを見といた、人が安定しないと動いてくれないよね、きっと。
ウォーミングアップ、なんか心許ないな。
脚への反応たしかめるだけぢゃなくて、馬の上で姿勢をいろいろ変えてみて、どこかに動かすスイッチないか探してみたりする。
ぢゃあ、4頭で部班。この馬では遠慮したいなと思ってんのに、先頭に立たされる。
軽速歩中心で蹄跡をクルクルと。フワンフワンして、前進してる感じしない。
「もっと動かして、もっと前出して」と何度も言われる。脚ドン、脚ドン。
「もっと動いて」「隅角で遅くならない」 んー、動かない、手綱はゆるゆると持ってんだけど、なんかジャマしてるかね?
「アタマの位置気にしない、動いてくればおさまるところに落ち着く」ということで、とにかく動かす。
ときどき巻乗り、「巻乗りに入るとき遅くならない!」ということで、動かせてない、あいかわらず。
キックぢゃなくて、はさんでしぼるようにギュッと脚を使えって。
まっすぐ前に出すようにして回転する。がさつな手の開き方をしてはいけない。
肘から手綱でつくる面ではさむボックスのなかに馬をおいて、そのなかで操縦するイメージ、そこからはみ出ると馬が動きづらそうで止まってしまう感じ。
前に出る勢いが弱いから隅角で内に入ってきてしまうんだろうか、とにかく前に進んで遠心力で外行っちゃうくらいの勢い欲しい。
輪乗り、何度も「両手はそろえてまっすぐ」と言われる。むやみに手綱を引っ張らない、前に出すこと優先、接線の方向に進むつもりで、内へ引っ張り込まないようにする。

んぢゃ、駈歩。あら、出ないよ。出たけど、パランパラン、動いてこない。
その馬駈歩出にくいんで、と言われて、列の最後尾にまわらされる。
あー、動かないなあ、人間が身体揺すっても逆効果なんで、ジッとして馬が動いてくるのを待つ。
輪乗りから蹄跡に出て、歩度を伸ばせと言われると、おっとガツンとギアが入った感じ。
遅れないように、ジャマしないように、馬を前において乗っていくイメージでいく。
手前を替えて、また輪乗りから駈歩。こんどはスムーズに出ていく感じある、よしよし、やる気に火が点いてくれたかな。
でも、どっちかっていうと右手前のほうが内に倒れるかな。そこでジタバタしても動き止めちゃうだけだから、前に出すこと優先、勢いで突破しちゃえ、ちっとくらいの傾きなんか。
あと、ときどき直線上でも、馬のカラダが斜めになるような気がする、斜め向いて前に進んでくのは、いつかコースアウトしちゃいそうで、ちょっとこわいものある。
はい、ぢゃあ常歩、手綱伸ばして。
手綱伸ばしたまま、常歩で輪乗り。手を使わずに、シートと脚で、馬を自分の思うように輪のうえ歩かせなさいと。
できないって、そんなこと。もぞもぞと馬の上で動く。
内に入ってきちゃいそうになったら、内の脚で圧す。おっと、その前に脚でまず前に出す、前進気勢ないから入ってくるんだから。
外行き過ぎたかと思ったら、外の脚を少しだけ後ろにひいて馬の後ろ半分が外へ流れてっちゃわないようにおさえる。
なんか、ときどきできる気がする。シートがまだ使えてないけどね。
手綱伸ばしたまま、常歩で三湾曲くりかえす。
ひとつめの弧を描いたあと、いちど真っ直ぐにして、左右の姿勢入れ替える。おっとっと、そうしようと思ってんのに、斜めにダラダラ進んでっちゃうよ。
くりかえすけど、馬は前の馬にくっついてってるだけだな、こりゃ。せめて蹄跡に接するところだけは内に入らないように押し込む。
かなり長いこと常歩でそういうの繰り返して、うまくいかないまま、練習は終了。
最後のほうは、脚つかうと速歩になりかけるくらい、馬のやる気は出てきたけれど、肝心のコントロールは納得いくようにはできなかった。

終わったら、手入れして、リンゴやる。
ふつうに食うんだけど、なんか無口ーな感じだよね。もっと表情にだして喜んでよ。