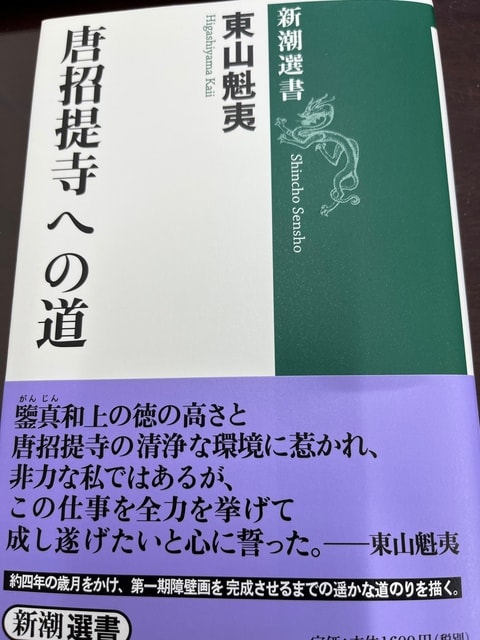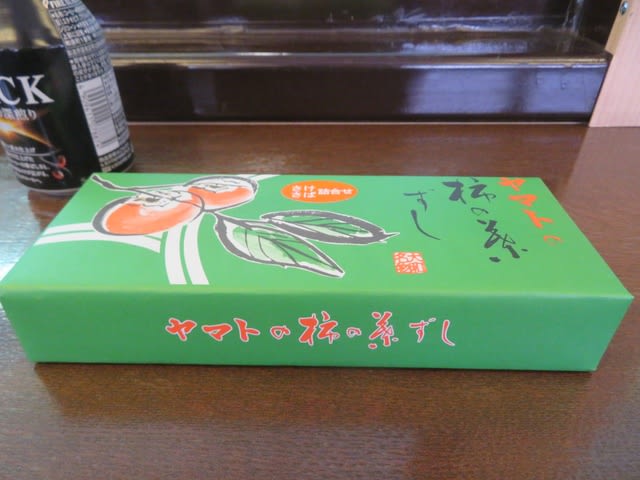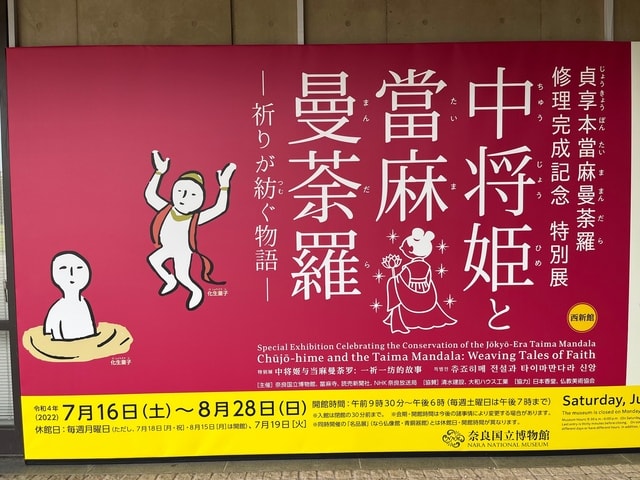今日は、温かい。
明日は、もっと温かくなるようだ。
花粉症の人はたいへん?
私は、花粉症デビューにならないよう祈るのみ。

今日は、昨年も行った法隆寺シンポジウム。
会場も昨年と同じ有楽町朝日ホール。
マリオンにある。

あまり、商売っ気はなく、まじめなシンポ。
会場はほぼ満席だったが、当選確率は、2倍だったという。
何と、勉強熱心な人が多いことか。

プログラムはこんな感じで、まず法隆寺管長が法隆寺の歴史について総括。
その後、3名が、そらぞれの分野について講演を行い、最後座談会という流れ。
リレー講演は、知っている内容や、文化財保護の歴史についての内容で、興味いまいち?
座談会で、焼損した金堂内陣の公開案についての、現状が披露され、興味深かった。
講演1は、東京文化財研究所保存科学研究センター長の建石さん。
数年前まで、奈良県庁に出向され、この金堂内陣公開プロジェクトに取り組まれてきた。
法隆寺は、日本の世界遺産第1号だが、当時は、世界遺産に対する認知度も低く、文化庁主導で、法隆寺は全く受け身だったという。
指定されたポイントは、①木造建築の傑作②仏教伝来直後の姿と将来への影響③中国文化が日本に変化を加えて受け入れられていった④仏教が流布される重要な段階等だったという。
確かに、最初法隆寺ができた時は、607年で、聖武天皇の時代よりも、150年近くも前だ。
興味深かったのは、昭和24年に金堂が焼損した時、上層は、戦争の被災をさけるため疎開していて、焼失から免れていたということ。
私は、建物は、全部再建と思っていたが、上層は、1400年前の物が引き続き残されていたのだ。
若草伽藍の話は知っていたが、今の法隆寺の伽藍と場所も違うし、方向もずれる。
様式も四天王寺様式で、より中国的。
聖徳太子一族が滅んでからの再建となるから、何かの意図があって、元の法隆寺とあえて変えて再建されたのか。
太子信仰は、飛鳥時代後半から既に始まり、南都七大寺時代に定着したが、江戸時代、国学、儒学が重用されるようになり、廃れたという。
廃仏毀釈もあり、文化財が粗末に扱われるようになったことを危惧し、湯島聖堂博覧会が開かれたのが1872年で、これが、トウハクの始まりになった。
その後、諸法律も少しづづ整備された。
まさに、法隆寺は、文化財保存科学の嚆矢と言える存在だ。
講演2は、奈良文化財研究所副所長兼文化財防災センター長の高妻(こうづま)さん。
文化財を守るためにどのような活動が行われているのかの話だった。
災害だと、地震、台風、火災になるが、その歴史を追うと、阪神淡路大震災以降、地震と台風の頻度が急増していることがわかる。
まさに平成になってからだ。
もちろん、他国では、戦争による被災があるが、日本は、幸い、戦後その事態に見舞われてはいない。
その対策として、文化財レスキュー隊(運べる物)、文化財ドクター派遣事業(直す物)があり、その集大成として、2020年10月1日に、文化財防災センターが設立されたのだそうだ。
ただ、環境は厳しさを増しており、その要因は、過疎・都市化・少子高齢化に伴う地域社会の脆弱化にある。
文化財を守る社会がなければ、保護もおぼつかない。
文化財は誰ものか、文化とは何かが問われている。
自分で守ろうとする意識が薄まっているのではないか。
氏は、社会のインフラの一つと説く。
講演3は、奈良文化財研究所長の本中(もとなか)さん。
まずは、世界遺産登録の要件とそれがどのように法隆寺に当てはまったかという話。
この話は、縄文遺跡の世界遺産登録の本を読んだ時、詳しく書いてあった。
難しい言葉で言うと顕著な普遍的価値(Outstanding Universal Value)の言明が認定には必要になる。
そのOUVは、総合的所見(評価基準、完全性・真実性、保護・管理の条件)にまとめられるが、法隆寺が指定された際、焼損部材の記載がなされなかったといい、これは、明確に世界遺産の一部に指定されているので、加えられるべきと説く。
そもそも世界遺産は、移動可能な物は対象外で、仏像などは、世界遺産に含まれていない。
また若草伽藍のような、地底に埋まっていたものについても含まれないという。
ただ、この定義は、この30年で大きく変わっているのは、みなが感じている通りだ。
法隆寺が指定された際、そもそも定期的に建て替えられたり、大規模修繕されている木造建築物が世界遺産対象になるのかという議論があったそうで(ベニス憲章違反?)、法隆寺が指定された後に、奈良会議が開かれ、明確に対象になると、再定義されたのだという。
そういった意味で、法隆寺が、世界遺産に指定された意義は、①文化遺産第一号、②修理に対する世界の理解(木の文化圏)、③文化財保存への意識変化という点が指摘できるという。
その後も、多様性とスタンダードとのバランス・調和が図られてきた。
座談会では、金堂内陣の公開に向けての話しが主だった。
昨年、1昨年と、クラウドファンディングによる限定公開がされたが、温度変化や、湿度変化、焼損文化財に与える影響調査が目的だったという。
これも初めて知ったのだが、焼損した柱は、内側が焦げているだけで、大部分は、無事なのだという。
壁画は、残念ながら、かなり傷んでしまったが。
だから、焦げた部分を削って、再建する方法も可能だが、文化財保護の意識を高めるためにも、現状での展示を目指しているという。
私のような素人だと、アクリル等の箱に覆って、外から見せればいいのではと思うが、その1400年前の木の香り、焦げた木の香りが残っており、是非、直に見れるように公開したい強い思いもあるとのこと。
ただ、そのために、カビが映えたり、形状が変わってしまっては、本末転倒なので、難しいところ。
近い将来、方向性が示されるということで、その内容が楽しみだ。
法隆寺についてのシンポジウムというよりは、文化財保護、世界遺産についての話しが多かったようにも思うが、興味深い内容だった。
本シンポジウムの内容は、3月下旬の朝日新聞に掲載されるそうなので、購読中の方はお楽しみに。
明日は、もっと温かくなるようだ。
花粉症の人はたいへん?
私は、花粉症デビューにならないよう祈るのみ。

今日は、昨年も行った法隆寺シンポジウム。
会場も昨年と同じ有楽町朝日ホール。
マリオンにある。

あまり、商売っ気はなく、まじめなシンポ。
会場はほぼ満席だったが、当選確率は、2倍だったという。
何と、勉強熱心な人が多いことか。

プログラムはこんな感じで、まず法隆寺管長が法隆寺の歴史について総括。
その後、3名が、そらぞれの分野について講演を行い、最後座談会という流れ。
リレー講演は、知っている内容や、文化財保護の歴史についての内容で、興味いまいち?
座談会で、焼損した金堂内陣の公開案についての、現状が披露され、興味深かった。
講演1は、東京文化財研究所保存科学研究センター長の建石さん。
数年前まで、奈良県庁に出向され、この金堂内陣公開プロジェクトに取り組まれてきた。
法隆寺は、日本の世界遺産第1号だが、当時は、世界遺産に対する認知度も低く、文化庁主導で、法隆寺は全く受け身だったという。
指定されたポイントは、①木造建築の傑作②仏教伝来直後の姿と将来への影響③中国文化が日本に変化を加えて受け入れられていった④仏教が流布される重要な段階等だったという。
確かに、最初法隆寺ができた時は、607年で、聖武天皇の時代よりも、150年近くも前だ。
興味深かったのは、昭和24年に金堂が焼損した時、上層は、戦争の被災をさけるため疎開していて、焼失から免れていたということ。
私は、建物は、全部再建と思っていたが、上層は、1400年前の物が引き続き残されていたのだ。
若草伽藍の話は知っていたが、今の法隆寺の伽藍と場所も違うし、方向もずれる。
様式も四天王寺様式で、より中国的。
聖徳太子一族が滅んでからの再建となるから、何かの意図があって、元の法隆寺とあえて変えて再建されたのか。
太子信仰は、飛鳥時代後半から既に始まり、南都七大寺時代に定着したが、江戸時代、国学、儒学が重用されるようになり、廃れたという。
廃仏毀釈もあり、文化財が粗末に扱われるようになったことを危惧し、湯島聖堂博覧会が開かれたのが1872年で、これが、トウハクの始まりになった。
その後、諸法律も少しづづ整備された。
まさに、法隆寺は、文化財保存科学の嚆矢と言える存在だ。
講演2は、奈良文化財研究所副所長兼文化財防災センター長の高妻(こうづま)さん。
文化財を守るためにどのような活動が行われているのかの話だった。
災害だと、地震、台風、火災になるが、その歴史を追うと、阪神淡路大震災以降、地震と台風の頻度が急増していることがわかる。
まさに平成になってからだ。
もちろん、他国では、戦争による被災があるが、日本は、幸い、戦後その事態に見舞われてはいない。
その対策として、文化財レスキュー隊(運べる物)、文化財ドクター派遣事業(直す物)があり、その集大成として、2020年10月1日に、文化財防災センターが設立されたのだそうだ。
ただ、環境は厳しさを増しており、その要因は、過疎・都市化・少子高齢化に伴う地域社会の脆弱化にある。
文化財を守る社会がなければ、保護もおぼつかない。
文化財は誰ものか、文化とは何かが問われている。
自分で守ろうとする意識が薄まっているのではないか。
氏は、社会のインフラの一つと説く。
講演3は、奈良文化財研究所長の本中(もとなか)さん。
まずは、世界遺産登録の要件とそれがどのように法隆寺に当てはまったかという話。
この話は、縄文遺跡の世界遺産登録の本を読んだ時、詳しく書いてあった。
難しい言葉で言うと顕著な普遍的価値(Outstanding Universal Value)の言明が認定には必要になる。
そのOUVは、総合的所見(評価基準、完全性・真実性、保護・管理の条件)にまとめられるが、法隆寺が指定された際、焼損部材の記載がなされなかったといい、これは、明確に世界遺産の一部に指定されているので、加えられるべきと説く。
そもそも世界遺産は、移動可能な物は対象外で、仏像などは、世界遺産に含まれていない。
また若草伽藍のような、地底に埋まっていたものについても含まれないという。
ただ、この定義は、この30年で大きく変わっているのは、みなが感じている通りだ。
法隆寺が指定された際、そもそも定期的に建て替えられたり、大規模修繕されている木造建築物が世界遺産対象になるのかという議論があったそうで(ベニス憲章違反?)、法隆寺が指定された後に、奈良会議が開かれ、明確に対象になると、再定義されたのだという。
そういった意味で、法隆寺が、世界遺産に指定された意義は、①文化遺産第一号、②修理に対する世界の理解(木の文化圏)、③文化財保存への意識変化という点が指摘できるという。
その後も、多様性とスタンダードとのバランス・調和が図られてきた。
座談会では、金堂内陣の公開に向けての話しが主だった。
昨年、1昨年と、クラウドファンディングによる限定公開がされたが、温度変化や、湿度変化、焼損文化財に与える影響調査が目的だったという。
これも初めて知ったのだが、焼損した柱は、内側が焦げているだけで、大部分は、無事なのだという。
壁画は、残念ながら、かなり傷んでしまったが。
だから、焦げた部分を削って、再建する方法も可能だが、文化財保護の意識を高めるためにも、現状での展示を目指しているという。
私のような素人だと、アクリル等の箱に覆って、外から見せればいいのではと思うが、その1400年前の木の香り、焦げた木の香りが残っており、是非、直に見れるように公開したい強い思いもあるとのこと。
ただ、そのために、カビが映えたり、形状が変わってしまっては、本末転倒なので、難しいところ。
近い将来、方向性が示されるということで、その内容が楽しみだ。
法隆寺についてのシンポジウムというよりは、文化財保護、世界遺産についての話しが多かったようにも思うが、興味深い内容だった。
本シンポジウムの内容は、3月下旬の朝日新聞に掲載されるそうなので、購読中の方はお楽しみに。