いやいや、梅雨とは言え、暑くなってきた。
読みかけていた松本清張古代史シリーズを読破したので、ちょっとご紹介。
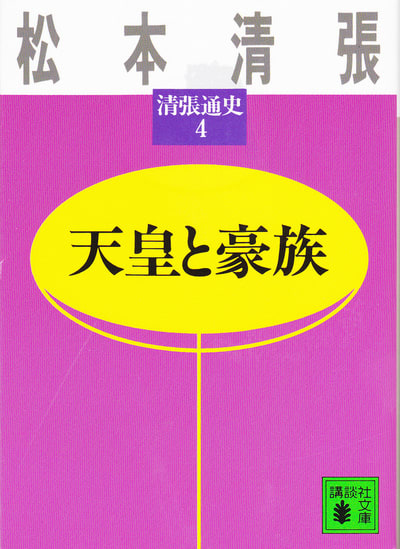
本書で、考古学から、また歴史に戻ってきた感じ。
日本書記が比較的史実に近くなってきた時代に入ったということだ。
ちなみに”大和”の名だが、”倭”が蔑称だったので、”大”を付けて”大倭”になり、倭と同音の和に変えて、”大和”の名称が使われるようになったのではないかという。だから、邪馬台国が東遷して、ヤマト(大和)になったという議論には、反対の立場である。
清張さんは、大和政権は、北九州にいた部族と、畿内にいた部族とは別に、後から、韓国から、直接畿内に入った扶余系の民族が立てたと推理する。
以前聖徳太子はいなかったという本の紹介をしたが、清張氏の議論もかなりそれに近い。存在そのものは否定しないが、聖徳太子の成果は、すべてが蘇我馬子の成果と見る。太子が、斑鳩に移ったのも隠遁と考える。その後の歴史の流れを見ても、十分ありうる考え方だ。その成果を聖徳太子のものとして、その子孫を滅ぼした蘇我氏征伐を正当化した。
藤原家についても、鎌足が祖ではなく不比等が開祖であり、鎌足以前の話は、権威づけのためのでっちあげで、鎌足は単なる有能な官僚に過ぎなかったのではと推理する。鎌足を祖として、天智と共に、大化の改新を成し遂げたストーリーを仕立てた。
当時の日本に大きな影響を与えていた朝鮮についても、詳しく説明している。高句麗は、隋を何度も跳ね返すいほど強大で、隋が新羅と連合後、敗北したという。そして、倭は、朝鮮における足場(帰る地?)を失い、逆に、中国、韓国連合国の侵略におびえる立場になった。
通史と言っても、清張氏の興味のある論点に話がぽんぽん飛ぶ通史で、なかなかまとまらないのだが、壬申の乱の原因についても触れている。単なる天智と天武の兄弟の不和ではなく、立派な権力争いで、三角関係とされた額田王の話も事実ではないと考える。
ただし、額田王の作家力は、たいしたもので、宮廷の職業的な歌人ではなかったかと考える。
それにしても、日本語ができた間もないころに、このようなすばらしい歌が多く作られたこと自体、感嘆すべきものがある。
とりとめのない話になったが、本書は、大和政権創成期について、さまざまな考察をしてくれる。
読みかけていた松本清張古代史シリーズを読破したので、ちょっとご紹介。
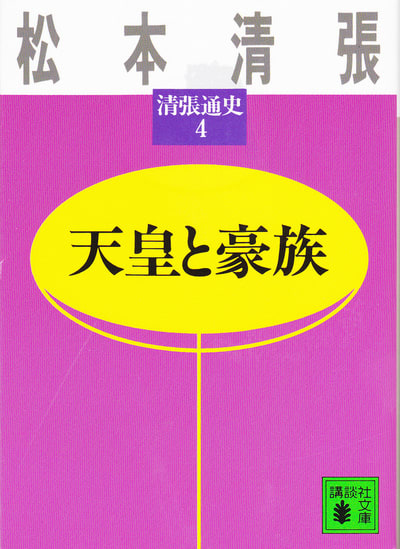
本書で、考古学から、また歴史に戻ってきた感じ。
日本書記が比較的史実に近くなってきた時代に入ったということだ。
ちなみに”大和”の名だが、”倭”が蔑称だったので、”大”を付けて”大倭”になり、倭と同音の和に変えて、”大和”の名称が使われるようになったのではないかという。だから、邪馬台国が東遷して、ヤマト(大和)になったという議論には、反対の立場である。
清張さんは、大和政権は、北九州にいた部族と、畿内にいた部族とは別に、後から、韓国から、直接畿内に入った扶余系の民族が立てたと推理する。
以前聖徳太子はいなかったという本の紹介をしたが、清張氏の議論もかなりそれに近い。存在そのものは否定しないが、聖徳太子の成果は、すべてが蘇我馬子の成果と見る。太子が、斑鳩に移ったのも隠遁と考える。その後の歴史の流れを見ても、十分ありうる考え方だ。その成果を聖徳太子のものとして、その子孫を滅ぼした蘇我氏征伐を正当化した。
藤原家についても、鎌足が祖ではなく不比等が開祖であり、鎌足以前の話は、権威づけのためのでっちあげで、鎌足は単なる有能な官僚に過ぎなかったのではと推理する。鎌足を祖として、天智と共に、大化の改新を成し遂げたストーリーを仕立てた。
当時の日本に大きな影響を与えていた朝鮮についても、詳しく説明している。高句麗は、隋を何度も跳ね返すいほど強大で、隋が新羅と連合後、敗北したという。そして、倭は、朝鮮における足場(帰る地?)を失い、逆に、中国、韓国連合国の侵略におびえる立場になった。
通史と言っても、清張氏の興味のある論点に話がぽんぽん飛ぶ通史で、なかなかまとまらないのだが、壬申の乱の原因についても触れている。単なる天智と天武の兄弟の不和ではなく、立派な権力争いで、三角関係とされた額田王の話も事実ではないと考える。
ただし、額田王の作家力は、たいしたもので、宮廷の職業的な歌人ではなかったかと考える。
それにしても、日本語ができた間もないころに、このようなすばらしい歌が多く作られたこと自体、感嘆すべきものがある。
とりとめのない話になったが、本書は、大和政権創成期について、さまざまな考察をしてくれる。















