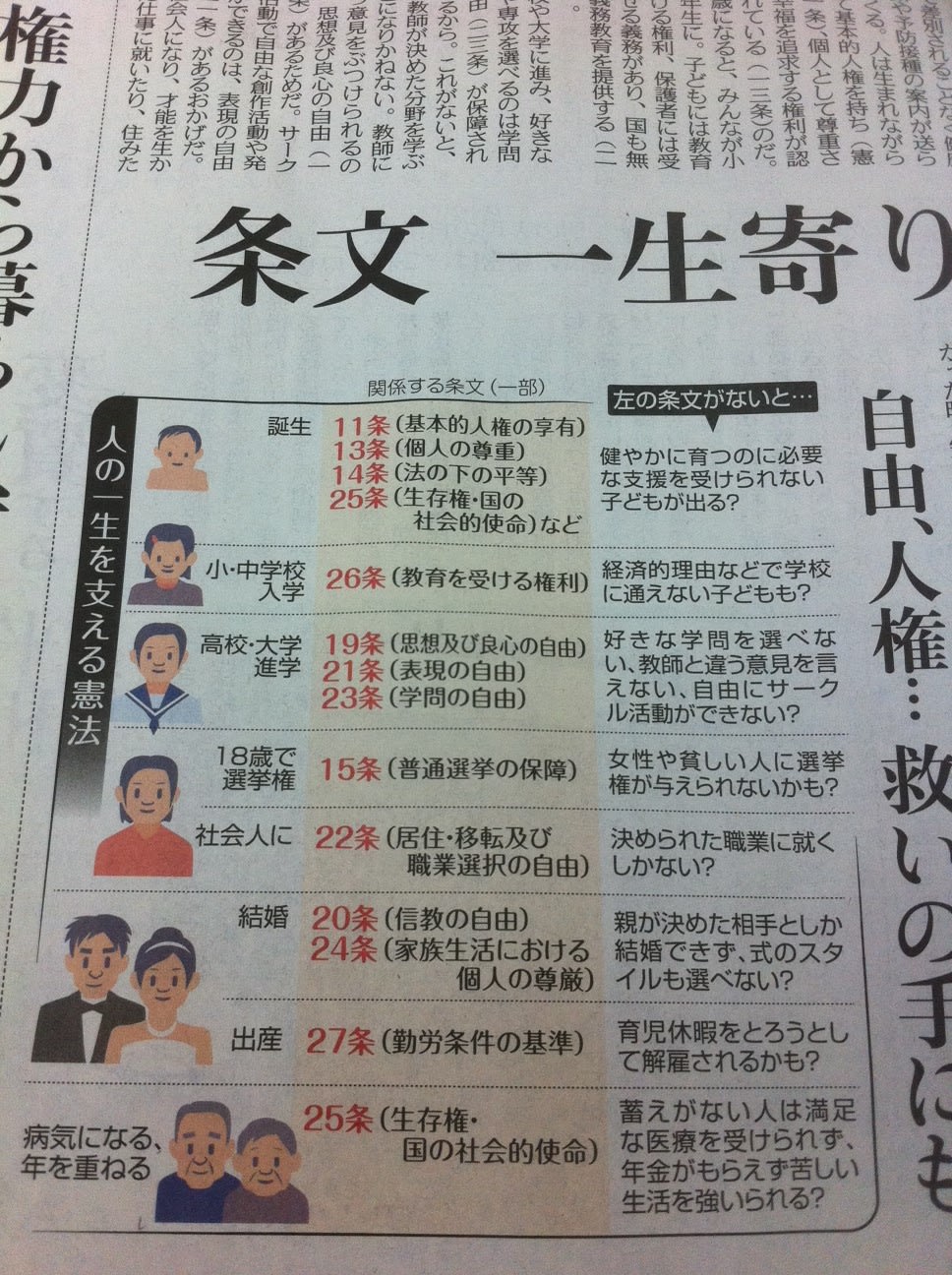現行憲法5条にあたると思われる自民党改憲草案の条文は、7条です。
*********************
日本国憲法
第五条 皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
参照:
1)前条第一項
⇒第四条一項 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
*実質的に準用していると解される条文で、準用の明記がない条文
2)三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
3)四条二項 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
自民党改憲案
(摂政)
第七条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名で、その国事に関する行為を行う。
2 第五条及び前条第四項の規定は、摂政について準用する。
参照:
1)第五条
⇒第五条 天皇は、この憲法に定める国事に関する行為を行い、国政に関する権能を有しない。
2)前条第四項
⇒第六条四項
天皇の国事に関する全ての行為には、内閣の進言を必要とし、内閣がその責任を負う。ただし、衆議院の解散については、内閣総理大臣の進言による。
*準用規定をすべて明記するのであれば、明記すべきと私は考える条文
3)六条三項 天皇は、法律の定めるところにより、前二項の行為を委任することができる。
*********************
憲法5条が、自民党改憲案でどのように変えられるのか。
自民党改憲案では、3条の日の丸、君が代規定と4条の元号の規定の挿入に伴い、条ずれを起こし、なおかつ、この摂政に関する規定は、現行5条から7条へとうしろの方に行きました。
また、準用する規定は、現行5条では、4条のみのところ、自民党改憲案では、現行憲法4条にあたる5条と、現行憲法3条にあたる6条4項(条文であったものが項のひとつに格下げされた大事な条文)が準用されています。
現行憲法5条は、天皇が自ら国事行為を行い得ないような状態のときに、法定代行機関として摂政を置くことを規定しています。
どのような場合に置くかは、皇室典範16条に規定されています。
******皇室典範16条******
第十六条 天皇が成年に達しないときは、摂政を置く。
○2 天皇が、精神若しくは身体の重患又は重大な事故により、国事に関する行為をみずからすることができないときは、皇室会議の議により、摂政を置く。
******************
摂政の順位は、皇室典範17条に規定されています。
******皇室典範17条******
第十七条 摂政は、左の順序により、成年に達した皇族が、これに就任する。
一 皇太子又は皇太孫
二 親王及び王
三 皇后
四 皇太后
五 太皇太后
六 内親王及び女王
○2 前項第二号の場合においては、皇位継承の順序に従い、同項第六号の場合においては、皇位継承の順序に準ずる。
******************
現行憲法5条は、4条1項のみを準用していますが、4条2項及び3条も実質的に準用されていると解されます。
そのことを自民党改憲草案では、明文で規定したため、準用条文が多くなっているのだと思います。
しかし、だとするなら、現行憲法4条2項にあたる自民党改憲草案の6条3項も、準用することを明文規定すべきであろうと思います。
現行憲法で、書かれていないけど、実質的に準用してきた内容を、明文規定におこうとした努力は認めますが、不十分です。実質的なものも明文におくなら、すべて明文におくべきです。
ただ、6条3項が現行憲法と大きく内容を異なるものにされているため、あえて準用から外したのかもしれません。
明日とりあげる現行憲法6条に関わりますが、
現行憲法:四条二項 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
自民党改憲草案:六条三項 天皇は、法律の定めるところにより、前二項の行為を委任することができる。
自民党改憲草案では、委任できる国事行為が狭められています。
なお、摂政を置くまでに至らない場合(例えば海外旅行や長期にわたる病気の場合)は、「国事行為の臨時代行に関する法律」により、臨時の代行が国事行為を行います(憲法4条2項⇒昨日8/4記載。)
(参考文献:『判例憲法 1』第一法規)
*****皇室典範 第三章摂政 第三章の全文抜粋**************
第三章 摂政
第十六条 天皇が成年に達しないときは、摂政を置く。
○2 天皇が、精神若しくは身体の重患又は重大な事故により、国事に関する行為をみずからすることができないときは、皇室会議の議により、摂政を置く。
第十七条 摂政は、左の順序により、成年に達した皇族が、これに就任する。
一 皇太子又は皇太孫
二 親王及び王
三 皇后
四 皇太后
五 太皇太后
六 内親王及び女王
○2 前項第二号の場合においては、皇位継承の順序に従い、同項第六号の場合においては、皇位継承の順序に準ずる。
第十八条 摂政又は摂政となる順位にあたる者に、精神若しくは身体の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、摂政又は摂政となる順序を変えることができる。
第十九条 摂政となる順位にあたる者が、成年に達しないため、又は前条の故障があるために、他の皇族が、摂政となつたときは、先順位にあたつていた皇族が、成年に達し、又は故障がなくなつたときでも、皇太子又は皇太孫に対する場合を除いては、摂政の任を譲ることがない。
第二十条 第十六条第二項の故障がなくなつたときは、皇室会議の議により、摂政を廃する。
第二十一条 摂政は、その在任中、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。
*************************************