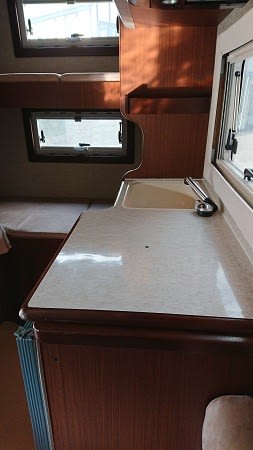天塩町二日目の今日も朝から研修講師。
今日は将来の幹部候補となる中堅職員への研修です。
昨日も今日も、講義の中に班編成のワークショップを取り入れました。
昨日の管理職の皆さんへのテーマは「上司や同僚、町民から信頼されるために必要なことはなにか」というもので、信頼を得るための振る舞いについて問うものでした。
そして今日の中堅職員へのテーマは「この地域の魅力を【見える化】して売り出し、あわよくばこの土地に人が来てくれるようにするためにはどのようなことをすべきか」というもので、地域の魅力や宝をどのように理解しているかを聞き出そうというものにしました。
ワークショップのやり方として、他人の意見を批判せずまずは思ったとおりに数を書き出す、ということが大事なのですが、次から次にメモを書き出す人もいれば慎重になりすぎて数が書けない人もいて、ばらつきが出ました。
外部の私は、天塩町の魅力としてまずは天塩川が思い浮かびます。
そこでのカヌーやカヤック、釣りなどは日本でも指折りのポテンシャルを持っているはずです。
また周辺も含めればサロベツ原野や酪農地帯の風景、海と利尻富士と夕焼けなどは魅力的に映ります。
ところが実際にメンバーからの発表を見ていると、上記のものがあまり出てきませんでした。
20人くらいいて「カヌー」と書いたのは一人だけ。
釣りも、鮭釣りとイトウに言及した人がわずかにいましたが、とてもすごいポテンシャルとは思っていない様子。
恐らくは地域の中にいて見慣れてしまって価値のすごさに気が付かないのか、はたまた観光のためということは遊びやアクティビティに関するものになるところが、あまり地元を生かして遊んだりもしていないのかな、という印象でした。
「近き者悦べば遠き者来る(論語)」と言って、自分たちがまず地元を面白がることが大切なんですよと述べた私の言葉はどのように聞こえたでしょうか。
自分たちが面白いと思わないような者では他所に宣伝をしたところで、その言葉に腹に力が入っていないことくらいすぐみ見透かされてしまうでしょう。
受講者の皆さんの行動変容に期待したいところです。
◆
講義の最後に会場の一人から質問がありました。
「講義の中で『書を読みなさい』というお話がありましたが、何か一冊推薦される本があるとしたら何ですか」というもので、私からの答えは「それならば二宮尊徳の本を読むとよいでしょう」でした。
二宮尊徳さんに関しては、自分自身というよりも彼にごく近かった弟子たちが日ごろの言行録を著した本が有名で、「報徳記」「二宮翁夜話」「二宮先生語録」などは実に良い本です。

何が良いかというと、二宮尊徳はその生涯の中で江戸時代末期に北関東の疲弊した村々を訪ねて、村民の心の荒蕪を耕して復活させたことで知られている農村経営アドバイザーでした。
彼の考え方はその後の経済人の心に大きな影響を与え、渋沢栄一が著した「論語と算盤」などはまさに尊徳の言う「経済と道徳は両輪」に沿ったものに違いありません。
また彼の村々を救ったやり方、考え方がまさにこれらの書物の中に刻み込まれていて、それを我が物として実践すれば救えない町はない、と思うからです。
天塩町の心ある方たちにこの書物が広がって、良い街づくりに繋がることを期待したいものです。
さて何人が読むでしょう。まさにその実践こそが問題なのですが。