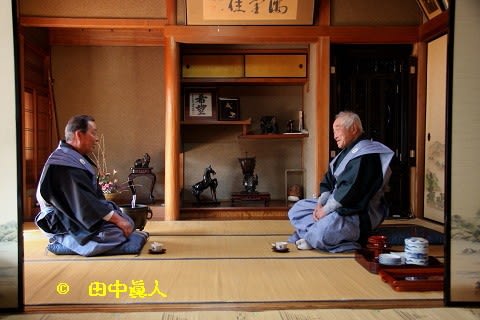本日も、おふくろの歯を治療する大阪・中央区伏見町にある林歯医者に通院する。
受付してから呼ばれるまでは多少の時間がかかる。
その間の私といえば伏見町界隈の散策。
歩いてではなく車異動の散策の目的は付近の格安駐車場を探すことだ。
前週に停めた駐車場は30分間で300円。
それ以上になる料金体系にある駐車場はごまんとある。
15分で400円はざらにある高額料金地帯である。
見つけたいのは以下の料金で提供する駐車場を探すことだ。
歯医者から真っすぐ東へ抜ける一方通行道がある。
あっと驚く料金に飛びついた。
その料金は15分でたったの百円。
ありえない価格体系に思わず飛びついたが、利用不可だった。
不可の理由は車高が高いということだ。
我が家の車は軽バンタイプのスズキエブリイジョインターボ。
ハイルーフ仕様の車高は1.895cm。
2mにも満たない車が入庫できない駐車場になんとかならんかと云いたいが、そこは無理・・・。
介護認定2級のおふくろは通院する歯医者への送迎は、昨年から数えて通算の4回。
その度に歯医者があるビル前に停めておふくろが足をのせる台を用意する。
それがなければ乗り降りができない。
杖搗き必須の歩行困難者にかーさんもつく。
車から降りたら、すばやくその場を離れる。
ぐるぐる回遊して受付を済ませたかーさんを乗せて、再び伏見町の他、周辺地域を回遊する。
治療が終わるまでこうしているわけにはいかないから、頃合いを見計らって、というよりも30分が300円の駐車場が「空」になるチャンスを狙っているのだ。
「満」の表示が出ておれば停められない。
空きが出るまで回遊してチャンスを待つ。
ぐるぐる廻っていたらおふくろから電話がかかった。
この日の治療は意外と早く終わった。
前回は1時間以上も費やしたが、この日は驚くほどの早さで終わった。
終わればかーさんをビル前に連れていく。
一旦は車を降りて5階に歯医者で出向く。
治療費を支払って降りてくるまでは多少の時間がかかるから、再び回遊する。
停める所がないものだから、毎回こうしている。
そのうち電話がかかっておふくろとともにビル前に出たと連絡が入る。
そこで再びビル前に出向いて介護認定2級のおふくろを乗せる。
このときも必要な台を足元に置く。
どこへ行くにしても、いつもこの繰り返し。
もう慣れたものだが、駐車場の男性、それも外国の人がそこに置くな、と尤もなことを通告する。
30秒もかからないおふくろの乗車を否定するような言い方に、すんまへんなといっても、早くここからどけ、である。
歯医者があるここのビルの駐車場の誘導員はもう一人いる。
その人は優しい眼差しでやさしく声をかける。
介護していると状況がわかるその人は乗り降りする状態を優しく見守る。
ところが外国人は云わんばかりの態度で攻めるから、思わず怒鳴ったら・・・といった。
それ以上突っ込みしようのない・・・であった。
そんなあれこれがあってもこの日も昼食を摂る。
前回、前々回ともくるくる寿司。
好評であるが、味替えもしたい。
そう思って車を走らせた国道は新なにわ筋。
真っすぐ南下すれがあきんどスシローがあるはず。
新なにわ筋を走るのは45年ぶり。
ずいぶんとかわった街の景観を観ながら南下する。
そのころに降り出した雨が土砂降りの様相。
できればあきんどスシローの駐車場は雨のかからない駐車場であってほしい。
車の乗り降りが多少困難なおふくろに傘が不要な駐車場であってほしい。
その願いが叶ったあきんどスシロー北加賀屋店。
ありがとうと云いたい。
入店した時間は午後12時40分。
くら寿司やはま寿司であれば席発券機はあるが、
あきんどスシローにはない。
北加賀屋店にないだけのかもしれないが、あるのは登録会員向けの事前予約した人のための機械。
当日受付機でなく予約専用機である。
店員さんはその機械の前に立って受けていたのでそれはないと云えば、待ち行列もなかったこともあって、3人と云えば、すぐさまテーブル席に案内してくれた。
階段を登ってきたおふくろは時間がかかる。
もうしわけないと云えば、いえいえ、待っておりますのでと笑顔で対応する店員さんだった。
席についた3人は早速の注文。
あきんどスシローに来た目的はくら寿司との味の比較である。
特に比べてみたい商品は130円のかけうどんである。
おふくろはうどんがなければ、という困った人。
寿司も造りもすべてはまぐろで食べ通す困った人である。
くら寿司のかけうどんはとても美味しいと云っていたから、食べ比べ。
しかも両店舗ともかけうどん1杯が税抜き130円である。
早速タッチパネルを操作してかけうどん2杯を注文する。
その間に流れてくる回転レーンにまぐろにぎりが・・。
あれ食べたいと指示がでればとっさに取る。
まぐろの色は艶々。
赤身のまぐろは1皿に一つ。
あとでわかったことだが、そのまぐろにぎりは脂がのっていてとても美味しかったという中とろまぐろのにぎりは一皿100円だった。
その間のかーさんといえば次から次に流れる回転レーンの寿司皿を取っては食べて、取っては食べていた。
どれもこれも美味しいというあきんどスシローの寿司ネタはくら寿司のネタより厚みに旨みがあるという。
それだから食は増すばかりというわけだ。
私といえばかけうどんを注文すると同時にタッチしたまぐろユッケの軍艦巻きである。

にぬきでなく半茹でと思われる黄身に白身をのせたまぐろユッケ。
まぐろの色が鮮やかな上にちょっと垂らしたと思えるタレが美味い軍艦巻き。
くら寿司よりかは多少の柔らかさがある海苔で巻いている。
こいつぁ美味いね。
連続、立て続けて口に入れてしまうほどに美味い。
海苔の固さは鉄火巻きの海苔もそうだというおふくろ。
そう、くら寿司の海苔は要介護老人には不向きな硬さがある。
さて、かけうどんである。

一口食べて、こりゃなと思った味。
出汁である。
旨みがないというのか、なんとなくたよんない味。
うどん麺はしこしこの固めの麺。
歯ごたえというか噛み応えのある麺に絡まないのである。
決して不味くはないのだが、箸の進み具合が遅い。
おふくろも同じ感想を伝えた。
違いは出汁だけでなく麺も違うな。
くら寿司の方が喉の通りがいいつるつる麺であるが、見た目も違うのが一つある。
それは薄いが2枚のカマボコである。
味的には補完していないからやはり見た目。
くら寿司では2杯も食べたおふくろは1杯でいいと云った。
私が次に選んだにぎりは奇をてらったつぶ貝・あか貝。
100円で2種類の貝の味を味わえる。

白と赤の貝はどちらも知っているし、食べたことのある貝であるが、うーん、美味すぎる。
特につぶ貝の食感が優れもの。
赤貝は独特の味がするのだが、これは押し殺してすっきり味。
噛み応えがたまらん一品、いや二品に艶がある。
次の注文はまた戻って軍艦巻き。

まぐろにとろろ芋を盛ったまぐろの山かけ軍艦巻き。
これが美味いんだな。
とろろよりも美味かったのはまぐろ。
味覚、食感からびんちょうまぐろのように感じた。
久しぶりに腰を据えて食べるあきんどスシロー。
軍艦巻きもそうだが、寿司ネタが大きくて旨さがある。
かーさんも同意見を申した。
寿司皿はたったの3枚しか注文していない。
もっと食べたいとついついタッチパネルを押して好みの寿司を探すのだが、しんどい。
というのもタッチパネルはスマホとかタブレットのような感触でスイッチは入らない。
とにかく力を込めないとスイッチが入らないのだ。
無理にでも押すのだが、云うことをきいてくれないタッチパネル。
いいかげん指が疲れてくる。
あきんどスシローさんょ、私だけがそう感じているのだろうか。
一度検査をしてほしいと思ったぐらいだ。
そのタチパネルを何度も押してぐぐったら「本日の海鮮軍艦」というのが現れた。
“本日“の冠があるということは”本日“限り。
まぐろかカツオかそれとも・・・。
どんな海鮮を盛ってくれるのか期待を膨らませる軍艦巻き。
”本日“限りの味を味わいたくタッチパネルを押した。

登場した本日の海鮮軍艦巻きはハマチの漬けのようだ。
まぐろユッケとかまぐろの山かけとの違いは大葉があるということだ。

軍艦巻きに大葉を挟んでいるのはあったっけ。
確かないよなぁ。
大葉は嫌いではない。
むしろ好みの部類。
造りに大葉が盛ってあれば、一番最初にいただく海鮮魚に大葉を包んで山葵醤油に浸けて食べる。
これが美味いんだな。
大葉を天ぷらに揚げたらパリパリサクサク感がたまらない。
細かく刻んだらたらこスパゲッティにパラパラ落として食べたら一層深みのある味になる。
大葉は刺身のツマだけでなくなんにでもツマになる。
思った通りの味になった本日の海鮮軍艦巻きが美味い。
ここで気がついたが、くら寿司も、本日のあきんどスシローも山葵をたっぷり入れて食べるのが特に美味しい。
なければふぬけのような味覚。
山葵を投入することで味に濃さが増しますである。
もうここらで納めどきのお腹。
テーブルに置いてあったペーパー形式のメニュー一覧があった。
そこにあった一枚の写真。
商品はスモークサーモンバジル軍艦巻き。
映像はスモークのように見えない。
ハジル色に染まっているから正体がわかり難い。
ぱっと見は細かい貝柱か小海老。
鮭はどこにあるの?と思ったくらいであるが、思わず注文を押した。
流れる回転レーンにもあったが、なんとなくその色具合が心をゆするので押した。
テーブルに置いた軍艦巻きはイメージと同じようにフレッシュさのないスモークサーモン。
唐揚げした小海老天のように見えるのがおかしい。

甘タレ醤油を落として山葵をたっぷり載せた軍艦巻きは思いもよらないとんでもない美味しさをもっていた。
これはいける。
今まで味わったことのないバジル味が軍艦巻きに溶け込んだ。
味を覚えたスモークサーモンバジル軍艦巻き。
私の中ではインパクト一番である。
ここでお腹を〆た。

それでも回転レーンは廻っている。
次回の来年に狙ってみたいにぎりが出現した。
「熟成牛 ツッケ風赤身肉」。
これもまた大葉を皿にしている一品は一週間、待てである。
会計ボタンを押して店員さんが枚数を数える。
お間違えないでしょうか、にハイである。
会計板をレジに盛っていってクレジットカードで支払う。
一人当たりの喰い料は842円。
これまでくら寿司で食べたときよりも支払い金額が増えた。
美味しさからそうなったんであろう。
店内でゆっくり寛いでいた時間帯も雨は土砂降り。
1時間弱も滞在したら少しはマシになるかと思われたが、降りやまない。
エレベータのないお店は帰りも階段。
一歩、一歩をてすりに縋って階段を下りるおふくろ。

一番下まで下りたら歩道側に一旦は出て駐車場に廻るということであるが、傘が必要な屋根のない処が歩道である。
それを避けるには高さのあるコンクリート造りの垣を跨がなくてはならない。
実際、100%のお客さんはそうしていたが、跨ぎ方が拙ければ足を引っかけてつんのめる可能性がある。
これまた事故があったのか、なかったのか、存じていないが、そこは店舗の敷地内。
どうか、足をあまり上げられない要介護の人たちのためにも、何らかの対応をお願いしたい。
また、車椅子で移動する身体障がい者の方たちにも美味しい
あきんどスシローのお寿司を食べられますよう、改善申し上げる次第である。
ちなみにこの日現在のデータであるが、既にエレベーターを設置済みの店舗がある。
大阪府の店舗は泉付中店、堺百舌鳥店、藤井寺店、守口大日店の4店舗。
府内46店舗のうち、たったの4店舗である。
尤も地上1階店舗なら不要であるが・・・。
(H30. 5.31 SB932SH撮影)