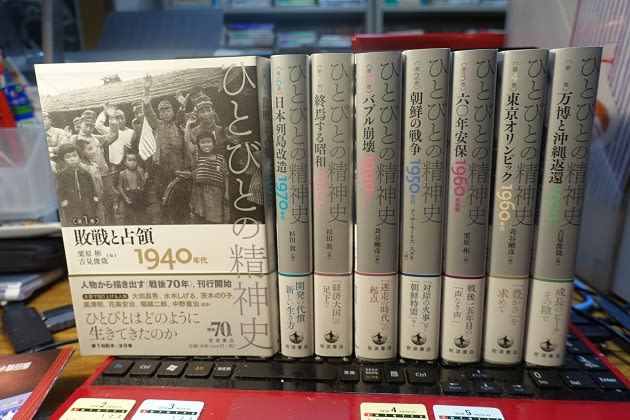8時、起床。
書斎に行くとお泊りをしたナツがまだ私の椅子の上にいる・・・と思ったら、そうではなくて、妻がゴミ出しをするときに一度出て、そしてすぐにまた入ってきたのだという。外はかなり寒いのだろう。ナツの行動でその日の寒さの程度がわかる。

朝食はトースト、サラダ(サーモン)、牛乳、紅茶の朝食。

昼から大学へ。
馬場下の交差点から本部キャンパに向かう道は「早大南門通り」という名前が付いている。

試験を終えて本部キャンパスから地下鉄の駅に向かう受験生たちが、「南門(難問)だったな」とつぶやきながら歩く道である。別名、「早大狭門通り」とも呼ばれている(嘘です)。

その早大南門通りにある「たかはし」。

ぶり照焼き定食。珍しく魚料理を注文したのは、先日、ニューヨークからやってきたアマネさんとジュリちゃんが目の前で魚料理(塩さば定食と銀むつ煮付け定食)を食べているのを見て、美味しそうだなと思ったからである。

ジュリちゃんが食べていたのはぶりの切り身の照り焼きだったが、今日はぶりのカマの照り焼きである。
同僚の上野先生と相席になり、あれこれおしゃべりをしながら食事をした。二人はほぼ同い年で、昔、私が二文の学生担当教務をしていたとき、上野先生は一文の学生担当教務をされていた。いわば戦友である。

馬場下の交差点の鯛焼き屋でお八つの鯛焼きを一尾買って、教員ロビー別室で食べる。

研究室で食べなかったのは、ここでしばらく雑用を片付ける必要があったからである。

教員ロビー備え付けのパソコン。ワードがまだ2010である。最新版は2016だが、せめて2013にバージョンアップしていてほしいものである。学生が2013で書いたレポートを2010で開くとレイアウトが微妙に違ってくるのである(デフォルトでは一頁の行数は36行だが、それを自分で40行まで増やすことができる。しかし、旧いバージョンで新しいバージョンの文書を開くと、その設定が反映されないのである)。

卒業生のアヤノさん(論系ゼミ7期生)からラインに写真が送られてきた。「先生こんにちは。静岡では、河津桜が咲き始めました!」のメッセージと一緒に。
ピンクの花が河津桜の特徴である。

本場河津町河津川沿いの桜並木である。

キャンパスのスロープ上の桜が咲くのはあとひと月ほど先だろう。卒業式(3月26日)とのタイミングは今年はどうだろう。

雑用を片付けてから、新宿の「シアター・ミラクル」に卒業生のサワチさん(アヤノさんと同じ論系ゼミ7期生)が出演する芝居を観に行く。

「シアター・ミラクル」を活動の拠点にしている4人の演出家が8作品を作り、A・B・C・Exと各チームに分かれて上演する演劇祭。
サワチさんが出演するのはfeblaboの「お父さんをください」。
「妻に先立たれ、男で一つで娘を育ててきた男は、いつしか自分がゲイだったことに気づき、年下の彼氏と恋に落ちていく。そしてある日。彼氏は男と娘のもとを訪ね、願い出る。「お嬢さん、お父さんをください」(シアター・ミラクル祭'18のHPの紹介文)

GLBTをテーマにしたコメディで、サワチさんは娘役を演じるのだろう、その程度の予想で芝居を見始めたが、実施、その通りなのだがが、話の展開は予想をはるかに超えたものだった。
娘が父親の結婚に反対するのは予想撮りだが、その理由は、たんに同性愛についての反感からではなく、自分が父親と結婚したいからであった。同性愛についての社会的受容は高まっているが、近親相姦はあいからずタブーであり、それは今後も変わらないだろう。父親は(そして年下の彼子も)娘の思わぬカミングアウトに狼狽するが、話はさらに時空を越えて展開していく。年下の彼氏というのは、実は、未来からタイムトラベルしてきた父親と娘の間に生まれた子供で(つまり近親相姦は成立してしまうのだ)、双子の兄が人類を滅ぼす邪悪な存在になることを防ぐべく、両親(父親と娘)を結婚させないために父親に接近したというのである。ただ、それは最初は任務のためであったが、やがて父親のことを本当に愛するようになってしまったのだとカミングアウトする。かくして父親は娘との近親相姦と年下の男(=息子)との同性愛+近親相姦のどちらを選ぶのかの選択を迫られる。もし前者を選べば、双子の子どもの一人が人類を滅ぼすことになるかもしれないし、後者を選べば息子は存在しない(生まれない)ことになる。話はここからさらにあっと驚く展開を見せるのだが、「ミラクル祭'18」は3月5日まで続くので、ここまでにしておこう。上演時間30分のよく練られたコントであった。

終演後、サワチさんと話をした。いつも思うことだが、ふだんの彼女と舞台の上の彼女とは別人である。今日も舞台の上の彼女は、ふだんの彼女からは考えられないようなきわどい台詞を話し、きわどい所作をくりひろげていた。役者とはそういうものだといってしまえばそれまでだが、私にはどうもふだんの彼女が「ふだんのサワチさん」というキャラクターなのではないかと思えてくるのである。

ちょっとポーズを取ってもらって撮った一枚。『ひよっこ』のシシド・カフカみたいだ。

後半に観た『モルフェウスの使役法』は上演時間1時間のよく洗練された不条理劇だった。コンピューター関連のベンチャー企業で働く(立ち上げメンバーの一人)男が主人公で、彼は「世の中には二種類の人間がいる。決断できる人間とできない人間だ」という人間観・人生観をもって、バリバリと仕事をこなしている。彼が友人の誘いにのって「明晰夢」についてのセミナーに参加したことをきっかけに、主体性とはなにか(本当に自分は自分の生を生きているのか)、現実と夢は何か違うのかいう問題に悩まされることになる。そこに企業の隠された秘密がかかわってくる。古典的な不条理劇とは違って、スタイリッシュで「出口(らしきもの)のある」不条理劇である。これを観られたのは儲けものであった。
たくさんもらったチラシの中に先日急死した大杉漣の写真が載っていた。

帰宅する前にちょっと「phno kafe」に寄って行く。

レモンとココアのケーキとあずき茶を注文。他に客はいなかったので、大原さんとおしゃべりをして、客が入ってきたのを潮時に席を立つ。

夕食はカレーライス。妻がときどきカレーが無性に食べたくなるのだそうだ。

一昨日、リョウコさんからいただいたバームクーヘンを食後にいただく。

2時、就寝。