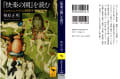

「『快楽の園』を読む」(神原正明、講談社学術文庫)を読了。というよりも目をとおした。いつものとおり覚書風に。
著者は文庫版へのあとがきで次のように記している。
「(私の研究動向としては)「快楽の園」から引き出されるボスを含む同時代の文化構造にある。‥1500年前後の中世末期からルネサンスへと移行する西洋の世界観を丸ごと結晶させた百科事典」という文章を見て、私はこの本を購入した。
私の頭ではどうも「西洋の世界観を丸ごと結晶」化されているのは理解できなかった。
やはり「結びにかえて」で著者は「「快楽の園」は無数のシンボルが織りなす曼荼羅のように、聖と俗の入りまじった夢の世界を演出している。ことに中央パネルに描かれた世界は、秩序雨正しく配置されて高邁な思想を隠しこんでいるようにも見えるし、全く逆にセクショナル・シンボルに彩られ、通俗的な駄洒落に終始する小噺集でもあるようだ。」
「まだまだ分からないことが多過ぎるし、何とか図像の意味を知りたいという私たちの期待は、いつも裏切られたままである。‥できる限り客観性のある説を紹介したつもりであるが、この絵が制作されて以降、数百年の叡智を結集しても、うまく辻褄は合ってくれない。」
私の基本的な疑問はいくら「客観性のある説を紹介し」ても、中世の全体像も、結晶化されたエッセンスも、そしてボスの描きたかったことも分からないだろうということである。著者の持つ中世の像を結ぶには、客観的な解説を幾ら並べても真実に、そして作者の求める像にはたどり着かないだろうということである。私は研究者でもないが、結局は自分で自分なりの中世の像を作り上げるしかないと専門家に突き放されてしまったようだ。
私はあまりに求め過ぎたのだろうか。










