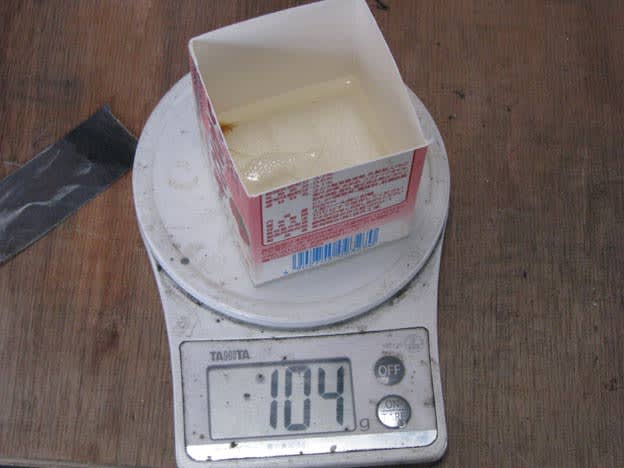ステムによって前方にオフセットされたハンドルバーは、オフセットをゼロにしたい。
ハンドル周りの部品は作る気になれば簡単に作れるが、丁度良い材料を在庫してないので、ドナーの物を加工して使用する事にした。
グリップが嵌る部分はバイクと同じで22.2φ。いわゆるテーパーハンドルなので、中心にハンドルステムが通る貫通穴を開けた。
正吉君の体にあわせてハンドル巾を出来る限り切り詰めて溶接。
これで部品の加工は全て終了したので、塗装に入る。
俺は一応、塗装に関してはある程度は本職なので(なんちゅー日本語だ)、参考までに手順を紹介。
旧塗装が残っている物はスケルトン(塗装剥離剤)である程度剥離してから、全ての部品にブラストを掛けた。
ブラストは塗装の下地処理として非常に有効。DIY塗装をする場合は、一般的にペーパー掛けなどして下地処理する事が多いと思うが、一度ブラストを使ってしまうと、アホらしくてペーパー掛けなどはやってられないほどの差がある。作業も早いし、細かく入り組んだ部分の処理も楽。そして何と言っても、塗装のノリが圧倒的に違う。ペーパー掛けだと垂れてしまうような場面でも結構な厚塗りができるので、缶スプレーで塗装してもかなりのクオリティが望める。塗装の食いつきもいいので、ヘタにプライマーを塗るよりも、ブラスト後に2液性のウレタン一発の方が良い場合すらあるほど。
今回はフレームをオレンジにして2液性のウレタンクリヤーで仕上げたかったのだが、在庫の塗料の組み合わせの都合でクリヤー以外はラッカーの缶スプレーを使うことにした。
この塗料の上からはあの塗料は塗れない・・・とか、色々あるんですわ。全てをウレタンにすれば問題はないけど、ウレタンのオレンジを1缶買わなきゃいけなくなってしまう。
プライマーを塗って、アイボリーで下塗り。
オレンジは下地の隠ぺい力が低いので、下地を白やアイボリーなどで塗ってやる必要がある。なんかルイガノっぽくてカッコいい。このままでもいいか?・・・と思ってしまうが、やっぱりオレンジを塗る。
ノズルの先っちょを回して楕円パターンを縦横変えながら、塗料が付きにくい箇所を先に塗っておく。場合によっては筆注ししておく場合もあり。
缶はお湯に漬けて暖めながらやっている。ストーブの上の鍋の中に入れる人もいるが、アリャ結構キケンなのでやめた方がいいと思います。知人の知人はそれをやって缶が爆発して、片目を失明してしまったのだそうだ。俺は俺で数ヶ月前にちょっとした事件に巻き込まれて、目の前で缶スプレーが爆発! 前髪がチリチリになってしまった。
オレンジの缶スプレーを買ってくる時、明るいオレンジと濃いオレンジの2種類があった。ホントはその中間くらいの色が良かったのだが、仕方なく濃い方をチョイス。狙った色が作れないのは缶スプレーの欠点の一つである。オレンジとグリーンは非常に難しい色で、看板屋に入って間もない頃は、注意して色を作るようにいつも言われたものだ。何せ大面積に塗ると、色見本で見たときとかなり印象が違う。大体は濃く見えるかな。
缶スプレーを買ってくる時は、経験上なるべく金額が高い物を買ってきたほうが良いと思う。高いやつと安いやつを比べると、塗料の違いも然る事ながら、ノズルの出来不出来の差が大きく感じる。
バイクの外装を塗る場合は、原則としてラッカーにしておいた方が何かと都合が良いと思う。もちろんラッカーを塗ったそのままだとガソリンには溶けてしまうが、上からウレタンを塗ることが出来る。変なのを塗ってしまうと、再塗装時に全剥離しなければならない。普通のエナメル(要するにペンキ)を刷毛塗りした人が知人におりますが・・・(笑)。
マーキングも塗装でやったほうが段差が出難くてきれいに仕上がるが、面倒臭いのでカッティングで・・・。クリヤー塗装の前に貼っておく。
正吉君マークがイイ味出してるでしょう(笑)。何度も書くようだが、「正吉君」は本名じゃありませんよ。字も全然違うのだ(笑)。
クリヤーは硬化剤を混ぜて、ガンで塗装。
ちなみに仕事ではガン塗装は滅多にやらない。刷毛5、ローラー3、筆1、吹き付け1くらいかな? 余談だが、一昔前は刷毛5、筆4、ローラー0.5、吹き付け0.5くらいだった。仕事のやりかたや求められるクオリティ、材料などが変わってきているのだ。
ガンは吸い上げ式(塗料カップが下に付いているタイプ)と落下式(カップが上に付いている)の2種類使っているが、ほとんどは落下式でやっている。何故かというと、最大の理由は下から上に向かってとか、上から下に向かって吹き付けできるから。缶スプレーもこれができないので不便だ。
ガンが無い人も、缶を二重構造にして2液性ウレタンを仕込んだ缶スプレーもあるので、今回とほぼ同じ塗装はできるはず。ただし1缶¥2000くらいだったと思うので、高くついてしまうのが欠点。
ウレタンは垂れ難く、かなり厚塗りが出来るので、ラッカーと比べてハイクオリティな塗装が可能。
塗料の種類に限らず、塗ってしばらくしたら石油ファンヒーターの前に置いて乾かしている。乾く前にやると泣きをみる場合があるので、触れるぐらいに乾いてからがオススメ。キレイに仕上げようと思ったら慌てるのは禁物で、今回くらいの大きさの物でも塗り始めてから3日間くらい掛けて塗っている。吹き付ける前に#600~#1000位のペーパーで擦ってやるとゴミも取れるし表面もテカテカに仕上がる。
全くのプライベーターが塗装をやろうと思うと、最大の問題になるのが場所でしょう。臭いもかなり出るし、塗装ミストも舞う。俺の場合は会社に垂れ流しの作業スペースがあるので、この程度の大きさの物であれば普通に塗れる。
でも、バイクのフルカウルくらいとか、車1台とかになると少々厳しい。大き目の物を塗る時は簡易ブースを作ってやっている。
組み立てて、アクスルの六角にキャップを取り付けた。コレはケガ防止もあるけど、倒した時に床に傷が入るのを防ぐ為。適当に買ってきたら、4個中2個が大きさが合わない・・・。
正吉君を跨らせてやったが、やっぱり爪先ツンツン。
サドルのクランプを引っくり返して、シート高を気持ち下げてみたが、あまり変わらないようだ。フレームの構成上、どんなサドルを持ってきても、これ以上は下げれそうにない。もっと初期段階で考えるべきであった。
丸棒を組んで専用スタンドを製作。ディスプレイ台のようなモンだ。
この状態で正吉君を乗せたら、自分で降りれなくなってベソを掻いていた。
それなのに興味深々の正吉君。
朝起きてきて、初めてこの自転車とご対面した時は、30秒くらい動きが止まっていた。
ついでに、満面の笑顔でテーブルによじ登る正吉君。
一心不乱にメシを食う正吉君。
ちょっと足つきが悪いので、この自転車はしばらく部屋の飾りかな。半年も経てば自分で乗れるようになるだろう。
カタログスペックを参考に、写真の縮尺を合わせてキャリーキッズと大きさを比較してみる。
タイヤの大きさはほぼ同じ、シートポストの位置から推測するに、キャリーキッズの最低位置とそれほどのシート高は変わらないと思われる。クソッ。それでも全長はかなり短い。
ちなみにこのミニミニ自転車、販売計画アリ。諸々の事情でこのブログ経由では売れませんが・・・。
今の所、コストと販売価格の折り合いが付かないので、もう少し先になりそう。