都月満夫の絵手紙ひろば💖一語一絵💖
都月満夫の短編小説集
「出雲の神様の縁結び」
「ケンちゃんが惚れた女」
「惚れた女が死んだ夜」
「羆撃ち(くまうち)・私の爺さんの話」
「郭公の家」
「クラスメイト」
「白い女」
「逢縁機縁」
「人殺し」
「春の大雪」
「人魚を食った女」
「叫夢 -SCREAM-」
「ヤメ検弁護士」
「十八年目の恋」
「特別失踪者殺人事件」(退屈刑事2)
「ママは外国人」
「タクシーで…」(ドーナツ屋3)
「寿司屋で…」(ドーナツ屋2)
「退屈刑事(たいくつでか)」
「愛が牙を剥く」
「恋愛詐欺師」
「ドーナツ屋で…」
「桜の木」
「潤子のパンツ」
「出産請負会社」
「闇の中」
「桜・咲爛(さくら・さくらん)」
「しあわせと云う名の猫」
「蜃気楼の時計」
「鰯雲が流れる午後」
「イヴが微笑んだ日」
「桜の花が咲いた夜」
「紅葉のように燃えた夜」
「草原の対決」【児童】
「おとうさんのただいま」【児童】
「七夕・隣の客」(第一部)
「七夕・隣の客」(第二部)
「桜の花が散った夜」
作・都月満夫
〈クラブ・マリッジ主催のパーティー会場は3階です〉
ホテルの入り口の案内板に掲示があった。
エントランスホール右手のエレベーターで三階へ上がる。エレベーターを降りると、受付があり、男女の参加者が列を作っていた。
土曜日の夜、久しぶりに参加する婚活パーティーだ。四十代後半から五十代前半にかけては、頻繁に参加していた。
転勤族で、各地を渡り歩いてきたが、北海道の女性は色白で美人が多い。帯広に来てからは、特にそれを感じていた。
誰もいない部屋に帰るのは、もう我慢できない歳になっていた。今を逃したら、もう絶望的な歳になってしまう。
カウンターで、男性参加者の受付を行っているのは、濃いエンジのジャケットにベージュのパンツスーツの女性スタッフだ。その傍らの女性参加者の受付は、細身で長身の男性だ。制服は女性と逆の組み合わせだ。
受付が終わると、安全ピンかクリップで服につける番号札と、プロフィールを記入する用紙を手渡された。番号は〈9〉番だった。
「プロフィール用紙に、お名前やご趣味などをご記入ください。女性と交換して会話していただきます。お話のきっかけになる紙なので、できるだけ詳しくお願いいたします。書き終わりましたら、〈9〉と表示された席にお座りになってお待ちください」
最後に女性参加者の名簿を渡された。
個人を特定できないように、番号とカタカナの名前だけが印刷されている。
名簿にある女性の数は十人。男性参加者も十人だ。これは、事前に登録された名簿の中から、主催者が選んだ二十人だ。
最近は人数が少ないパーティーが主流だ。
婚活をする人数が減っているのか、主催者がそうしているのかはわからない。
人数が少ない分、一人との会話時間が長くなる。コロナ感染の状況下で、スペースに余裕があり、隣との間隔が空くので、周囲を気にせずに会話ができる。男女一組ずつにパーティションで仕切ったスペースがある。このタイプのパーティーはフリータイムがない。いわゆるパーティー形式ではない。
受付から会場に入ると、低音量でバラードナンバーが流れている。ヴォーカルに寄り添うようなギターが心地よく響く。
プロフィールを記入するテーブルがあり、消毒済みのボールペンが並んでいた。
ざっと見まわしたところ、女性参加者は皆服装に気をつかっている。結婚相談所のプロフィール写真のように、ワンピース派とスーツ派がいる。白っぽい色が多い。
男性は女性と比べると服装には無頓着だ。
コットンパンツか、ダボッとしたデニムパンツだ。ジャケットを着ている男は少ない。シャツかセーターが目立つ。コートやダウンジャケットを羽織って来たのだろう。この中で、スーツ姿の私はある意味目立っていた。
私もプロフィール用紙を記入する。結婚相談所に提出した資料とほぼ同じ項目だった。
ただし、独身証明書や年収を証明する書類の提出までは求められない。
プロフィール用紙を記入し終え、パーティションで仕切られた<9>番の席に座ると、すでに女性が着席していた。大きな瞳、長い睫毛、整った鼻筋。ショートヘアで、黄色のジャケットの下の白いTシャツは、はち切れそうに大きな胸が主張している。
容姿端麗とはこのことかと思った。
テーブルは下が開いたアクリル板で仕切られていた。この隙間からプロフィールを交換するのだろう。軽く会釈をすると、相手も会釈をかえしてくれた。
音楽がフェイドアウトした。
受付の女性がマイクを手に挨拶をした。司会も担当するらしい。これまでに何百回も同じことを繰り返してきたのだろう。パーティーの流れや注意事項の説明がよどみない。
プロフィールを交換して会話を行う。
五分経過すると、男性の席が消毒され、男性が隣の席へ移動し、女性と会話をする。パートナーを替えながら、全員と会話できる。
最後に、気に入った相手の番号を指定の用紙に記入して提出する。スタッフの集計によってマッチングが成立すると、退出時にそれぞれに伝えられ、後は自由恋愛だ。連絡先を交換しても、帰りに食事に行ってもいい。
マッチングが成立したのは、最初の大きな胸の女性だ。ミツコ、八野充子という。
パーティーで彼女は積極的だった。随分と私を気に入ったようだ。理由はわからない。
彼女は三十三歳だった。二十歳以上若い女性が、積極的に私に話してくれる。私には、それがとても心地よかった。
帰りがけに、八番目に会話をした四十一歳のサリナさんに、「エロ親父」と罵られた。
彼女とは歳も近かったので、会話も弾んでいた。彼女は私を指名したのだろうか…。
この人を指名しなくてよかったと思った。
しかし、若い女性を指名した自分を見透かされたようで、ドキッとした。大きな胸に目がくらんだ自分に、少し嫌悪した。
パーティーの後、会場近くのカフェレストランで、食事をした。
現在、彼女の家族は祖母と妹の三人だと言う。母親は数年前に亡なったそうだ。
物心がついたころには、父親はいなかったそうだ。父親を知らずに育ったので、年上の男性に憧れると言った。何か事情がありそうだが、理由はあえて聞かなかった。
プロフィールには市内在住と書いたけど、実際は更別在住だと打ち明けられた。
市内在住と書いたのは、近いうちに市内で暮らしたいという願望だそうだ。
市内に友だちがいて、夜遅くなったときには、彼女の部屋に泊るという。一万円を超えるタクシー代は痛いと言った。
相手は迷惑しているのではないかと思ったが、もちろんそんなことは聞かない。
彼女はエステティシャンだという。
「エステティシャンは、美容師のような国家資格はないのよ。民間資格はあるけどね。勉強は苦手だから、経験を積んで、お店をやりたいのよ。おばあちゃん孝行したいの…」
彼女はそう言って、ケラケラと笑った。
私の自己紹介は、会場で伝えていた。
美濃木健。五十七歳。バツイチ。子どもなし。独身生活は三十年近い。転勤族なので、いつまでここにいられるか分からない。
三十分もすると、彼女は美容整形をしていると打ち明けた。
「私ね、何度も振られてるのよ。そのたびに整形したの…。振られた自分のままでいるのって嫌じゃない。これは言っとかないとね」
そう言って、ケラケラと笑った。
整形を打ち明けられ少し驚いた。しかし、今は特別なことではないのだろうと思った。
翌日からミツコさんは毎晩電話をくれた。いつも深夜零時ころだ。そろそろ眠ろうという時間にスマホが振動する。出るか…、眠るか…、迷いながらも、結局対応してしまう。
電話にでると、彼女はその日にあったことを、ケラケラと笑いながら、一方的に話す。
三夜目だったか、四夜目だったか、ミツコさんは自分の写真を送信してきた。
かなりきわどい。ホテルのベッドに横たわっている姿が真横から撮影されている。ホテルのパジャマの胸がはだけ、谷間はくっきり、瞳はうっとり。ズボンは履いていない。体の肝心なエリアはかろうじて隠されている。自撮りだというが、そうは思えない。
カメラと本人の距離は、明らかにリーチよりも離れているし、全身が写っている。男とベッドの上なのだろう。
「これ、誰に撮ってもらったんですか?」
思わず口に出た。
「あら、妬いてくれてるの? 自撮りよ。一眼レフに三脚をつけて、モニターを自分側に向けてスマホでシャッターを押せるの。写真はスマホに取り込めるわよ。職業柄、自分がどう見えているかを把握しておかないとね」
彼女はケラケラと笑った。
「今は、そんなことができるんですか?」
説明を鵜呑みにしたわけではないが、納得したような返事をした。
次の土曜日、夜八時にミツコさんから電話がかかってきた。いつもよりはるかに早い。
「今、市街にいるの。ご飯食べようよ」
賑やかな場所で、大声で話している。
ちょっと迷ったけれど、結局、駅前のホテルのイタリアンレストランで待ち合わせた。
黒いオーバーコートを脱ぐと、オレンジの花が華やかに咲いているワンピースは、夏でもないのにノースリーブ。丈は膝よりはるかに上で、下着が見えそうだ。
自慢の胸は上三分の一が見えている。
会話は盛り上がり、アルコールで血色のよくなった彼女が、今日は帰れないと言い出した。更別の自宅に帰れないことはわかっていたが、市内の友だちも不在なのだという。
「今日はもう帰れないなぁ…」
ミツコさんが上目遣いに見つめてくる。
「ケンさん、ここにお泊まりしようよ!」
彼女は私の隣に座って、腕を組み、胸を押し付けて、そう言ってケラケラ笑った。
先週の土曜日に会って以来、初めてのデート。あまりにもあっけらかんとした誘いに、私の理性は簡単に破綻した。
ホテルはシングルしか空いていなかった。週末の十一時過ぎ。どのホテルも満室だ。そんな中、やっと、ダブルルームを確保した。
ミツコさんに腕をからめられ、喜色満面。わくわくしながらホテルへ向かう。
夜風は冷たいが、そんなことは気にならないほど体が熱い。
しかし、不安が一筋の雲のように頭をよぎった。会って一週間でホテル…。後で怖いお兄さんが出て来るんじゃないだろうな…。
一度不安が生まれると、真夏の入道雲のように、どんどん膨らんでいく。
考えてみれば、彼女の派手な容姿は、とても〝素人〟とは思えない。
友人が不在の時に、あえて私を誘ったのにも意志が感じられる。
五十七歳で、バツイチは、婚活市場では概ね不利なはずだ。ジジイで、失敗経験者で、年齢差は二十歳以上ある。
それなのに、年上が好きだと言っても、三十三歳の女性が、毎日電話をするほど熱心だというのも、冷静に考えれば不自然だ。
私はチェックインの手続きの後、トイレへ行き、会社の後輩、小俣君に電話をした。
「美濃木です。こんな夜遅くに悪いね」
彼は三回の離婚経験があり、若い女性に痛い目にあったこともある。彼に言わせれば、失敗ではなく学習だという。その学習からアドバイスをもらおうと考えた。
「部長、どうされましたか?」
「相談があります。実は今、先週婚活パーティーで知り合った女性とホテルにいます。トイレから電話をしています。初めてのデートで、ホテルに誘われました。これって、大丈夫だと思いますか?」
「部長、何が大丈夫なんですか?」
「だから…、、二十歳以上も年下の女性が、いきなり誘ってきたので…。何か面倒なことになるのではないかと…」
「ああ、そういうことですか…。なんで私に電話をくれたんですか?」
「君はいろいろ経験が豊富なので…」
「経験? ああ…、あのことですか…」
「いや、別にそう言うわけじゃ…」
私は慌てて否定した。
「了解です。お急ぎでしょうから、端的に聞きます。積極的だったのは彼女ですか?」
「パーティーでは、彼女が一方的に喋っていたかな…。マッチングでペアになったので、食事に行きました。そこでも、彼女は積極的で、結構ボディータッチがありました」
「身の上話、特に不幸話はしましたか?」
「不幸話ですか?」
「家族のこととか…」
「あ…、母親は最近亡くなって、家族は祖母と妹の二人で、父親は知らないそうです」
「ああ、それで年上の男性が好きだと…」
「そう…、そう言ったよ。よくわかったね」
「わかりますよ。あと、将来の夢とかは…」
「エステの店を開きたいそうです」
「お店ですか…。服装はどうですか? 特に男を意識した挑発的なものですか?」
「あ、かなり責められている感じかな…。エステティシャンなのでそのせいかと…」
「露出は多めってことですね」
「そうです。かなり多めです」
「あと、特にセクシーな話をしましたか?」
「いや…、話というよりは、セクシーな写真を見せられたよ」
「ホテルに誘ったのは、彼女なんですね」
小俣君は、そう言うと束の間沈黙し、深刻そうな低い声で言った。
「男の気を引く話。特に身の上話は常套手段です。将来の夢も同じです。積極的でベタベタした態度。露出多めの服装。セクシーな写真。男に考える隙を与えない…。危険です」
「コマタ君、どうしたらいい?」
「そうですね…。一時間後に私が部長に電話します。危険な状況だったら、そう言ってください。すぐにフロントに通報します」
小俣君はそう言った。いい提案だ。
「助かるよ。あ、このことは内密に…」
「部長、分かってますよ」
トイレでスマホを握ったまま頭を下げた。
ミツコさんは、部屋に入いると、すぐに服を脱ぎ、ベッドに倒れ込んだ。
その姿は、あまりに無防備だった。
私は目をそらし、パジャマに着替えた。
振り向くと、彼女は寝息をたてていた。寝息はやがて、アシカの叫びのようないびきになり、ときどき歯ぎしりも重なった。
心配が杞憂であったと笑いが込み上げた。
「心配かけたけど、大丈夫そうだよ」
私は小俣君に電話をした。
仰向けのミツコさんの大きな胸は、引力に逆らって真上を向き、いびきに合わせて、ゆっくり上下している。
私は彼女に布団をかぶせながら、この顔とこの体を手に入れるのに、いくらかかったのだろうと、余計な心配をした。
ミツコさんは振られるたびに整形したと言ったが、それは違う気がした。
整形をするたびに、どんどん自分を見失っていったのではないかと思った。
私はまったく眠れず、いびきと歯ぎしりの二重唱の中で朝を迎えた。
十一時にチェックアウトし、ランチをすることにした。昼間の光の中で見るミツコさんの姿は、強烈だった。形状のはっきりした顔も、大きな胸も、派手なワンピースも、太陽の下では、夜よりもはるかに目立つ。
ミツコさんはやはり腕をからめてきた。すれ違う人の視線がどうしても気になる。私とはバランスが悪すぎる。
私は年甲斐もなく、若い女性に目がくらんだことを心底後悔していた。
彼女の、あっけらかんとした天真爛漫な性格は、天性のものなのだろう。
それは、間違いなく長所なのだと思う。
しかし、彼女と一緒に暮らしていくのは、賑やかで落ち着かないと感じていた。
私は平穏無事に過ごしたいと思う。
どう言えば、彼女を傷つけず、整形もさせずに別れられるか、必死で考えていた。
人は見かけじゃないとは言えないし…。
#StandWithUkraine
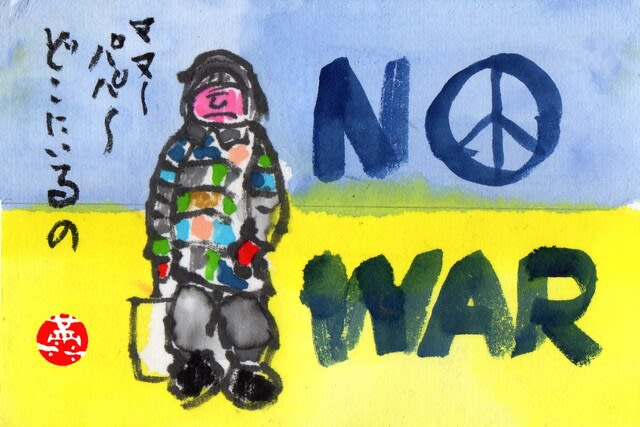
■昨日のアクセスベスト3


















