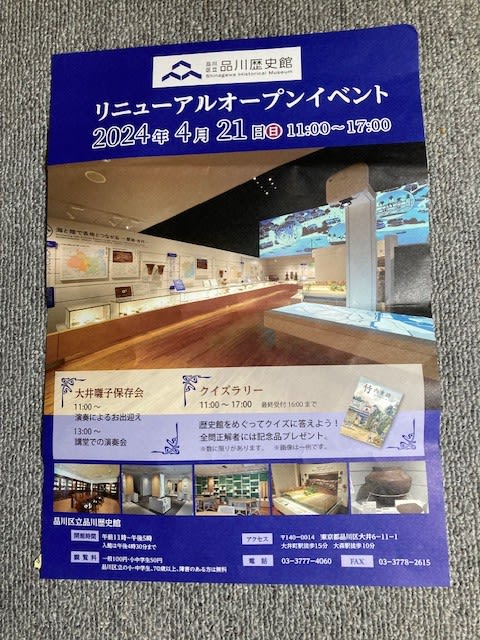また一つ知らない漬物に関する言葉を知った。日本経済新聞のコラムで料理研究家の土井善晴さんが書いていた言葉。
-香の物は日本の漬物の事を言うので、韓国のキムチとかドイツのサワ-クラウトのような外国の漬物は香の物とは言わない。それは香の物という言葉の成り立ちから来ていて鎌倉時代から室町時代に茶の湯や香道文化が発展すると、漬物が「香の物」と呼ばれるように。 これはお香の香りを楽しむ「聞香(もんこう)」の際に、香りの強い漬物を口にして嗅覚をリセットしたことに由来するといわれています。 江戸時代初期には、江戸や京都、大阪に漬物専門店である「香の物屋」が誕生し大繁盛となります。
漬物の歴史の文献では良く引用されるのは延喜式で平安時代の文献で、それ以前の記録がない。しかし塩と野菜があれば保存食の漬物が存在しないことは無いので、記録がないだけと思われる。
延喜式は 10 世紀に作られた官人の業務マニュアルであり、古代日本各地の特産物、全国の神社、朝廷で用いる物品の原材料、神様への捧げ物など、様々な情報が掲載されています。延喜式に記述があっても、一般人の食事とは見ない方が良いと感じる。
日本独自の食は鎌倉時代から室町時代に大変化し、日本の独自性が出て来たと思われる。汁飯香の言葉から土井善晴さんの本を借り出し読むがやはり和食の人で、戦後の混乱期からアメリカの援助食糧で日本の和食文化が壊されていると思っているようだ。和食を語る人の人材不足が今の米消費量の減少につながる。長寿世界一の日本人の基本食を今まで宣伝で否定していた戦後史がある。この辺りは農政の人達のタコツボ行政の欠点だろう。ペリ―来航時から日本人はアメリカ人との対格差で栄養の問題と考えていて、今でもカルシウムの摂取で牛乳が米食に病院でも学校でも出てくる。牛乳の無い江戸時代でもカルシウムをどこかで食べている。
一般人
-香の物は日本の漬物の事を言うので、韓国のキムチとかドイツのサワ-クラウトのような外国の漬物は香の物とは言わない。それは香の物という言葉の成り立ちから来ていて鎌倉時代から室町時代に茶の湯や香道文化が発展すると、漬物が「香の物」と呼ばれるように。 これはお香の香りを楽しむ「聞香(もんこう)」の際に、香りの強い漬物を口にして嗅覚をリセットしたことに由来するといわれています。 江戸時代初期には、江戸や京都、大阪に漬物専門店である「香の物屋」が誕生し大繁盛となります。
漬物の歴史の文献では良く引用されるのは延喜式で平安時代の文献で、それ以前の記録がない。しかし塩と野菜があれば保存食の漬物が存在しないことは無いので、記録がないだけと思われる。
延喜式は 10 世紀に作られた官人の業務マニュアルであり、古代日本各地の特産物、全国の神社、朝廷で用いる物品の原材料、神様への捧げ物など、様々な情報が掲載されています。延喜式に記述があっても、一般人の食事とは見ない方が良いと感じる。
日本独自の食は鎌倉時代から室町時代に大変化し、日本の独自性が出て来たと思われる。汁飯香の言葉から土井善晴さんの本を借り出し読むがやはり和食の人で、戦後の混乱期からアメリカの援助食糧で日本の和食文化が壊されていると思っているようだ。和食を語る人の人材不足が今の米消費量の減少につながる。長寿世界一の日本人の基本食を今まで宣伝で否定していた戦後史がある。この辺りは農政の人達のタコツボ行政の欠点だろう。ペリ―来航時から日本人はアメリカ人との対格差で栄養の問題と考えていて、今でもカルシウムの摂取で牛乳が米食に病院でも学校でも出てくる。牛乳の無い江戸時代でもカルシウムをどこかで食べている。
一般人