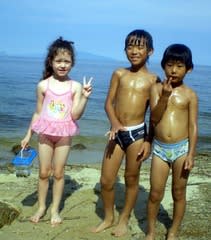天候不順を絵に描いたような今年の夏。
今日は大丈夫だろうとたかをくくって近くの海に行っていても、急に雲が出てきたな…と思うとたちまち降り始める。
例年のように、雲が出るだけで通り過ぎてはくれない日が多かった。その上、夕立とは思えない長雨になったりする。
夕立の後に虹が出るのは例年と大きく変わらない。多くの場合虹の向こうに青空が広がってくれると「ああ、夕立だったのか…涼しくなるぞ…」と期待もするし、空の青さや、湧き上がる積乱雲の白さに映えて、虹も美しく見栄えがする。
ところが世の中、一筋縄ではいかない。
虹の向こうに、今にも降りそうなどんより雲がかかっていて、虹の存在さえかすんでしまう、本来の姿とは違う“雲の中の虹”が結構見られた。
しかし、こんな虹の姿も子供達には見せておく必要がある。でなければ、虹と言えば美しく・夢を抱かせるのも…という単純知識だけ植え付けては片手落ちであろう。
我が岩国市の将来像を語る上でも、“岩国再生レインボーシティビジョン” なる構想を勉強したこともある。
『先進医療都市構想』『民間空港再開による企業誘致構想』『治山治水・農林漁業活性化構想』など。
言葉は硬いが我々岩国市民にとって、推し進めていきたい中味ではある。
しかし、用地の確保・先行投資の壁など大きな問題が立ちはだかる。
構想はレインボーでも、曇り空に覆われて、すっきり見えにくい今年の夏空の虹のようだ。
今回の国政選挙の結果が大きく左右することも間違いない。やはり、虹を夢みるのは一筋縄ではいかないようである。
それでも、虹のような夢を追い続けるのも人情。出来るなら、子供達にも夢を抱かせる“レインボー”であって欲しい。
( 写真:曇り空に覆われて、冴えない今年の“レインボー” )
今日は大丈夫だろうとたかをくくって近くの海に行っていても、急に雲が出てきたな…と思うとたちまち降り始める。
例年のように、雲が出るだけで通り過ぎてはくれない日が多かった。その上、夕立とは思えない長雨になったりする。
夕立の後に虹が出るのは例年と大きく変わらない。多くの場合虹の向こうに青空が広がってくれると「ああ、夕立だったのか…涼しくなるぞ…」と期待もするし、空の青さや、湧き上がる積乱雲の白さに映えて、虹も美しく見栄えがする。
ところが世の中、一筋縄ではいかない。
虹の向こうに、今にも降りそうなどんより雲がかかっていて、虹の存在さえかすんでしまう、本来の姿とは違う“雲の中の虹”が結構見られた。
しかし、こんな虹の姿も子供達には見せておく必要がある。でなければ、虹と言えば美しく・夢を抱かせるのも…という単純知識だけ植え付けては片手落ちであろう。
我が岩国市の将来像を語る上でも、“岩国再生レインボーシティビジョン” なる構想を勉強したこともある。
『先進医療都市構想』『民間空港再開による企業誘致構想』『治山治水・農林漁業活性化構想』など。
言葉は硬いが我々岩国市民にとって、推し進めていきたい中味ではある。
しかし、用地の確保・先行投資の壁など大きな問題が立ちはだかる。
構想はレインボーでも、曇り空に覆われて、すっきり見えにくい今年の夏空の虹のようだ。
今回の国政選挙の結果が大きく左右することも間違いない。やはり、虹を夢みるのは一筋縄ではいかないようである。
それでも、虹のような夢を追い続けるのも人情。出来るなら、子供達にも夢を抱かせる“レインボー”であって欲しい。
( 写真:曇り空に覆われて、冴えない今年の“レインボー” )