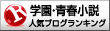「ロンドンは食べものはおいしいし、何といっても英語が通じて気楽だから、すべて楽しめるだろうが、イギリス料理は食べないことだ」
「ロンドンは食べものはおいしいし、何といっても英語が通じて気楽だから、すべて楽しめるだろうが、イギリス料理は食べないことだ」あるイギリス史の先生の言葉。とくにシェファード・パイは食べるなと。
「アメリカの料理は不味い」「アメリカ人は味覚音痴だ」と言われることもあるけれど、決してそんなことはない。
もちろん開拓時代や南北戦争時などの食糧事情やライフスタイルもあって、缶詰やサプリメントなど簡単に食べられるものが重宝される傾向はあるけれど、人種のるつぼといわれたアメリカだけに、ここには世界のすべての料理があるし、その食材だって捨てたものじゃない。
パーティーにお呼ばれされたらハンバーガーが出てきたなんて話もあるけれど、本当に美味しいハンバーガーをみんなで仲良くバーベキューグリルを囲みながら作って食べる醍醐味を知ったらバカにはできない……。
いろいろ先入観から食べずにスルーして後悔したこともあれば、これは美味しくはないんじゃないかなと思いつつ食べてみたらやっぱり不味かったとか、日本のノンフィクション作家が、1950年代後半から1970年代にかけてのアメリカ滞在中に見聞きしたことをベースに、「アメリカの食卓」を通じてアメリカ文化を語った回想録的なエッセー集+レシピ。
料理本は多いけれどビジュアル的に美味しそうに料理を見せることはなく、ただ手順と分量しか書いてない。そこには食べものはなんでも感謝して食べるべきで、ピューリタン的には賛美したり感嘆するものじゃないという意識があるのではないかとか、あるいは知的階級の人間は太っていてはいけない。だから温かくて美味しいものは食べさせては食べ過ぎて良くないという考えがあって……と、さまざまな引用やら体験談の中から引っ張り出してきています。
それでも、美味しいものはたくさんある。
ローストビーフは最高のメインディッシュだし、河沿いに内陸部にまで広がっていったクリオール料理は絶品で、欧羅巴に滞在していたマーク・トウェインは焼き林檎から亀のスープまで食べたいアメリカ料理を書き連ねていた……という話から、アメリカ人に日本料理を振る舞おうとしたり、ユダヤの人を料理でもてなそうとしての失敗談とかあれこれ。
文庫版はエッセーとして、文化論として面白く、夫婦で愛読していたのだけれど、あまりに面白くて知人に貸したら無くなってしまい、謝罪を受けて買い直したら1982年のソフトカバー版でした。これはこれで。
各章ごとにレシピがつくけれど、これに写真やイラストがなく文章だけというところがアメリカ流です。
【アメリカの食卓】【本間千枝子】【文春文庫】【文藝春秋】【サントリー学芸賞】【タートル・スープ】【ラフカディオ・ハーンの料理書】【ヴァジニア・ハム】【ピラミッドケーキ】【フランス料理教室】【レズビアンバー】【フィッシャー夫人】【リトル・イタリー】【ユダヤ教】【禁酒法】