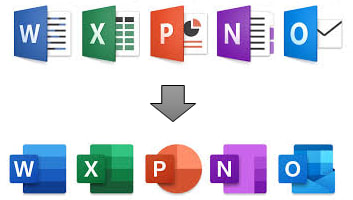読者の皆さまこんにちは。事務局の渡邉です。
6月より実家の事業承継を目指して岡山に帰る事となりました。
それに伴い勤めていた会社も先週末を持って退職しました。
この機会に私の勤務先について書きたいと思います。
(あくまで個人的な見解になります。)
私が勤めていた会社は、米国資本の医療機器メーカーで手術支援ロボットを販売していました。
本社はシリコンバレーにあります。
ロボットと言っても勝手に動いて手術をするわけではなく、ドクターが3Dの画像を見ながら操作をすると
ロボットのアームがそれ通りに動き手術ができる、という物になります。
ロボット支援手術の何が良いかというと、
①内視鏡手術であり、患者の体を切るのはロボットのアームが通る穴だけで良いので患者の負担が少ない。
②画像の立体感とロボットの動きの正確性により、従来の内視鏡手術より圧倒的に簡単
③ドクターや助手にとっても体力的な負担が少ない。
④複数のドクターで同じ画像を見ながら手術ができるので教育効果も高い
などなど、たくさんのメリットがあります。
ロボット支援手術は今後も成長産業の一つと目されており、大手医療機器メーカ―も続々と
ロボット開発に乗り出す等競争が激化することが見込まれています。
国内においても、ロボット支援手術は急速に広まってきています。
保険適用できる術式も従来は2つでしたが、昨年は新たに12の術式が追加となりました。
私の勤務先も加速度的に成長を遂げており毎年増収増益、という状況でした。
私はLogisticsの担当で、ロボット本体の他、付属品類や保守部品等の物流を管理しておりました。
新製品も続々と上市しており、取り扱う物量も毎年30~40%以上増加する等、変化の速い職場でした。
私の部署では業務量は増加しても人員の増加は無く、常に業務改善を図っていかなければついていけない
というシビアな環境でしたが、毎日がエキサイティングで楽しく仕事ができました。
そんな会社に勤めていた私が最も魅力的に感じていたのは、「人材の多様性」です。
米国本社はシリコンバレーにあるだけあって、国籍・年齢・性別を問わず多種多様な人が働いていて、
皆仕事熱心です。「外国人は残業などしない」というイメージを持っていましたが、全くそんなことは無く
現地時間の深夜でもアメリカ人から平気で連絡が来ます。
日本においても社員の国籍は多様で、様々なバックボーンを持つ社員が在籍していました。
この様に多様な人材を支えるため、柔軟な勤務体系や教育システムが整備されており、
自由で働きやすい環境でした。日本法人では毎年社員旅行(今年はグアムでした)やパーティも企画されており、
社員同士の交流も図られています。
そして、「患者のためにロボット支援手術を広める」というミッションが全社員に浸透しています。
多様な人材が共通の目的を持って仕事を進めているからこそ先進的なアイデアが生まれ、加速度的な成長を実現
してきたのだと思われます。
医療機器は行政からの管理も厳しく、アナログで不都合な面も多々ありましたが、それでもここではチーム一丸
となって業務に取り組む、ということができ、私にとっては大きな財産となりました。
今後もこの経験を基に実家の会社においても社員にとってエキサイティングで働きやすい職場づくりを目指して
いきたいと思うようになりました。
会社には感謝しかなく、書きたい事もたくさんあるのですが、ブログではこの辺でとどめておきます。
最後に、事務局として私がブログを書くのも今回で最後となりました。今までありがとうございました。