ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)の決勝を見てから実家へ向かいました。
お彼岸なのですがお墓がちと遠いので、家族揃って実家の仏壇にお参りで許してもらいました。
許してもらえたかな?
【王ジャパン、世界一!】
朝からもう気が気じゃなくて、7時前にはもう目が覚めてしまいました。
別に野球のせいばかりとは言えないにしてもどこか興奮していたのかも知れません。
試合は11時からという話だったのに11時15分になってもまだ始まりません。なんとものどかなものですが、これが世界標準なのでしょうか。
試合の方は、一回にヒットやフォアボールでチャンスを広げたところで、デッドボールで先制点を取るという、なにやら荒れた展開で始まりました。
小笠原も外角の球を良く我慢してフォアボールで追加点、今江が韓国戦でのエラーを帳消しにするセンター前ヒットでなんと初回に4点を取りました。これは幸先がよい。
しかしキューバも簡単にずるずると戦意を喪失するということにはならず、松阪が先頭バッターにホームランを打たれキューバも反撃開始です。
その後日本の2点追加点で6-1になったときは、もう安全圏かと思われたのですが、キューバもピッチャーが渡辺(俊)に変わってからは、日本にエラーも出始めて、2点を返され、さらに8回裏には2点ホームランまで打たれてしまい、一気に土俵際まで押し返されたような気がしました。
ところがところが、最後の役者はやはりイチロー!突き放して欲しい時にライト前への適時打を見事に打ってくれ、エラー気味で意気消沈気味の川崎もそれまでのことを全部吹き飛ばすような劇走で本塁生還!
私は見ていてタイミング的に「アウトか!」と思いましたが、右手がしっかりとホームベースを掃いていました。これはよく見ていてくれた審判のファインプレーです。
こうなると再び流れは日本に傾いて福留のタイムリーに小笠原の犠牲フライと畳みかけることが出来ました。
実際生で見ていると、「もう安心…」とは思うものの自信が持ちきれませんでした。大塚がツーアウトから最後のバッターを三振に取ってくれたときには、本当に嬉しさがこみ上げてきました。
本当に良くやってくれました。日本チームが誇らしいです。
※ ※ ※ ※
今回の始めてとなる野球での世界一決定戦。どのチームも自国の威信をかけて本当に精一杯戦ったと思います。
テレビでは、キューバの監督のインタビューが放送されていましたが、「日本はよいチームだった。おめでとう」と言った後に、「WBCではお金のためではなく、国の旗のために戦うことが出来た。自分のためでなく旗のために戦うことができた」というコメントを述べていました。
世の中は誰でも、心を寄せて一致団結する時のシンボルとして、当たり前に旗を使います。「3人集まるところ、旗と歌の無きはなし」という言葉を聞いたこともあります。日の丸が世界の人達が見ている中で翻っているのは実に嬉しいことです。
普段はほとんど笑顔を見せず、修験者のような風貌のイチローまでもが、まるで子供のようにはしゃいでいました。本当に心底嬉しかったんでしょうね。
「カゴに乗る人、かつぐ人、そのまた草鞋を作る人」と言われますが、みんながみんな松阪やイチローではなくて、それぞれに与えられたポジションと期待に応えたことの結集が、この世界一の称号なのですね。
日本中に歓喜をもたらしてくれた選手とチームにもう一度お礼を言いたい。ありがとう、本当にありがとう!
お彼岸なのですがお墓がちと遠いので、家族揃って実家の仏壇にお参りで許してもらいました。
許してもらえたかな?
【王ジャパン、世界一!】
朝からもう気が気じゃなくて、7時前にはもう目が覚めてしまいました。
別に野球のせいばかりとは言えないにしてもどこか興奮していたのかも知れません。
試合は11時からという話だったのに11時15分になってもまだ始まりません。なんとものどかなものですが、これが世界標準なのでしょうか。
試合の方は、一回にヒットやフォアボールでチャンスを広げたところで、デッドボールで先制点を取るという、なにやら荒れた展開で始まりました。
小笠原も外角の球を良く我慢してフォアボールで追加点、今江が韓国戦でのエラーを帳消しにするセンター前ヒットでなんと初回に4点を取りました。これは幸先がよい。
しかしキューバも簡単にずるずると戦意を喪失するということにはならず、松阪が先頭バッターにホームランを打たれキューバも反撃開始です。
その後日本の2点追加点で6-1になったときは、もう安全圏かと思われたのですが、キューバもピッチャーが渡辺(俊)に変わってからは、日本にエラーも出始めて、2点を返され、さらに8回裏には2点ホームランまで打たれてしまい、一気に土俵際まで押し返されたような気がしました。
ところがところが、最後の役者はやはりイチロー!突き放して欲しい時にライト前への適時打を見事に打ってくれ、エラー気味で意気消沈気味の川崎もそれまでのことを全部吹き飛ばすような劇走で本塁生還!
私は見ていてタイミング的に「アウトか!」と思いましたが、右手がしっかりとホームベースを掃いていました。これはよく見ていてくれた審判のファインプレーです。
こうなると再び流れは日本に傾いて福留のタイムリーに小笠原の犠牲フライと畳みかけることが出来ました。
実際生で見ていると、「もう安心…」とは思うものの自信が持ちきれませんでした。大塚がツーアウトから最後のバッターを三振に取ってくれたときには、本当に嬉しさがこみ上げてきました。
本当に良くやってくれました。日本チームが誇らしいです。
※ ※ ※ ※
今回の始めてとなる野球での世界一決定戦。どのチームも自国の威信をかけて本当に精一杯戦ったと思います。
テレビでは、キューバの監督のインタビューが放送されていましたが、「日本はよいチームだった。おめでとう」と言った後に、「WBCではお金のためではなく、国の旗のために戦うことが出来た。自分のためでなく旗のために戦うことができた」というコメントを述べていました。
世の中は誰でも、心を寄せて一致団結する時のシンボルとして、当たり前に旗を使います。「3人集まるところ、旗と歌の無きはなし」という言葉を聞いたこともあります。日の丸が世界の人達が見ている中で翻っているのは実に嬉しいことです。
普段はほとんど笑顔を見せず、修験者のような風貌のイチローまでもが、まるで子供のようにはしゃいでいました。本当に心底嬉しかったんでしょうね。
「カゴに乗る人、かつぐ人、そのまた草鞋を作る人」と言われますが、みんながみんな松阪やイチローではなくて、それぞれに与えられたポジションと期待に応えたことの結集が、この世界一の称号なのですね。
日本中に歓喜をもたらしてくれた選手とチームにもう一度お礼を言いたい。ありがとう、本当にありがとう!











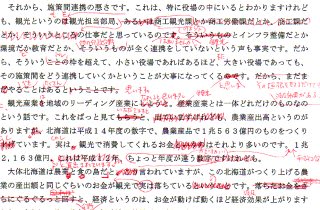




 。
。




