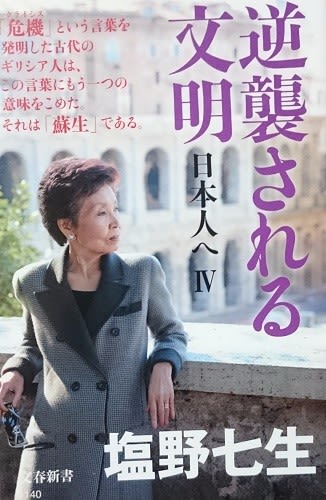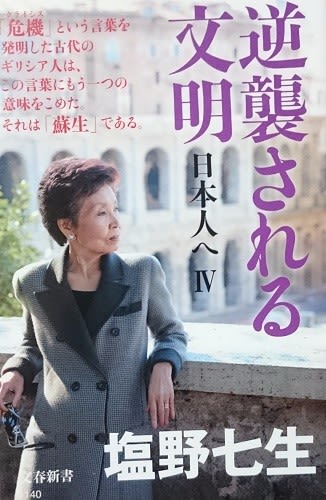
「ローマ人の物語」で知られる、ヨーロッパの歴史小説家塩野七生さんの最新刊「逆襲される文明~日本人へⅣ」(文春新書)を読みました。
文芸春秋の2013年11月から2017年9月号に、塩野さんが書いているエッセイを集めた新書。
普段はイタリアに住んでいて、ヨーロッパ特にEUの混乱ぶりを目の当たりにしている著者が、ヨーロッパについて評論するとともに、日本に帰国した際に彼我の差を観て、日本を評論したエッセイの数々は、長く歴史を見て考え抜いた著者ならではの視点が新鮮です。
著者の塩野さんは、今執筆中の『ギリシア人の物語』の第三巻で作家生活が50年になるのだそうで、「本格的な、つまり勉強して考えてその結果を書くという歴史エッセイは、これで終わりにしようと決めた」とこの本の中で書いています。
ローマ、ベネツィア、十字軍そしてギリシアと書いてきて、最近著者は「五十年間西洋史を書いてきて、何を学んだのかと考えるようになった」と言っています。
真の勉強とは、答えを教えてもらうことではなくて、人生の過程の中から答えを自分なりに見つけることなのです。
塩野さんが特に『ギリシア人の物語』三部作を書きたいと思った動機は二つあるそうで、一つは古代のギリシア人を分かりたいと思ったことで、二つ目は、彼らの創造した政体である民主制が、なぜある時代には機能し、なぜある時期からは機能しなくなったのかを分かりたいと思ったから、なんだそう。
古代ギリシアのアテネが良き民主政から衆愚政に変わった境目は偉大な政治家であったペリクレスが死んだこと、というのが定説なのだそうですが、一夜にしてアテネの民衆が愚か者になったわけでもないだろうに、というのが著者の素朴な疑問。
そしてその思いは、「要するに『民主主義』と言えばそれだけで問題が解決すると思い込んでいる人々への疑問を、書いていくことで晴らしたかったのだ」と書いています。
そうか、買ってあったけれどまだ読んでいない「ギリシア人の物語」をようやく読む気になってきました。
◆
塩野さん自身、かなり率直な物言いをする方なので、思ったことをズバズバと書いていますが、文体に品があるのと、スパイスのようなユーモアを忘れないので、読後感は爽やか。
『民主政が危機に陥いるのは、独裁者が台頭してきたからではない。民主主義に内包されている欠陥、(つまりは根源である権利の平等ということ)が表に出てきたからなのです』として、"リーダー国があってはならない"とされているEUのシステムは、指揮命令系統が不明確で責任が誰にあるかもわからない、という点で民主主義の欠陥品のようだ辛辣に批判しています。
「民主主義を唱えていれば民主主義は守れると信じている善男善女は、羊の群れを柵の中に入れるには羊一匹ずつの自由意思を尊重していてはいつになっても実現せず、羊飼いが追い込んでこそ実現するのだという事実を、考える必要もないし考えたくもない、と思っているのであろうか」とも。
どのような政体であろうとしっかりしたリーダーが必要だ、という歴史の現実を思い起こす必要がありそうですね。
◆
著者は、日本で議論されていた軽減税率は良策とは思っていないと述べたうえで、消費税について独自の提案をしています。
それは、「ある地方は消費税が10%でもある地方はその半分、というような政治もありではないか」というもの。
税が半分にすることで、その土地に人が住んで経済が活性化することを導くことこそ政治の領域だ、というのです。
選挙が始まった今の時期なので、余計に政治と言うものを塩野さんがどう感じているかが印象に残ります。
この本を読んで、語られている多くの政治的課題のうち、歴史に残るようなテーマは何かを長い時間的俯瞰を感じながら眺めると、ちょっと心が落ち着いてくるような気がします。
がちゃがちゃした言葉の投げかけあいは置いておいて、自分なりの頭を整理するためにも良い一冊です。