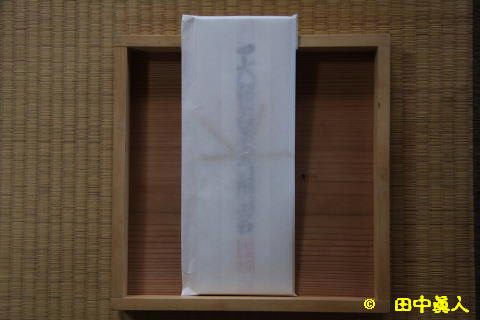この日の朝は冷え込んだからかどうか判らないがエンジンが一発で始動しなかったスズキエブリイジョインターボ。
冷えておればアクセルを踏み込んでエンジンキーを回す。
そう教えてもらったことがある。
が、なんとも・・・である。
ギュギュをし続けていけばバッテリーが上がってしまう。
何度も試す時間の余裕はない。
出勤時間が間に合わない朝のトラブル。
スタータがおかしいのか、それとも自動チョークの不良なのか。
今年の2月は冷え込むどころか雪が積もった日もあった。
そのときもエンジンは始動しなかった。
そうであればアクセルを踏みこんでエンジンキーを回す。
それで動いていたマツダスクラム時代を思い出したが、思い出に浸っている場合ではない。
電車で行こうと思いかけたが、やはり自転車だ。
折りたたみ自転車で通勤していたことがある。
勤務シフトが替って昼過ぎには終えるようになった。
昼飯は我が家である。
早く戻ることがお腹に優しい。
いつしか自転車通勤はすることもなく自動車に移っていった。
冬は寒い。
防寒着・手袋・ズボンバンドを探して着替える。
タイヤ空気を入れている時間もない。
とにかく急げである。
ギヤとチェーンがペダルを踏み込むたびにギリギリを音がする。
油切れである。
1kmも走れば汗がでてくる自転車走行。
事務所まで30分間。
いつもより10分遅れで到着した。
仕事を終えて帰りはしんどい。
行きは下りだが帰りは登り。
走行路もガタガタ道。
10分オーバーの40分で帰宅した。
遅くなった昼食は午後2時半。
帰宅するなりエンジンキーを回した。
一発でかかった。
翌日の朝は問題なく一発でかかったエンジン。
何が原因か判らないが一時的な事象であろうと済ませた。
二日目の17日も問題なく一発でかかる。
薄氷となった18日は気温が3度。
冷え込みどころか突風が吹き荒れる日だが、エンジンは支障なくかかる。
ところが19日の朝はまたもや同事象が発生した。
エンジンキーを回してもギュルギュル。
回しながらアクセルを踏み込んだら回転した。
エンジンは始動したものの、これはまずい状態だ。
山間であれば間違いなく気温は零下。
取材に出かけた先で始動かなかったら大変なことになる。
そう思って中古のエブリイジョインターボを購入したAKGコーポレーションに現象を電話で伝えた。
寒くなってからは顧客からの問い合わせが多くなった冬期のエンジン始動。
やはりかかりにくくなっているそうだ。
点検する期間は代車を準備するというので走った。
代車はダイハツミラジーノ。
ワイン色の車は奇麗だがシートはなぜか焼け焦げた穴がぽつぽつある。
そんなことはかまっていない。
アクセルを踏み込めばそう快に走り出す。

戻って車体カラーが気に入ったかーさんが云った。
「これに買い替えたら・・・」の一言。
それはともかくかかりにくい事象の原因が判明したのは数日後の12月24日。
エンジン始動不良はバッテリーの劣化もあるが、容量不足もあった。
バッテリー交換は大型に切替交換。
費用は12000円にもなったが、安心するための出費と思って対応した。
もう一つ懸念していた不安材料。
低水温表示灯の長時間点灯である。
この原因はサーモ不良による水温度計不備。
調整・手数料はオマケ対応にしてくれた。
これで冬場も安心して運転することができる。
(H26.12.15 SB932SH撮影)
(H26.12.19 SB932SH撮影)
冷えておればアクセルを踏み込んでエンジンキーを回す。
そう教えてもらったことがある。
が、なんとも・・・である。
ギュギュをし続けていけばバッテリーが上がってしまう。
何度も試す時間の余裕はない。
出勤時間が間に合わない朝のトラブル。
スタータがおかしいのか、それとも自動チョークの不良なのか。
今年の2月は冷え込むどころか雪が積もった日もあった。
そのときもエンジンは始動しなかった。
そうであればアクセルを踏みこんでエンジンキーを回す。
それで動いていたマツダスクラム時代を思い出したが、思い出に浸っている場合ではない。
電車で行こうと思いかけたが、やはり自転車だ。
折りたたみ自転車で通勤していたことがある。
勤務シフトが替って昼過ぎには終えるようになった。
昼飯は我が家である。
早く戻ることがお腹に優しい。
いつしか自転車通勤はすることもなく自動車に移っていった。
冬は寒い。
防寒着・手袋・ズボンバンドを探して着替える。
タイヤ空気を入れている時間もない。
とにかく急げである。
ギヤとチェーンがペダルを踏み込むたびにギリギリを音がする。
油切れである。
1kmも走れば汗がでてくる自転車走行。
事務所まで30分間。
いつもより10分遅れで到着した。
仕事を終えて帰りはしんどい。
行きは下りだが帰りは登り。
走行路もガタガタ道。
10分オーバーの40分で帰宅した。
遅くなった昼食は午後2時半。
帰宅するなりエンジンキーを回した。
一発でかかった。
翌日の朝は問題なく一発でかかったエンジン。
何が原因か判らないが一時的な事象であろうと済ませた。
二日目の17日も問題なく一発でかかる。
薄氷となった18日は気温が3度。
冷え込みどころか突風が吹き荒れる日だが、エンジンは支障なくかかる。
ところが19日の朝はまたもや同事象が発生した。
エンジンキーを回してもギュルギュル。
回しながらアクセルを踏み込んだら回転した。
エンジンは始動したものの、これはまずい状態だ。
山間であれば間違いなく気温は零下。
取材に出かけた先で始動かなかったら大変なことになる。
そう思って中古のエブリイジョインターボを購入したAKGコーポレーションに現象を電話で伝えた。
寒くなってからは顧客からの問い合わせが多くなった冬期のエンジン始動。
やはりかかりにくくなっているそうだ。
点検する期間は代車を準備するというので走った。
代車はダイハツミラジーノ。
ワイン色の車は奇麗だがシートはなぜか焼け焦げた穴がぽつぽつある。
そんなことはかまっていない。
アクセルを踏み込めばそう快に走り出す。

戻って車体カラーが気に入ったかーさんが云った。
「これに買い替えたら・・・」の一言。
それはともかくかかりにくい事象の原因が判明したのは数日後の12月24日。
エンジン始動不良はバッテリーの劣化もあるが、容量不足もあった。
バッテリー交換は大型に切替交換。
費用は12000円にもなったが、安心するための出費と思って対応した。
もう一つ懸念していた不安材料。
低水温表示灯の長時間点灯である。
この原因はサーモ不良による水温度計不備。
調整・手数料はオマケ対応にしてくれた。
これで冬場も安心して運転することができる。
(H26.12.15 SB932SH撮影)
(H26.12.19 SB932SH撮影)