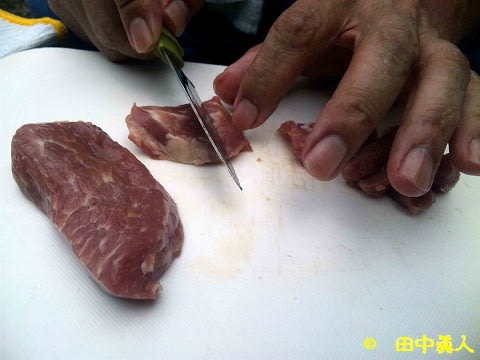この日は極端に寒さを感じる。
昨日の天気予報通りになった急降下気温は身体に堪える。
身体が震えているような感じも受けるが、それは心臓のドキドキ感。
昼食を摂った直後の心拍数は75拍。
昨日までなら徐々に冷めていくような感じだったが、この日は薬を要求するまでに陥った。
薬は昨年の11月に診察を受けた循環器内科医師の診立て。
処方された内服薬はワソラン錠。
120拍にも上昇したど頻脈状態に処方してもらった。
一時は入院手続きも終えて電極カテーテルアブレーション処置をすることになっていた。
予定していたが急激に落ち着いたが、本来ならば心房粗動アブレーション処置をしているところだった。
ところが処方されたワソラン錠を服用することで治まった。
入院・処置は消えた。
その後も少し上昇する日もあったが、服用すれば一日限りで治る。
医師からはご自身の判断で必要としたときに服用してくださいと云われていたが、その後は何事も起こらなくて今日に至っている。
3カ月検診においても異常値は認められない。
そういう状態が、突然に・・・。
いや、異常の予兆は一週間ほど前から訪れていた。
私は毎日の朝、昼、晩則後の処方箋を服用する。
そのときに必ず計測する血圧に心拍数。
値の変動は自身で確認しているから傾向も絶えず認知している。
その計測値を振り返ってみる。
心拍数が高めとする基準値はないが、身体の反応から68拍以上になった兆候日・時間を拾ってみる。
9月19日の昼は69拍。
20日の晩は76拍。
21日の晩は71拍。
22日の晩も70拍。
23日の昼は72拍で晩が69拍。
24日の昼は取材に出かけていたので計測はしていないが、晩は72拍。
この日の取材地は吉野町山口―大宇陀栗野―吉野町平尾巡り。
次の取材時間までは待機の休息。
無性に身体を休めたくなる日だった。
1カ所目は吉野町の三茶屋。
もう1カ所は大宇陀の道の駅。
ぐったりした身体を休めていた。
25日の晩は67拍。
そして本日26日の昼が75拍である。
これまでの最高値に達した。
危険水域と判断してワソラン錠を1錠飲む。
ドキドキ感は止まずに座る姿勢が苦になる。
横たわってひと眠りしたが、ドキドキ感に変化はない。
夕方5時にもう1錠を追加服用する。
少しはマシになった感があるが、難儀だったのが両足とも発症したこむら返り。
寝ているときや座しているときに発症しやすいこむら返り。
発症すればすぐに立ち上がる。
歩いたりして数分間。
立っておれば解消される。
この原因は気温である。
寒さが厳しくなったら足先の筋肉を刺激して収縮する。
手で揉んでコトを済ませることもしてきたが、最近は“立つ“ことで治している。
異常な寒さに足の筋肉縮小。
治すには温めるしかないと判断して、電子レンジでチンして温める温かい用具で足を包める。
また、部屋にずっと敷いていたホットカーペットも電源オン。
温かくなったら機嫌が治った。
19時、入浴する前に念のために計測した心拍数は67拍。
やや落ち着いてきた。
それは気分だけであり、症状に変化が見られない。
効き目が見られるのはいつ。
そう思って飲み続けるワソラン錠。
朝、昼、晩の服用は毎日になった。
27日の晩も69拍。
28日の昼が70拍。
29日の晩が69拍。
30日の晩も68拍。
とうとう10月に入った1日の昼も70拍。
その間のデータにもう一つの異常があった。
心拍数でなく血圧である。
認識した日は9月28日。
その日の昼に測った血圧は96-59。
異常に低い血圧データは2桁台。
えっ、である。
身体の内部に何かが動き始めた。
(H30. 9.26、30 記)
昨日の天気予報通りになった急降下気温は身体に堪える。
身体が震えているような感じも受けるが、それは心臓のドキドキ感。
昼食を摂った直後の心拍数は75拍。
昨日までなら徐々に冷めていくような感じだったが、この日は薬を要求するまでに陥った。
薬は昨年の11月に診察を受けた循環器内科医師の診立て。
処方された内服薬はワソラン錠。
120拍にも上昇したど頻脈状態に処方してもらった。
一時は入院手続きも終えて電極カテーテルアブレーション処置をすることになっていた。
予定していたが急激に落ち着いたが、本来ならば心房粗動アブレーション処置をしているところだった。
ところが処方されたワソラン錠を服用することで治まった。
入院・処置は消えた。
その後も少し上昇する日もあったが、服用すれば一日限りで治る。
医師からはご自身の判断で必要としたときに服用してくださいと云われていたが、その後は何事も起こらなくて今日に至っている。
3カ月検診においても異常値は認められない。
そういう状態が、突然に・・・。
いや、異常の予兆は一週間ほど前から訪れていた。
私は毎日の朝、昼、晩則後の処方箋を服用する。
そのときに必ず計測する血圧に心拍数。
値の変動は自身で確認しているから傾向も絶えず認知している。
その計測値を振り返ってみる。
心拍数が高めとする基準値はないが、身体の反応から68拍以上になった兆候日・時間を拾ってみる。
9月19日の昼は69拍。
20日の晩は76拍。
21日の晩は71拍。
22日の晩も70拍。
23日の昼は72拍で晩が69拍。
24日の昼は取材に出かけていたので計測はしていないが、晩は72拍。
この日の取材地は吉野町山口―大宇陀栗野―吉野町平尾巡り。
次の取材時間までは待機の休息。
無性に身体を休めたくなる日だった。
1カ所目は吉野町の三茶屋。
もう1カ所は大宇陀の道の駅。
ぐったりした身体を休めていた。
25日の晩は67拍。
そして本日26日の昼が75拍である。
これまでの最高値に達した。
危険水域と判断してワソラン錠を1錠飲む。
ドキドキ感は止まずに座る姿勢が苦になる。
横たわってひと眠りしたが、ドキドキ感に変化はない。
夕方5時にもう1錠を追加服用する。
少しはマシになった感があるが、難儀だったのが両足とも発症したこむら返り。
寝ているときや座しているときに発症しやすいこむら返り。
発症すればすぐに立ち上がる。
歩いたりして数分間。
立っておれば解消される。
この原因は気温である。
寒さが厳しくなったら足先の筋肉を刺激して収縮する。
手で揉んでコトを済ませることもしてきたが、最近は“立つ“ことで治している。
異常な寒さに足の筋肉縮小。
治すには温めるしかないと判断して、電子レンジでチンして温める温かい用具で足を包める。
また、部屋にずっと敷いていたホットカーペットも電源オン。
温かくなったら機嫌が治った。
19時、入浴する前に念のために計測した心拍数は67拍。
やや落ち着いてきた。
それは気分だけであり、症状に変化が見られない。
効き目が見られるのはいつ。
そう思って飲み続けるワソラン錠。
朝、昼、晩の服用は毎日になった。
27日の晩も69拍。
28日の昼が70拍。
29日の晩が69拍。
30日の晩も68拍。
とうとう10月に入った1日の昼も70拍。
その間のデータにもう一つの異常があった。
心拍数でなく血圧である。
認識した日は9月28日。
その日の昼に測った血圧は96-59。
異常に低い血圧データは2桁台。
えっ、である。
身体の内部に何かが動き始めた。
(H30. 9.26、30 記)