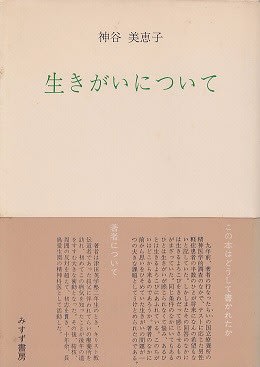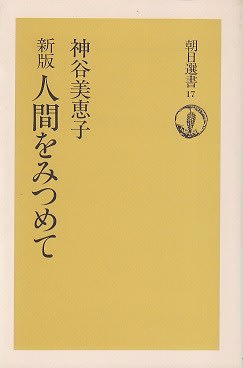最近、図書館から借りて読んだ本の中からの一冊。著者は、オックスフォード大学などの計算科学及び計算生物学の専門家。
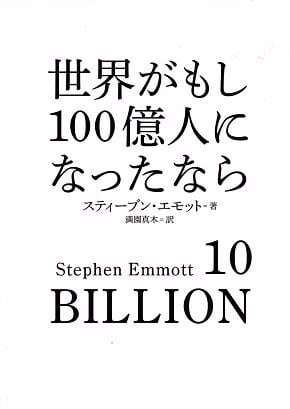
標題を見れば、大よその内容は察しが付く。が、正確な数字で危機に満ちた将来像を予測されると、やはり怖くなる。そして、それは今のままでは、ほぼ確実にやってくる。次の、あるいは次の次の世代が、確実に蒙らなければならない、破壊された環境に対する負担。それは「社会的コスト」ともいわれるが、これから生まれてくる子供達は、負の遺産を背負って生まれてくるようなものなのだ。なんとか、化石燃料や金属、さらには水などを異常に消費する文明を止める手だてを講じる必要があるが、現状では危機感があまりに乏しい。
わたしは、個人的には太陽光や風力などによる発電、つまり「再生可能エネルギー」を有効に拡大利用できる科学技術に一縷の望みがあると考えていた。しかし、この本によると、太陽光パネルや畜電池の製造に必要な金属・レアアースを採掘することは環境に対する負荷の方が大きく、太陽光パネルの製造に欠かせない三フッ化窒素は極めて強力な温室効果ガスだという。悲観せざるを得ない、と暗い気持にもなる本だが、多くに人に読んでもらい、共に未来の環境について考えたい。
「・・・今のままのペースで子どもが生まれ続ければ、今世紀末までに世界の人口は100億人になるどころではありません。
280億人になります。・・・
よほどの馬鹿でないかぎり、地球が支えられえる人口には限度があることは否定しないでしょう。問題は、それが70億(現在の人口)なのか100億なのか、280億なのか、ということです。もう限度を超えている、とわたしは思います。それも大きく超えていると。
今わたしたちが置かれた状況は変えられます。科学技術の力で切り抜けることはおそらく無理だとしても、わたしたちの行動を根本から変えることによって。
しかし、それが起こっている様子も、これから起ころうとしている様子もありません。わたしたちはこれからも、たぶん何も変わらないでしょう。・・・」
(本文P195~より抜粋)
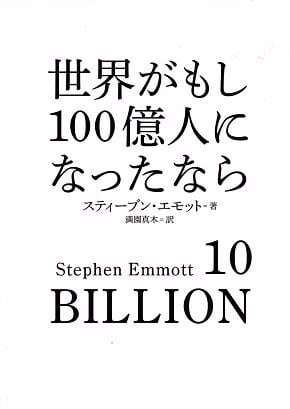
標題を見れば、大よその内容は察しが付く。が、正確な数字で危機に満ちた将来像を予測されると、やはり怖くなる。そして、それは今のままでは、ほぼ確実にやってくる。次の、あるいは次の次の世代が、確実に蒙らなければならない、破壊された環境に対する負担。それは「社会的コスト」ともいわれるが、これから生まれてくる子供達は、負の遺産を背負って生まれてくるようなものなのだ。なんとか、化石燃料や金属、さらには水などを異常に消費する文明を止める手だてを講じる必要があるが、現状では危機感があまりに乏しい。
わたしは、個人的には太陽光や風力などによる発電、つまり「再生可能エネルギー」を有効に拡大利用できる科学技術に一縷の望みがあると考えていた。しかし、この本によると、太陽光パネルや畜電池の製造に必要な金属・レアアースを採掘することは環境に対する負荷の方が大きく、太陽光パネルの製造に欠かせない三フッ化窒素は極めて強力な温室効果ガスだという。悲観せざるを得ない、と暗い気持にもなる本だが、多くに人に読んでもらい、共に未来の環境について考えたい。
「・・・今のままのペースで子どもが生まれ続ければ、今世紀末までに世界の人口は100億人になるどころではありません。
280億人になります。・・・
よほどの馬鹿でないかぎり、地球が支えられえる人口には限度があることは否定しないでしょう。問題は、それが70億(現在の人口)なのか100億なのか、280億なのか、ということです。もう限度を超えている、とわたしは思います。それも大きく超えていると。
今わたしたちが置かれた状況は変えられます。科学技術の力で切り抜けることはおそらく無理だとしても、わたしたちの行動を根本から変えることによって。
しかし、それが起こっている様子も、これから起ころうとしている様子もありません。わたしたちはこれからも、たぶん何も変わらないでしょう。・・・」
(本文P195~より抜粋)