ベランダのコブシが季節外れに花が咲きましたが、近所の植え込みに、
大きな紫陽花が一輪咲いていました。やはり何かちょっとおかしいのかも。
手元の会報に、“人工知能(AI)に小説は書けるか?”との設問に、面白いタッチ・
論調の投稿記事がありましたのでその一部を紹介しながら、私なりにも考察してみたいと
思いました。
記事の投稿者は、円城塔氏(作家、東大学術博士)で、その冒頭に『書けるのかと言わ
れれば、それは書けるに決まっており、書けないのかといえば、それは書けないに決まっ
ている。』と、いわゆる“張り手型”で、問題が提起されています。
『人間そっくりの情報処理を行う人工知能の中には、ある日、小説を書き出す奴だって
生まれるだろうに決まっていて、しかしここには、人間そっくりの人工知能が書く小説は、
小説そっくりに過ぎないのではないかという疑問が残る。』
条件が決まれば、ある程度の定型的なものは書けるし、それらを進化させれば品質も
上がって行く・・それは機械の独壇場だとしながら、
『果たして読者は、機械的に生み出された小説の中から小説として優れているものを見出
すことが出来るのだろうか。』 『機械に小説を書かせようとする人は、「ある作家の
全作品」を機械学習させたりしようとするようだ。』
 (ネット画像より)
(ネット画像より)
しかしこれだと、不意に新人作家が誕生する・・ということは起きない。 そこには、
機械に与えるべき要素があり、たとえばその作家が生涯に読んだ小説のすべてや、家族
との会話、知人との関係、近所の風景や旅行の思い出などなど、もっと多彩な要素がある
だろうとしており、ついでに、『機械に手足も付けて、胃も付ける・・』 『という考え
を進めていくと、小説を書くのに必要なのは、人工知能というよりは、人工人間という
ことになって行きそうである。』
『しかもその「人工作家」に創作の秘密を訊ねてみても、人間の作家が答えるような、
わかったような 分からないような内容になるに決まっている。なぜなら、そいつはただの
作家だからだ。』
しかし、最後に『だがしかし、人間とは違った知覚を備えた機械は、人間とは異なる
文芸を発達させうるのではないか。 鳥にカメラを付け、情景描写をする人工知能を載せ
るだけでも新しい表現は生まれるかもしれない。』
『この星に小説を書く生き物が人間一種しかいないのは、人間自身のせいであって、
他から生まれるかもしれなかった小説の可能性をつぶしてしまったのであり、自分たちと
は違う種の生み出す小説というものを人間はすっかり無視してきたのである。』
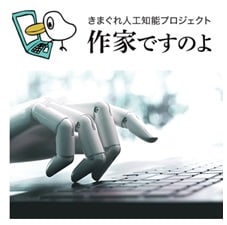 (ネット画像より)
(ネット画像より)
引用部分がずいぶん多くなりましたが、結局、AIには独創的な小説は書けないとの流れ
だと思います。
円城氏のいうAI構造は、膨大な事例がログとして蓄えられ、それらのデータを基として
記述された小説は、たとえば、日常の些細な経験も踏まえた中での創作を、とうてい書け
ないのではないかと言われていると思います。
しかし、AIには学習機能があり、従来の単なるログデータの組み合わせ(による創造も
含む)だけでなく、他の条件、例えば日常生活上の経験などの情報を多数インプットする
ことによって、従来のログ(データ)から学習による新しいデータが創造され、それらが
蓄積されたログを超越したデータとして無限に増殖して行くわけですから、ある程度の
時間はかかるかも知れませんが、我々が評価できる小説がいつの日かできるのではないか
とも思います。
出来上がった小説が、どのように評価されるかは、時代によっても違ってくるのでは
ないでしょうか。 もちろん、ミロのヴィーナスは、2000年の歳月を経てもなお美しい
ですが、美術の世界においてもその後の表現美は変遷していますし、音楽の分野でも歴史
の流れと共にそのスタイルが変わって行くように、文学の世界でも同じような変遷をたど
ることを考え併せれば、これから先、ロボット作家が現れても不思議ではないのかもしれ
ない・・と思うのです。

 今日はこの後すぐに蓼科農園に向かいます。 台風19号で、中央道・大月あた
今日はこの後すぐに蓼科農園に向かいます。 台風19号で、中央道・大月あた
りは通行止め、う回路もダメ、中央本線の電車も不通のため、東名から富士五湖回りで
中央道に入る・・そんな予定です。 今回は大収穫祭です。
人工知能AIが独自の言語を生み出す!
















