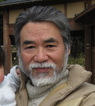金環日食を木もれ日で撮影しました。ひげ爺の蔭も映っています。
11ヶ月のお子さんの離乳食と発達の質問がありましたので渡辺眞史先生に回答をお願いいたしました。
素晴らしい回答をしていただきましたのでご紹介します。
*************
うちの子は11ヶ月ですが,(1)離乳食を全く食べません.完全母乳です.親の食べ物を取り分けても嫌がって全く口を開けてくれないのです.
義母は泣かせてでも食べさせなさいと言いますが,私は泣かせてでも食べさせるのは嫌だし,そのうち食べたくなる時期がくるかなと思って待っています.(2)1ヶ月早く生まれたせいか,運動の発達が遅れ気味です.寝返りはし,うつぶせでよく遊びますが,ハイハイはまだ前には進みません.おすわりは私からはさせていませんが,健診で医者がさせたら座っていました.ハイハイもそのうちするだろうと思ってみていますが,かかりつけ医はあと少し待ってハイハイしないようならば大きな病院へ相談へ行きなさいと言います.つかまり立ちはたぶんできません(させていません).(3)人見知りがひどいです.義母はお母さんべったりだからいけないと言うのですが,私は今はまだ気にしなくていいのではないかと思うのです.支援センターなどに行っても,他の子の発達を私が気になるし,子ども自身も楽しんでいるようには見えないので,抱っこしてお散歩したりして(ベビーカーはいやがるので)母子で楽しく過ごしています.
回答 たまごママネット医師団
赤ちゃんの発達は予定日からの修正月齢で考えます。また個人差が大きく、いわゆる標準と比べてその通りにならないことは普通のことです。
質問の赤ちゃんの発達は実際に見てみないと確かなことは言えませんが、質問の内容からは悪い印象はありません。寝返りが上手で自由に移動できるとハイハイが遅くなることがあります。
早い時期からうつ伏せ遊びをするとハイハイが早くなりますが、していないとゆっくりになることもあります。
一応の目安として、予定日から数えて1歳の頃までに自分でつかまり立ち、伝い歩きをしないときにはかかりつけの小児科に相談すると良いと思います。
できないから異常ではありませんが、私は経過観察の目安の一つにしています。
1歳前に人見知りの強い子はたくさんいます。
私はそれが当たり前と思っています。
早くから保育園に行った子や、家族が多かったり、人の出入りが多く大勢の人から抱っこやあやしてもらっている子は人見知りをしなくなります。
むしろこの時期はおかあさんとのつながりが大切な時期ですから人見知りをすることは必要なことですが、一つ注意することがあります。
赤ちゃんはお母さんの目を通して相手を見ます。
お母さんが心を許している相手には赤ちゃんも安心し人見知りが軽くなります。
周りからいろいろなことをいわれお母さんがストレスを感じ、周りに心を許せなくなっていると赤ちゃんも警戒し、人見知りがひどくなることがあります。このことだけ注意をしてください。
支援センターも行くことによりお母さんが同じ悩みを持ったお母さん達と話ができ、楽しくできるなら行ってもよいでしょう。しかし他の子どもと比べて、心配が増えるなら止めましょう。
お母さんが楽しい気持ちになれれば子どもも楽しんでいるように見えてきます。
離乳食も急ぐ必要はありません。母乳中心で栄養的に問題になることはありません。
離乳食は2歳ごろまでに完了することを目標にしますから、まだまだ時間があります。
しかし、そろそろ、なぜ食べないかを考える必要があります。
お母さんと同じ味を食べさせる、向かい合いではなく、抱っこをして自分も食べながら話しかけながら食べさせるなどをしてください。
母乳の赤ちゃんの場合、あまり柔らかいものより少し堅めのものを好むこともあります。
離乳食の時間の前は十分お腹が空くように、母乳を含めて何も口にしない時間を作る事で食べてくれる赤ちゃんもいます。
家族の食事の雰囲気はどうでしょうか。
お母さんが緊張するような雰囲気だと赤ちゃんも食事の時間を嫌がることがあります。
お父さんが一緒に食べるときには、お父さんの膝に座らせ、食べさせてもらうと、意外にたくさん食べることもあります。
同じぐらいか少し大きい子どものお母さんと話しながら(愚痴をこぼしながら)一緒に食べさせると食べることもあります。
離乳食を食べさせることに焦る必要はありませんが、お母さんが緊張していないか、楽しい雰囲気で食事の時間を過ごしているか、赤ちゃんの機嫌と睡眠はよいかなどに注意をしてゆっくり待ってあげてください。
渡辺眞史先生 山形県立中央病院小児科 2012.5.22
************
渡辺眞史先生の心のこもった回答を参考にしてください。
お母さんが焦らず、ゆったりとしていると赤ちゃんもそれに応えてくれます。
周りを気にせず、わが子をしっかり見ていきましょうね。
応援しています。