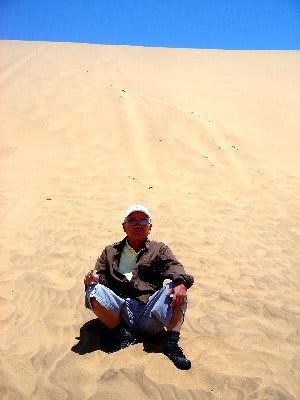4月27日(金)
例の黒川紀章さんがデザインしたと言う「新国立美術館」を
SG御夫妻と連れ立って見学に出掛けた。
外見 見た感じは なぜか「繭」を連想した。
またイサム・ノグチの提灯ランタンに非常に似ていると思った。
鉄骨とガラスのこのコンテンポラリーな建造物は時が経てば
ランドマークと呼ばれる建物に成り得るのだろうか?


建物内部に入ると天井まで吹き抜け。
外部からの日の光でスケールの大きな空間がど肝を抜く。
ただチョッと巨大な温室のような感じがしないでもない。
好意的に云えば「障子を通して入ってくる日の光」をイメージしたものか。
ガラスが汚れる事もあろうしクリーンナップは大変だな。

その明るい大空間と絵画展示室の間を区切っているのがこの回廊。
入場者はこの少し薄暗い回廊をゆっくり歩きながら
芸術鑑賞の心の準備が出来るのだろう。

館内3階には有名シェフがやっているレストランがある。
なにか御盆の上に乗っている様で不安定な感じ。
大変な人気で何時テーブルに有り付けるか全然目途も立たない。
諦めて近くの馴染みのイタリアン「ニノ」へ。
芸術鑑賞もまた次の機会に。

例の黒川紀章さんがデザインしたと言う「新国立美術館」を
SG御夫妻と連れ立って見学に出掛けた。
外見 見た感じは なぜか「繭」を連想した。
またイサム・ノグチの提灯ランタンに非常に似ていると思った。
鉄骨とガラスのこのコンテンポラリーな建造物は時が経てば
ランドマークと呼ばれる建物に成り得るのだろうか?


建物内部に入ると天井まで吹き抜け。
外部からの日の光でスケールの大きな空間がど肝を抜く。
ただチョッと巨大な温室のような感じがしないでもない。
好意的に云えば「障子を通して入ってくる日の光」をイメージしたものか。
ガラスが汚れる事もあろうしクリーンナップは大変だな。

その明るい大空間と絵画展示室の間を区切っているのがこの回廊。
入場者はこの少し薄暗い回廊をゆっくり歩きながら
芸術鑑賞の心の準備が出来るのだろう。

館内3階には有名シェフがやっているレストランがある。
なにか御盆の上に乗っている様で不安定な感じ。
大変な人気で何時テーブルに有り付けるか全然目途も立たない。
諦めて近くの馴染みのイタリアン「ニノ」へ。
芸術鑑賞もまた次の機会に。