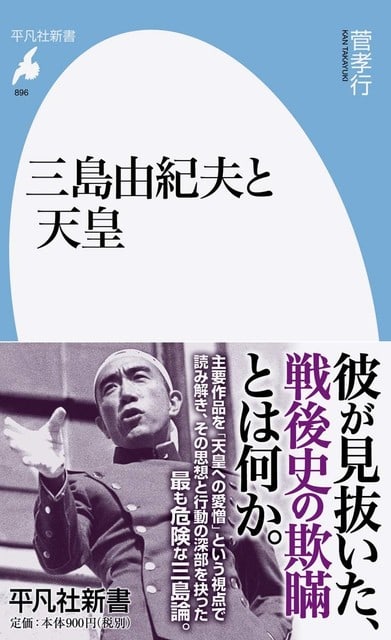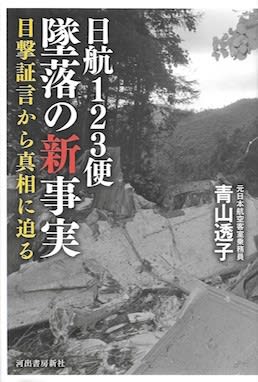『帝国日本の「開発」と植民地台湾~台湾の嘉南大圳と日月潭発電所』(清水美里 著 有志社 2015年)を読む。
著者の清水美里(みさと)さんは、共立女子大国際文化学部卒業後、東京外国語大学大学院地域文化研究科博士後期課程修了、博士(学術)号を取得している。本書は、博士論文をもとにまとめられた。
本書の帯文には、「開発」の視点から帝国日本と植民地台湾の関係を再考すると書かれていて、嘉南大圳(かなんたいしゅう)および日月潭(にちげつたん)における台湾総督府の「開発」が台湾社会にもたらした社会変動を分析している。
「あとがき」には著者がこのようなテーマに関心を持つに至った動機として、故郷である神奈川県相模湖町(現・相模原市緑区)の相模ダム建設にかかる出来事について記している。大学の卒業論文のテーマは「戦時期の相模ダム建設における中国人捕虜の強制労働について」だったという。高尾山近くに住んだこともある私にとって、相模湖は親しみのある場所だったが、中国人捕虜の強制労働があったとは、全く知らなかった。著者は「小・中学生時、教室からこのダム湖を眺めながら過ごし、大学では中国文化専攻だった私にとって、それはのどに詰まった小骨のような発話すると痛みが走るテーマだった」と記す。
このような原体験があったからこそ、著者は台湾総督府による台湾の「開発」に目を向けたに違いない。
全体的なブックレビューにならないことを承知で書くが、私が最も興味深く読んだのは「補論 八田與一物語の形成とその政治性~日台交流の現場からの視点」(本書p.234~284)だった。
杉原千畝やシンドラーにしても、実像と「物語」の乖離が著しいことは知られていた。杉原千畝に関しては、外務省OBの評論家・馬渕睦夫が「杉原は外務省の方針に従って行動したに過ぎない」として、その「論功」を否定している。
八田與一については、本来、台湾総督府の業績であるべきものが、大日本帝国の敗北ゆえに、八田本人の偉業に変換されなければならなかった。
また、八田與一のエピソードについて、日本と台湾ではかなりの差異が見られるという。たとえば台湾側は、敗戦直後、八田を追って烏山頭ダムに投身自殺した妻・外代樹の物語にシンパシーを寄せる傾向が強いというように。
政治的には「八田與一物語」は、中共(中国共産党)の圧力により疎遠になりがちだった日台関係を結びつける絆となった。その内実、プロセスを分析してみせた本論文の意義は大きい。
共立学園の八王子校舎(中・高部)に通った親族を持つ私としては、あの大学から、このようなテーマで学術論文をものにする研究者が現れるとは夢にも思わなかった。相模湖、高尾の山々そして「台湾」。こんな結びつきに心が躍った。また、著者は「あとがき」で佐藤公彦先生に謝意を表している。7年ほど前、私はこの佐藤公彦教授(当時=東京外国語大学教授 現在=同大名誉教授 中国近代史)の授業(東アジア国際関係史、近代中国とキリスト教、及び現代世界論Ⅰ)を聴講し、その熱意に圧倒された。著者は佐藤先生の弟子だったのかと、改めて親近感を覚えた。