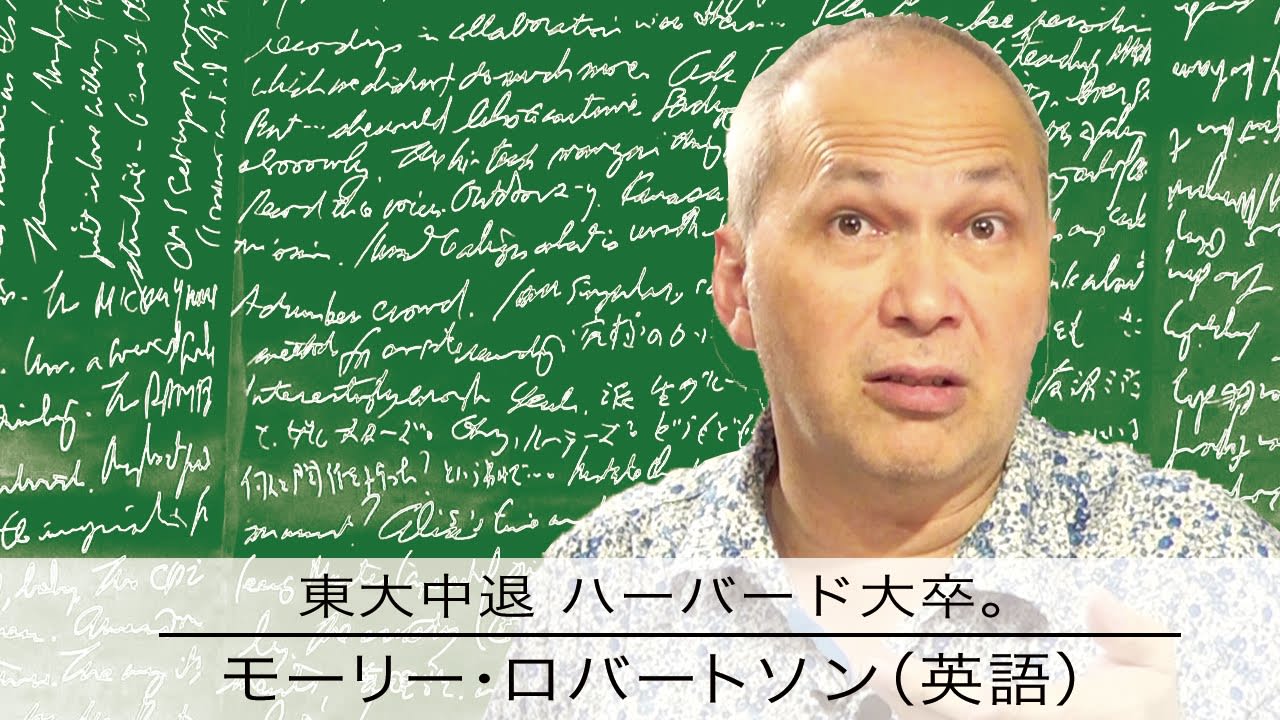映画「沖縄 うりずんの雨」を観る。週日の昼間、「岩波ホール」はインテリ風(?)のジジババばかりで、若者は一人もいない。
私がこの映画を見ることになったのは、いま聴講している授業で、この映画のレポートを書く課題が出たから。でなければ、はるばる(畏れ多い?)「岩波ホール」に足を運ぶこともなかっただろう。
折しも百田尚樹氏の発言が「朝日」「毎日」などに袋叩きにされ、「沖縄の心」を踏みにじる発言は許せない、という風潮が作り出されている。「沖縄」に心を寄せ、「戦争ができる国」に反対する「市民」が、これらの新聞のよき読者であり、この映画を見る人なのだろうか。
けれども、私はこの映画を見て、全く別の感慨を抱いた。冒頭の沖縄本島を空から俯瞰する映像を見てすぐに感じるのは、沖縄戦は「逃げ場のない」戦いだったということだ。兵士、島民ともども、一蓮托生の戦いだった。
1945年4月に始まった沖縄戦は6月には壊滅的敗北で終わる。この間、沖縄島民は「日本と天皇を信じて戦った」(太田昌秀)のだった。沖縄戦が終わったあと、米軍の本土爆撃はさらに苛烈を極め、8月には広島、長崎への原爆投下、そして敗戦に至る。この期間だけでも、100万人近い日本人が犠牲になったはずだ。
日米戦争を回避できず、「一億玉砕」に至るまで戦争を収束できなかった、その責任はいったい誰にあるのか?木戸幸一の日記(木戸日記)には「東京裁判の判決後、天皇陛下は自発的に退位されるであろう」 と記されていた。しかし木戸の予測に反して、戦争責任を問われる心配がなくなったあとでも、昭和天皇は自発的に退位などしなかった。累々たる屍の上に築かれたわが身の安泰!これはだれも責任をとらない、「曖昧な日本」そのものの姿ではないのか。
だからと言って、天皇の戦争責任を問い詰める側に政治権力がわたっていたら、「曖昧な日本」が変わっていたかと言うと、そうとも思えない。福島原発事故の危機のさなか、日本政府(民主党政権)は徹底した情報統制を行った。菅直人首相は、福島原発に”話し合う”ために乗り込み、枝野幹事長は「現時点では何の問題もない」と繰り返すだけ。その一方でNHKなどで放送されていた各国の海外ニュースをすべて遮断した。ZDF(ドイツ)は早くから福島原発の速報を伝えていたので、ドイツの友人は私に「福島原発はメルトダウンしているから早く逃げて!」というメールを送ってきた。3月15日前後の危機の一週間、国民は「原発はメルトダウンしていない」と信じ込まされ、放射性物質が降り注ぐなか、会社や学校でいつもの日常生活を強要された。あのとき、われわれはこの国が「逃げ場のない、一蓮托生の国」であることを実感させられた。まるで操り人形のようなこの国の「民草」…。沖縄と本土が私の中で初めて一体化したときだった。
この映画を作ったジャン・ユンカーマン監督は、どうみても完璧な市民派左翼。その目線で沖縄を映し出すと「岩波」御用達のこのような映画が出来上がるのだろうけれど、そこには決して触れられないことがある。日本の安全保障はどうあるべきか、という政策論、未来像だ。
米国が世界戦略として、沖縄に基地を置くのは理解できる。だが、米国が未来永劫、東アジアに関心を持ち続けることなどありえず、そのような他国に身を委ねてしまうリスクを考えないのは極めて無責任な話だ。米軍を追い出し「基地のない平和の島・沖縄」が実現したとしても、沖縄群島の安全保障は誰が担うというのか?そういう肝心の議論は素通りしてしまうこの映画の中にも、自己欺瞞的な無責任、言葉だけのきれいごとが息づいているとしか思えない。いや、これはプロパガンダ映画だよ、と言ってしまえば、それまでだが…。