今から63年前の今日、台湾で起きた「二二八事件」。台湾の知識人・指導者層二万八千人が、大陸から敗走してきた中国国民東軍に虐殺された事件だ。
われわれ日本人には、あまり馴染みがない出来事だが、実は現在多くの台湾人が抱く「親日感情」と無縁ではない。
映画「台湾人生」(酒井充子監督)の中でも、この「二二八事件」を詳しく説明している。陳清香さん(女性)は「蒋介石は大陸から自分の名前さえ書けないごろつきを連れてきた。そういう連中が警察署長になったりしていた」と語る。蕭錦文さんは、実際に虐殺現場を目撃した。
台湾では、民主進歩党を中心にこの事件を忘れないようにと追悼行事を続けているようだ。
台湾人虐殺事件 独立派史跡巡る 「2・28」追悼行事
2010年2月28日 朝刊
|
27日、台北市内で行われた「2・28事件」追悼行事で、事件の関連史跡を巡る民進党の蔡英文主席(右)=栗田秀之撮影 |
 |
【台北=栗田秀之】中国から台湾に渡った国民党政権が多数の台湾人を虐殺した一九四七年の「二・二八事件」から六十三年を前に台湾の本土・独立派団体は二十七日、事件への理解をより深めようと、台北市内に点在する事件関連史跡を巡る追悼行事を行った。
二〇〇八年に民進党から国民党に政権が代わり、犠牲者の遺族を中心に事件の風化を危ぶむ声が強まっており「音楽会など例年の行事では事件の意義が伝わりにくい」(主催者)として、歴史資産を通して台湾戦後史最大の悲劇とされる事件の記憶を刻むことにした。
主催者発表で約千人が、事件の発端となった闇たばこ取り締まりをめぐる市民殺傷事件の現場など、五カ所を回った。野党民進党の蔡英文主席も駆け付け「台湾の民主と自由は多くの犠牲の上で成り立っていることを感じてほしい」と訴えた。
記?片-《台灣的?史──在光復初期二二八事件》4










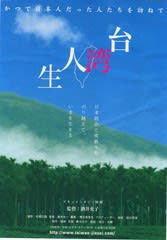 (映画「台湾人生」のチラシ)
(映画「台湾人生」のチラシ) (2009年7月4日、映画上映後の酒井充子監督と蕭錦文氏 東京にて)
(2009年7月4日、映画上映後の酒井充子監督と蕭錦文氏 東京にて)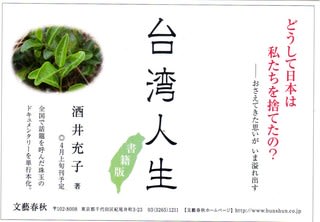 (書籍版「台湾人生」 文藝春秋社)
(書籍版「台湾人生」 文藝春秋社) (アンプがネコの座布団代わり?)
(アンプがネコの座布団代わり?)