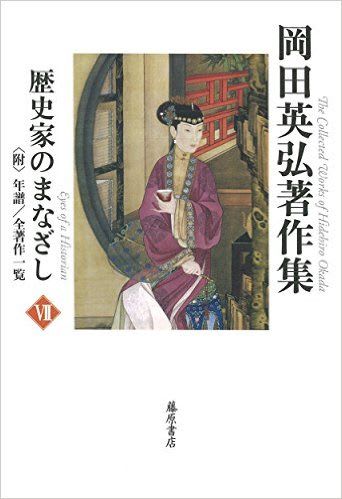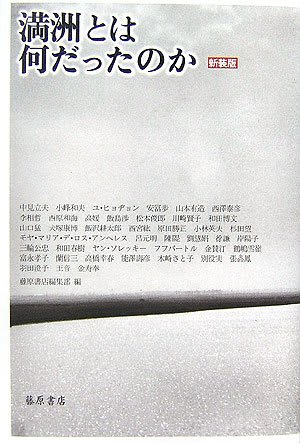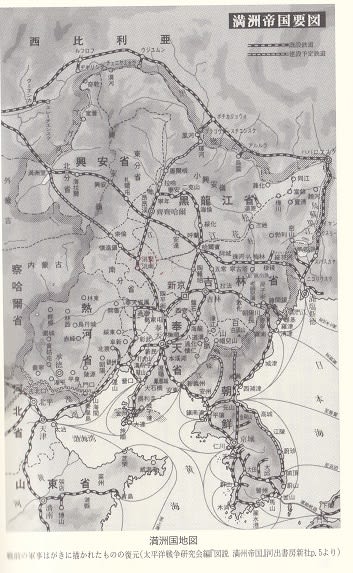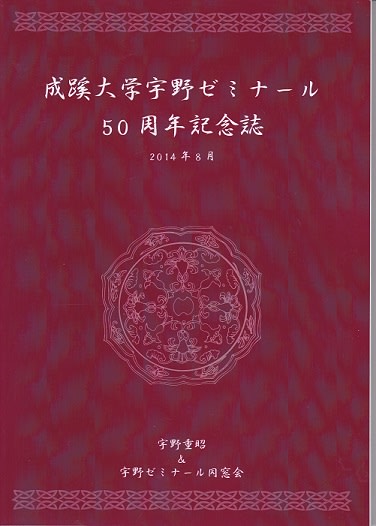「日本統治時代の台湾~写真とエピソードで綴る 1895-1945」(陳柔縉 著 PHP研究所 2014年)を読む。本書の原題は「人人身上都是一個時代」、2009年に台湾で刊行された。

本書の原題は「人人身上都是一個時代」。日本統治時代の50年間、台湾には人々の普通の生活があったことを教えてくれる好著だ。1964年生まれの著者は、「日本語世代」の台湾人古老から聞き取りを進めるとともに、日本統治時代の新聞や雑誌を調べて、数々のエピソードを紹介する。
その手法は、イデオロギー的な見方、すなわち植民地統治を断罪するのではなく、あくまで普通の人々の暮らしや意識を採り上げる。
例えば、ヤマハピアノは台湾統治の初期から台湾で販売され、1920年代には多くの学生がピアノを弾いていた。また、日本統治時代の台湾においても、大陸から多くの出稼ぎ労働者が来ていて、双十節には中華民国国旗が掲揚されたという。他にも、数々のエピソードが盛り込まれている。そのどれもが、日本統治時代は、台湾の人々にとって、特別ではない普通の時代だったことを示している。はっきり言うならば、日本が去った後の蒋介石時代よりずっといい時代だったのである。台湾社会の近代化は、日本統治時代に進められた。交通、医療、産業、教育、行政制度など、日本統治時代に成し遂げられた社会インフラは、中国大陸よりはるかに進んでいた。これは朝鮮半島についても言えることなのに、「植民地支配」断罪が声高に叫ばれる中で、日本人自身が近代化遂行者としての誇りを忘れてしまったのだ。
現在の台湾が「親日」と言われる理由もよくわかる好著だ。
著者のインタビュー記事を以下に転載させていただく。

日本と台湾が最も密接な関わりを持った日本統治時代。当時の台湾の人々からすれば異民族による統治は決して歓迎すべきことではなかっただろう。だが、どのような時代であっても人々は着実に自らの生活を営んでいた。そこには人間臭くも豊かなエピソードがあまた埋もれている。陳柔縉〔ちんじゅうしん〕『日本統治時代の台湾──写真とエピソードで綴る1895~1945』(天野健太郎訳、PHP研究所)はそうした一つ一つを丁寧に掘り起こしてくれる。 「歴史名探偵」とも言うべき旺盛な好奇心としなやかな行動力を兼ね備えた著者の陳柔縉さん。台湾人の立場から日本統治時代をどのように捉えているのか、お話をうかがった。
(1)なぜ日本統治時代に興味を持ったのか?
もっと台湾(以下、も):日本統治時代に関心を持つようになったきっかけは何ですか?
陳柔縉(以下、陳):私は以前、政治記者をしていました。特に政商関係をテーマとしていたのですが、政財界のキーパーソンたちの家族関係を調べ、インタビューしていると、必ず日本統治時代の話題が出てくるんです。どうしても避けられないテーマなんですね。
戦争中の日本についてはマイナスのイメージが強かったんです。ところが、インタビューをしていくと、日本統治時代は良かった、と語る人が多いんですよ。李登輝・元総統も「自分はかつて日本人だった」と語っていましたね。私自身の祖父にも「日本人と中国人、選べるとしたらどっちが良い?」とたずねてみたら、「もちろん、日本人だよ!」と返ってきました。ある高齢の大学教授はこんなたとえ話をしていましたよ。「日本統治時代の台湾はお嬢様。ところが、中国人がやって来て、そのお嬢様が無理やりヤクザと結婚させられてしまった感じ」(笑) 聞けば聞くほど、私自身が学校教育で習った歴史とは全然違う。祖父の世代は一体どんな体験をしたんだろう? どうして歴史の見方がこんなに分裂してしまっているんだろう? 真相を知りたいと思いました。
台湾が民主化される以前の歴史教育では、中国史を台湾へ接ぎ木するように持ってきただけで、1945年以前の台湾についてはほとんど無視されていました。日本統治時代についてのキーワードは皇民化、植民地統治、経済的圧迫…こういったステレオタイプだけで、その他のことは一切触れられません。この空白の時代はいったいどんな状況だったんだろう? 自分の住んでいる土地に根差した視点が欲しかったんです。
も:陳さんのご著書を拝読いたしますと、日常的に見慣れたものの由来とか、過去にあった意外な出来事とか、そういったエピソードを一つ一つ紹介していく語り口がとても面白いです。言い換えると、事実の積み重ねを通して、「上から目線」ではない見方で歴史を描こうとしていると理解してもいいでしょうか?
陳:そうですね。この本の原題『人人身上都是一個時代(一人一人に刻まれた時代)』の通り、一人一人が自分の歴史を持っていますし、また歴史を見るにしても一人一人が自分の歴史観を持つのは当然のことです。しかし、以前の台湾の学校教育では歴史の見方を押し付けられてきました。そうしたことへの反発から、何事も疑いをもって見るようになりましたね。私自身が学生の頃、法律を勉強したことも関係しています。自分自身で証拠を集めて、真相は何であったのかを調べる。総合的な判断によって自分自身の歴史の見方を組み立てていくことが大切だと思います。
も:日本統治時代について調べる際にはどのような資料が役立ちましたか?
陳:当時を体験した方々からうかがったお話が貴重な資料となります。そういったお話を記録しておくのも大切な仕事です。
も:当時を知る方々もすでに相当なご高齢ですが、焦りはありませんか?
陳:戦後も60年以上たってしまうと、ご存命の方々が覚えていることも日本統治時代後半の時期に偏ってしまいますね。台湾で生活面の発展が著しかった1920年代について語れる方はもうほとんどいません。焦ったところで、諦めるしかありません。自分でこの仕事をしながら、そうした限界は感じています。もっと前の時代を調べるには史料に頼るしかありません。例えば、『台湾日日新報』1 などは時代的に網羅されていますし、生活面の情報もたくさんあって役立ちます。
『日本統治時代の台湾』著者・陳柔縉さんに聞く #2
投稿日 : 2014年9月19日 | カテゴリー : Interview
(2)ディテールから当時の生活実感に迫る
も:『日本統治時代の台湾』の内容についてお話をうかがいます。タバコ工場の女子工員たちの意識調査が紹介されていますね。アンケート結果を見ているとなかなか面白いのですが、「つらいこと」として「中国語の勉強」を挙げている人がいます。これはどういうことなのでしょうか?
陳:ここでいう中国語とは、古典の中国語、日本で言う漢文のことです。このアンケートは戦争が始まる前に実施されたものですが、当時はまだ日本語が全面的に強制されていたわけではありません。例えば、『台湾日日新報』にも当時は漢文版があって、漢文が日本語と併用されていました。会社内のサークル活動で漢文を勉強するものもあったようです。普段は台湾語をしゃべり、日本語を勉強し、さらに漢文の勉強もしないといけない。サークル活動ですから任意なんでしょうけど、女の子たちの感覚からすれば、「やっぱり苦手だな、古臭くて役に立ちそうもないし、面倒くさいし…」。
も:そこは日本人の若者と同じ感覚だったかもしれません(笑)。若者の感覚という点では第2章「モダニズム事件簿」で色恋沙汰をめぐる騒動が取り上げられていますね。日本でも20世紀初頭は、古い道徳観から開放的な考え方への移行期で、こうした背景は台湾とも共通すると思います。ところで、「男女関係の乱れ」について、当時の日本では西洋化の悪影響と考える人がいましたが、台湾では日本の悪影響とみなされていたのが興味深いです。
陳:台湾での西洋化のプロセスは日本からもたらされたものですから、当時の台湾人が日本の悪影響と考えたのは当然でしょうね。日本で明治維新が起こったのは1868年、台湾を領有したのは1895年、だいたい30年のズレがあります。台湾の西洋化もやはり30年ズレると考えていいでしょう。
戦後の私たちの世代では、恋愛問題で自殺するなんて事件はあまりありませんでした。ですから、この当時、どうしてこんなに心中事件があったのか不思議な感じもします。古い道徳観の時代には恋のために死ぬなんて発想が最初からあり得ない。現代は誰を好きになろうが全く自由で、反対されることなんてないし、反対されたとしても勝手にすればいい。やはり、過渡期の現象なんでしょうね。
も:台湾で暮らしていますと、旧暦(太陰暦。台湾では農暦という)が今でも日常生活の中に根強く残っているのを実感します。対して日本は明治時代以降、太陽暦で完全に一本化してしまいました。例えば、お正月といえば、日本では1月1日ですが、台湾では春節です。日本統治時代にも旧暦はしぶとく生き残ったんですね。
陳:日本統治時代は約50年間にわたりますが、その影響が生活の隅々にまで浸透してしまうほど長かったわけではありません。例えば、家事を切り盛りしている普通のお母さんたちは学校へ行く必要もなく、昔ながらの生活習慣をそのまま続けていました。その子供たちが学校へ通ったり仕事へ行ったりしても、家へ帰れば昔ながらの生活習慣が待っているわけです。日本のお役人もそこまでは干渉できません。政府の権力が家庭の中まで及ばない時期が意外と長かったんですね。日本人社会の側でも旧暦など台湾の伝統的な慣習をむしろ面白がって受け止める雰囲気があって、新聞記事でもよく取り上げられていました。
も:「味の素」が当時の台湾でも大流行だったそうですが、人気があるだけニセモノにも悩まされたというあたり、商売人のずる賢さを感じさせます。
陳:中身を入れ替えた悪質なニセモノもありましたし、パッケージ・デザインやネーミングを似せたり、色々なケースがありました。戦後の台湾でも、「味王」「味丹」「味全」といったメーカーがありますが、こうした社名はやはり「味の素」を意識していると思います。日本ブランドのイメージをパクって売り込みに利用しようという発想もありました。例えば、蚊取スプレーを作っている「必安住」という台湾企業がありますが、これはかつて日本で有名だった「安住の蚊取線香」(安住伊三郎[1867-1949]が創業、空襲で工場が焼失して廃業)から名前を取っています。
も:「味の素」が台湾での市場調査をもとに大陸へ進出したというのは初めて知りました。
陳:日本人から見れば、台湾は漢人が住む地域ということになりますからね。戦後になっても、日本企業が海外展開を図るとき、まず一番近い隣国である台湾への進出から始めるというケースは多かったですよ。この場合は日本企業が台湾を選んだというよりも、台湾人の企業家が誘致した可能性もあります。日本統治時代に育った人は日本語ができますから、言語の壁がないのでやりやすかったのだと思います。
も:本書にも登場する台南のハヤシ百貨店が今年の6月、再オープンしました。台湾各地で日本統治時代の建物を修復・復原して観光名所としているのをよく見かけますが、どんな背景があるとお考えになりますか?
陳:両蒋(蒋介石と蒋経国)時代の国民党政権にとって台湾は大陸へ戻るまで一時的に滞在する場所に過ぎませんでした。ですから、わざわざ新しいものを建設しようという発想がなく、日本統治時代の建物で使えるものは使おうと考えたわけです。壊すのもお金がかかりますしね。彼らは保存しようと考えたわけではなく、単に放っておいただけですよ。
1988年に李登輝が総統に就任して以降、台湾では「本土化」の気運が高まります。台湾人自身の歴史を見直そうという発想から、古いものを保存しなければいけないと考えるようになりました。現存する古い建物というと、ほとんどが日本統治時代のもので、それ以前のものは寺廟くらいです。今の台湾人にとっては、ずっとそこにあって見慣れたもの。日本統治時代が良いとか悪いとか、特にそういった意識はありませんね。
も:当時の建物が保存されているのを見ると、日本人としては何となく嬉しくなりますが、現地の台湾人とは受け止め方にズレもありそうです。
陳:日本人が残した建物は頑丈だし、きれいだし、レベルが非常に高いです。私が卒業した高校の校舎も日本統治時代のものでしたが、てっきり国民政府が作ってくれたものだとばかり思いこんでいました。そういうことは学校で教えてくれませんでしたから。戦後、国民政府が建てた建物はあんまり良くなくて、こっちの方が先に壊されたりしました(笑)。
投稿日 : 2014年9月20日 | カテゴリー : Interview
(3)台湾人が日本に残した足跡
も:台湾が日本の植民地だった時代、多くの台湾人が日本へやって来ました。彼らが日本に残した足跡についてうかがいたいと思います。日清戦争の結果、日本が台湾を領有したのは1895年のことです。翌年の1896年、李春生〔りしゅんせい〕1が東京へ来ました。彼が見た東京の印象はどんな感じだったのでしょうか?
陳:彼は日本での見聞をもとにした旅行記を『台湾新報』(後の『台湾日日新報』)に掲載しています。上野の動物園や博物館、それから国会、見るものすべてが新鮮だったようです。当時の台湾は農村社会で、これといったものは何もありませんでしたから、カルチャーショックは相当に大きかったはずです。
も:明治日本は西洋文明との落差を痛感して急速な西洋化を進めていましたが、李春生も東京で西洋的な文物を目の当たりにして、同じような切迫感を抱いたわけですね。
陳:西洋化を目指していたのは日本だけではありません。清朝を倒した中国の革命家たちも東京へ留学して近代的な知識を学ぼうとしていたでしょう。大きな時代の流れの中で捉える必要があります。
も:東京駅の前で、林献堂〔りんけんどう〕2 をはじめ台湾議会設置請願運動の人々が記念撮影した写真がありますね。この運動にはどのような意義があったのでしょうか?
陳:当時、台湾総督府は独裁的な権力を握っていましたから、台湾人には民主的な制度が欲しいという気持ちがありました。清代にはそんな発想すらありません。日本統治時代に入ってから民主主義への要求も芽生え始めたと言えます。日本の大正デモクラシーが台湾へ波及したという側面もあるかもしれませんが、それだけではありません。やはり台湾総督府は言うことを聞いてくれない。ですから、もっと上の人たち、つまり東京という政治的中枢へ直接訴えかけないといけいない。台湾人の民族性は穏やかですから、テロとか過激な手段は好みません。あくまでも合法的に運動を展開しようとしました。
台湾議会設置請願運動は実質的には東京の留学生が担っていました。林献堂のような有名人はその上に乗っかっている感じです。
も:東京にいた留学生はどんな人たちでしたか?
陳:多くの場合、やはり裕福な家庭の子弟ですね。東京で苦学した楊逵〔ようき〕(1906-1985、『新聞配達夫』で日本の文壇に登場したプロレタリア作家)のような人はむしろ例外的です。
台湾人女性の留学生もいました。例えば、女医ですね。台湾総督府医学校は女性の入学を許可していませんでしたので、台湾で最初の女医さんは東京女子医学専門学校(現在の東京女子医科大学)の出身です。ここを出た眼科の女医さんに会ったことがあります。怒ったところを誰も見たことがないほど本当に優しいおばあちゃんです。日本の洗練された教育を受けたんだなと感じました。私も年取ったらこうなりたい。もう理想のおばあちゃんです!
も:本書には林献堂が林熊徴〔りんゆうちょう〕 (1889-1946、台湾五大名家の一つ・板橋林家の当主) に招かれて、東京の旅館「松泉閣」で裸踊りを見たという話が出てきます。
陳:裸踊りとはいっても、女性のストリップとか、そういうのではありません。男性がお腹に顔を描いて踊るという…。
も:ああ、日本の酒宴で盛り上がると、そうやって場を盛り上げる人がいましたね。しかし、林献堂といえば台湾民族運動のリーダーとして台湾総督府から睨まれる存在、林熊徴といえば逆に台湾総督府と利権的なつながりの深い「御用紳士」、お互いに敵対し合っているイメージがあります。そういう二人が一緒にお酒を飲んでいたというのが面白いです。
陳:はい、やはり色々なつながりはあったわけです。実際の歴史は複雑で、単純に黒白つけられるものではありません。安易に貼られたレッテルは剥ぎ取っていく必要があります。
も:本書には芸術を志した留学生も登場します。彼らは東京でどのようなことを学び、その後の台湾にどのような影響をもたらしたと考えられますか?
陳:うーん、芸術というのは影響関係が客観的に見えるものではありませんから、難しい問題ですね。例えば、音楽家の呂泉生〔ろせんせい〕(1916-2008)のようにたくさんの生徒を教えたのならともかく、油絵の陳澄波〔ちんちょうは〕(1895-1947)は二二八事件で命を落としてしまいましたし、日本画の陳進〔ちんしん〕(1907-1998)の場合にはそもそも日本画というジャンルがなくなってしまいましたし…。戦後は存分に能力を発揮できる舞台がなかなかありませんでした。
芸術に限らず、様々な分野の留学生が東京に来ていました。彼らの影響をはっきりと見て取るのは難しいですが、少なくとも中堅層として台湾社会を支え、台湾が発展する力となったことは確かだと思います。
中国人留学生の東京体験について書かれた本はたくさんありますね。魯迅一人だけでも結構あります。しかし、台湾人留学生についてはあまりありません。日本と台湾の交流はこんなに密接なのに、なぜでしょうね。もっと調べる必要があると思います。
質問に答えながら不明瞭な部分に行き当たると「ああ、今すぐ図書館へ調べに行きたい!」と身悶えしていた陳柔縉さん。「優秀な若い研究者が活躍し始めているから、私の出番はもうありません」などと謙遜されていたが、いやいや、ヴァイタリティーあふれる行動力は健在である。次は日本統治時代の広告からうかがえるマーケティングについて新刊を準備中だという。当時の時代相をどのように浮かび上がらせてくれるのか、楽しみである。
(了)