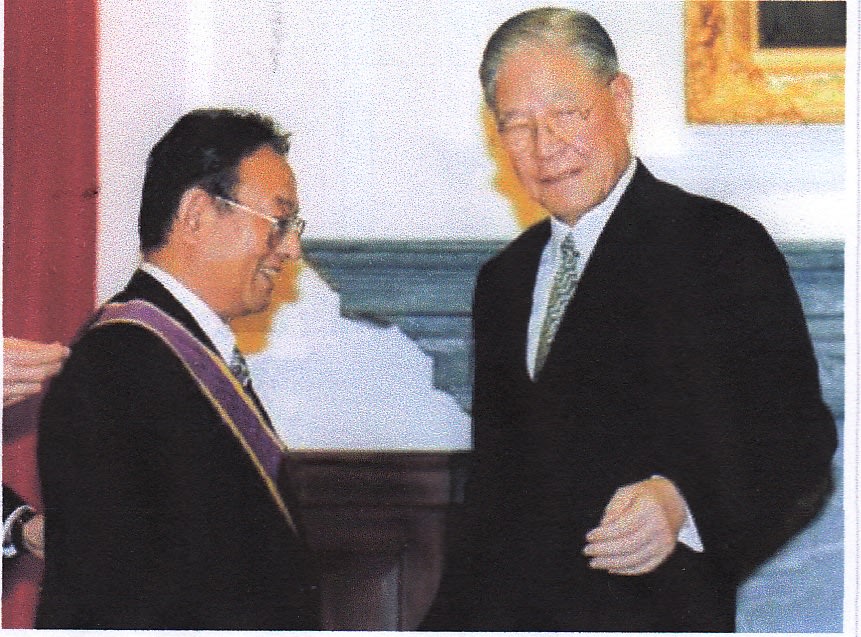「日中友好」の美談として描かれた番組だったので、これを見たほとんどの人は「感動」したのだろうが、私はあえて次のような疑問を呈した。
① 江沢民がわざわざ内モンゴルに会いに行き遠山正瑛にお礼を言ったというエピソードや「中国で生前銅像が建てられたのは毛沢東と遠山先生だけ」というナレーションは、遠山の「偉業」を賞賛しているというよりも、かえって遠山正瑛という人物の俗物性を疑わせる結果となっている。
② 番組では内モンゴルの砂漠化が、漢人農民の移住という人為的原因で引き起こされているという事実には一切言及がない。
③ 遠山正瑛の「砂漠の緑化」が、漢人農民の入植を助け、モンゴル人遊牧民の居住範囲を狭める結果となっている。遠山の「善意」が漢民族による少数民族支配の強化に好都合だからこそ、江沢民はわざわざ謝意を示したのではないのか。
①については、遠山正瑛の長男・遠山柾雄が、父親と同じ鳥取大学農学部準教授として「砂漠の緑化」に取り組んでいたが、政府からの補助金を不正受給したのはないかと指摘されている。この遠山柾雄は、父親が教授をしている鳥取大学に入学し、父親の研究室で乾燥地農業を学び、父親のポストを引き継いでいる。国立大学でこんな人事があるなどとは信じられない話だが、その彼が砂漠緑化事業のための政府補助金から使途不明金を出したのだとすれば、「内モンゴル砂漠緑化事業」の理念さえ疑われかねない、驚くべきスキャンダルである。
②と③については、「Southern Mongolian」に詳しく論じられているので、下記に引用させていただいた。主要な指摘は、次のようなものだ。
「日本人研究者の研究成果は悪用される恐れがあり、研究は民族文化の保護と維持を意識しなければならない。日本人による沙漠研究は、緑化も目的のひとつであるようだ。ただし、沙漠地域での緑化はすなわち農産物の栽培をどのように促進するなど、緑化=農耕開墾を意味しているような印象が強い。というのは、いかに灌漑すれば作物が生長し、何本の木を植えれば防風林となって農耕地が保護できるか、という実験が多いのではなかろうか。沙漠化を防止するためには、農耕を中止し、定住から再度移動放牧に回帰しなければならない、という発想は毛頭ないのではないか。」
「中華人民共和国が積極的に漢族農民の入植をすすめた結果、オルドス地域をはじめ、内モンゴル各地に無数の漢人村落が形成された。漢族はどこへ移動しても農業中心の生活を営む。乾燥地域での営農は環境を破壊しただけでなく、異なる生活を送ってきたモンゴル族とのあいだで、衝突も増えるようになった。」
「現地住民は日本からの「緑の使者」を歓迎し、大きな期待を抱いている。しかし、牧草地が植林地化される現状への懐疑も隠せない。地下水が比較的豊富な牧草地での植林は、活着がよいため補助金の報告書は書きやすい。また、植林団体の誤解も少なからずある。牧民の家畜が植林地に入り込むことが植林事業実施の障害となるとしたり、強く「禁牧」(家畜の放牧を禁止し、宿舎飼育を奨励する)を訴える団体さえある。」
「砂漠化」の真の原因はどこにあるのか?砂漠を緑化することによって、その人間社会はどう変化するのか。こういった洞察を抜きにして、「地球環境の保護」「日中友好」などと安易に囃し立ててほしくないものだ。
「美談」仕立ての「感動番組」にはくれぐれもご注意を! この番組の感想は、そういう結論になりそうだ。
モンゴル人からみた沙漠化
-日本の緑化運動とも関連づけて-
楊 海英(やん はいいん)
静岡大学人文学部
今日、地球上の各地で沙漠化の問題がクローズアップされている。なかでも、中国・内モンゴル地域の沙漠化については、日本でも注目されている。では、沙漠化をもたらした原因は一体何であろうか。今後、人々は沙漠という存在といかに接するべきかをモンゴルの視点から考えてみたい。
1.沙漠化をもたらしたのは遊牧民ではなく、農耕民である
モンゴルなど北・中央アジアの遊牧民はウマ、ウシ、ラクダ、ヒツジとヤギの五畜を放牧し、その乳と肉を生活・生産資源としてきた。彼らは季節ごとに異なる放牧地を有し、そのあいだの移動をくりかえす。元来、万里の長城以北の地域は降水量が少なく、農耕に適さぬだけでなく、ある一カ所での長期間放牧にも耐えられない環境であった。遊牧民の定期的な、規則正しい移動は、厳しい自然環境を合理的に利用するために発達してきた技術である。換言すれば、移動によって「過放牧」という破壊的な結末を避けることができたのである。
「草原を天の賜物」とみなし、人間が土地を私有化したり、過度に加工したりする行為は忌み避けるべきだ、と遊牧民は考える。沙漠化の原因のひとつとして、植物の伐採があげられてきた。一般的に遊牧民は伐採をおこなわない。森林地帯の人々は枯れた枝しか拾わない。ゴビ草原の住民は家畜の糞を燃料とする。私の故郷オルドス地域は沙漠性草原で、そこには沙嵩(A.ordosica Krasch,A.sphaerocephalla Krasch。学名は「伊克昭盟的生物」による)という植物が生長する。冬のあいだ、大地が凍りついたときのみ、植生の濃密なところをえらんで、若干、枯れかけたものを切る。モンゴル人はこの作業を「植物に風を通す」と表現し、一種の園芸に近い行動である。実際、翌年の生長ぶりは前年よりも良くなる。
ここで歴史を回顧してみよう。
オルドス地域は黄河の南に位置することから河套、河南地とも呼ばれていた。中国の漢族側からの名称である。戦略的に重要な場所であったため、有史以来、遊牧民と農耕民との争奪の地でありつづけた。漢族側がときどきこの地を占領すると、城池をきずき、屯田をすすめた。現在のオルドス地域には40を越える古城の跡が各地に残る。
興味深い現象がある。
歴代王朝の屯田地の中心地だった古城の周囲はほとんど例外なく塩田化している。灌漑によって地中の塩分が上昇し結晶した塩がさらに草原に散って利用できなくなっている。このような荒れはてた古城とその周囲をモンゴル人は「黒い廃墟」と呼ぶ。農耕民と対照的なのは、モンゴル人は早くから乾燥地での開墾がもたらす環境破壊に気づいていた。たとえば、清朝末期に政府がオルドス地域へ大規模な入植と開墾を押しすすめたとき、モンゴル族は抵抗運動を展開した。そのとき、農耕を受け入れられない理由のひとつに、開墾による塩田化をあげていた。その主張は古文書のかたちでヨーロッパの宣教師たちに収集されている(Serruys 1997,'Five documents regarding salt production in Ordos',Bulletin of the school of oriental and african studies)。
私自身の経験を紹介しよう。
1966年から1976年までつづいた文化大革命期のことである。遊牧民はすべて定住を強制されていた。我が家は身分上「労働人民を搾取した悪い階級」と断定されたため、家畜放牧の権利を奪われ、農業労働を命じられていた。多数の農民が我が家の周辺に押しかけて草原を開墾しはじめたのは1970年のことである。灌漑はなく天水に頼る農業だった。最初の年だけ収穫があった。翌1971年からは収穫が減少し、ついに1974年には政府も我が家近辺での開墾を中止せざるをえなかった。
一度開墾され、やがて捨てられた草原にはところどころハンホクという家畜も食べない毒草だけが生長したが、大半は何もない「本当の沙漠」に化していた。我が家の周囲にふたたび牧草が生えてきたのは、1990年に入ってからのことで、緑がもどるまで10年間以上待たなければならなかった。もっとも、我が家の周辺は偶然にも成功した方で、開墾されてから、二度と緑にもどれない地域の方が多い。
以上、私自身の調査と経験からいえば、沙漠化をひきおこしたのは農耕民であって、本来の住民である遊牧民はむしろ環境に優しい生活を営んできたのである。
2.いままでの沙漠研究の問題点と緑化運動
黄沙が飛来する日本にとって、沙漠化は決して他人事ではないようである。たとえば、鳥取大学乾燥地研究センターは早くからオルドス地域に研究所を設置し、研究活動をつづけてきた。今日、日本人研究者は内モンゴル全域に足をのばし、活動範囲を広げている。
日本人研究者の成果は大いに評価すべきであろう。しかし、被調査者側のモンゴルからみれば、同時に懸念せざるをえない問題もある。いくつかの事例をあげよう。
まず、研究姿勢である。現地に行って来た研究者は現地語を学ぼうとしなかった。その結果、調査地である内モンゴルの地名のモンゴル語表記は間違いだらけである。漢語を媒介に調査がおこなわれたため、現地語表記を無視した結果となっている。
つぎに、現地の知識を吸収しようとしなかった。現地語の修得が欠けているだけではない。公開された論文のなかで、たとえば植物名は学名しかなく、現地語でなんと呼んでいるかに関心を示さなかったようである。モンゴルにかぎらず、世界のどの民族においても複雑な植物認識体系が確立されている。モンゴルの場合、たいていの植物には二通りの名称がある。モンゴル語名とチベット語名である。モンゴル語名称は牧草利用、草原利用と関係し、チベット語名は医薬用と連動する。いわば、植物の名称に自然認識の論理が内含されているのである。現地語の表現と現地名称を無視した研究は、まさに机上の空論にすぎない。
第三、日本人の研究成果は現地に還元されていない。学名だけをならべた論文を専門外の人は読んでも分からないし、われわれがそれらを現地語に翻訳する際にも困難が大きい。研究成果を現地に還元し、現地の自然環境の保護に有益的に消化されるためには、研究者自身が謙虚になって、現地住民の環境認識と植物利用方法を学ぶ必要がある。
第四、日本人研究者の研究成果は悪用される恐れがあり、研究は民族文化の保護と維持を意識しなければならない。日本人による沙漠研究は、緑化も目的のひとつであるようだ。ただし、沙漠地域での緑化はすなわち農産物の栽培をどのように促進するなど、緑化=農耕開墾を意味しているような印象が強い。というのは、いかに灌漑すれば作物が生長し、何本の木を植えれば防風林となって農耕地が保護できるか、という実験が多いのではなかろうか。沙漠化を防止するためには、農耕を中止し、定住から再度移動放牧に回帰しなければならない、という発送は毛頭ないのではないか。なぜ、北・中央アジアに歴史がはじまって以来ずっと遊牧文明が発達してきたか、ということも検討しないで、ひたすら農耕をすすめる考え方の背後には、「狩猟→遊牧→農耕→都市」という発展段階論的な思想が機能しているのではなかろうか。
中国は有史以来遊牧民を脅威とみなしてきた。遊牧民を定住させ、農耕民に改造することは、国家維持のための政策である。場合によって、あるいは結果として日本人の研究成果は、モンゴル族を定住させ、中華に同化させるという政治的な行為に利用される危険性がある。研究成果がだれにいかなるかたちで利用されるかを意識しないできた人類は、すでに代価をはらっていることを忘却してはならない。
水さえやれば作物や草が生長する、というシンプルな発想は捨てなければならない。乾燥地での灌漑は塩田化にもなることをみこんだうえで研究をつづけてほしい。内モンゴル地域を対象とした沙漠研究は、ある意味では科学の限界を示す典型的な例のひとつでもあろう。
毎年春になると、日本各地から内モンゴルに緑化運動の団体が出かける。モンゴル文化に触れ、コミュニケーションが促進されることは大いに結構だが、文明論に立脚した緑化運動が展開されてほしい。厳しい自然環境を破壊せずに、何千年にもわたってその地に生活してきた人々の知恵、その地に成立してきた遊牧文明を無視し、自分の出身文化をおしつける方法は改めるべきである。
3.将来への展望
清朝末期に政府が「移民実辺」政策をうちだしたとき、モンゴル族は塩田化を理由に反対したことはすでに述べた。しかし、モンゴル族の主張は一度も受け入れられなかった。清朝が崩壊し、中華民国に入ると、政府は漢族農民の入植を奨励し、軍隊による屯田もおこなった。この時期、内モンゴル東部と中部に勢力をはっていた日本軍政権も農業活動に従事するようにモンゴル人を勧誘した。
社会主義中国が1949年に成立すると、政府は歴史上のどの王朝よりも徹底的に遊牧民の定住化をすすめた。組織的に漢族農民を移住させるのみならず、もとからの住民モンゴル人をも人民公社というコミュニティに編入し、定住化政策を強行した。異民族を自らの生活形態に改造し、次第に同化させるという点では、いまの中華人民共和国は歴代王朝よりも成功しているといえよう。
沙漠化の拡大という環境破壊の面でも、現在の中華人民共和国の50年のあいだの変化は、歴代王朝の累積よりも激しいのではなかろうか。例をあげてみよう。現在70-80代の老人によると、かつてのオルドス地域には沙漠性草原のいたるところに無数の水溜まりや湖、小川があったという。1960年代まで、一般のモンゴル人は井戸を掘ることはしなかった。家畜も人間も湖や河の水でじゅうぶん足りていたからである。人民公社と文化大革命を経た現在、湖や河は姿を消し、普通の井戸よりも十数メートルも深く、電気ポンプ式井戸ではないと生活できないような地域も現れるようになった。地下水位の変化を物語っている。
1960年代までのオルドス地域には、オオカミやガゼルなどの野生動物が生息し、子どもだった私がひとりで放牧にでかけるのが怖かったぐらいだった。1970年代に入ってから人口増加にともない次第に絶滅においこまれた。
中華人民共和国が積極的に漢族農民の入植をすすめた結果、オルドス地域をはじめ、内モンゴル各地に無数の漢人村落が形成された。漢族はどこへ移動しても農業中心の生活を営む。乾燥地域での営農は環境を破壊しただけでなく、異なる生活を送ってきたモンゴル族とのあいだで、衝突も増えるようになった。
遊牧民を定住させる為政者側には、農業=文明化という発想が根底にある。沙漠化など自然環境の変化を考えるならば、遊牧すなわち野蛮という偏見を放棄しないかぎり、根本的な改善策は導きだされないにちがいない。無視できないのは、日本人研究者も農業的な出自を有し、遊牧生活にほとんど関心をはらわなかったということである。農業国だった日本出身の研究者たちは、どこかで中国の漢族と同様な考え方をもっているのではないか。北・中央アジアの広大な、厳しい自然環境のなかで、遊牧という生活形態が人類の一部を養ってきたことを評価し、遊牧文明に対する再認識をしなければならない。
内モンゴル地域での沙漠化が食い止められないもうひとつの人的原因は、政府の政策が安定しないことに原因があろう。内モンゴル自治区の指導者が替わるたび、政策も変化する。牧畜や植林を重視する指導者がたまに現れても、数年後には中止されたりして、成果が実らないのが現実である。いままでに何度もあったことである。
歴史を鑑み、とくに20世紀後半50年をふりかえることにより、われわれは将来へ向けてひとつの結論を出したい。内モンゴルにおいて農業を中止し、牧畜に重点を置くであろう。牧畜でも定住放牧ではなく、移動遊牧という原点にもどらなければ、沙漠化を防止する方策はない。遊牧こそ、沙漠化問題を解決する唯一の道である。
誰のための植林か、問われる本質問題
中国内モンゴル自治区で砂漠化防止植林を行う日本のボランティア団体は15とも、20とも言われている。これらの団体は1990年代初頭から本格的な活動を開始し、その活動範囲は内モンゴル砂地全域をカバーしている。その中、主力的な日本の海外ボランティア団体も数多く存在する。これらの団体の規模や特色は様々であるが、多様性こそがNGO、NPOの特長でもある。近年それぞれの植林活動の成果が公表され、砂漠化防止の一歩を踏み出した。砂漠化防止策においては、また試みの段階であるが、今までの活動で蓄積した成果は中国の砂漠化防止国家政策に大きな刺激を与えていることも確かである。
しかし、これらの団体の殆どは官・民の助成機関から補助金を受けて活動していると言う点で共通している。植林地における団体の活動資金はほとんどが助成機関の資金提供によるものである。確かに、一定の会員数を保持し会費収入が多いところもある。しかし、それでも補助金がないとその多くの団体は自立した活動を出来ないのが現状である。植林団体にとっては、現地における活動を継続的に行うためにいかに補助金を確保するかは大きな課題なのである。
助成機関としては、いち早く結果が出て、注目される事業に補助金を出しやすい。助成前と助成後の著しい変化、成果は審査官の目を引き、継続事業になりやすい。しかし、いつの間にか変化=成果という方程式が成り立ってしまうことも度々ある。これにより、助成先への配慮の度合いが増すに連れ、現地への配慮が追いつかないという現象が生じてくる。何のための植林か、誰のための植林であるべきか、という本質的な問題があやふやになってしっている。
現地住民は日本からの「緑の使者」を歓迎し、大きな期待を抱いている。しかし、牧草地が植林地化される現状への懐疑も隠せない。地下水が比較的豊富な牧草地での植林は、活着がよいため補助金の報告書は書きやすい。また、植林団体の誤解も少なからずある。牧民の家畜が植林地に入り込むことが植林事業実施の障害となるとしたり、強く「禁牧」(家畜の放牧を禁止し、宿舎飼育を奨励する)を訴える団体さえある。植林地の活着率を優先する植林団体と、自分の生活の糧でもある牧草地が植林地化されることに戸惑う牧民の間では砂漠化防への認識や思い入れに違いがある。昨年から内モンゴル自治区では広範にわたる放牧地の「禁牧」の政策が実施された。しかし、従来種のモンゴル五畜は宿舎飼育に適さず、牧民は家畜を手離すことを強制された。牧畜地域における家畜の激減に伴い、牧民はさらに貧困へと追いやられているのが現状だ。
内モンゴル草原の生態系はその地域によって大きく異なる。また、砂漠化の過程も多様である。灌木が多くあった牧草地のところもあれば、木が全くなかった牧草地も少なくない。歴史的に形成された砂地の砂漠化防止植林に、該当地域の自然の歴史を調査し研究することを強く薦めたい。砂漠化防止に喬木の植林は確実で早いが、従来の植物多様性の回復に灌木、牧草の回復も欠かせない。また、本来喬木がなかったところでのポプラの植林は地下水位低下、植物多様性の回復が困難になる。砂漠化防止植林は牧草回復、灌木植林を視野に入れた多様性をもつ事業として進められることが急がれている。同時に、現地住民を砂漠化防止植林の主力に導き、主役と位置づけ、現地住民本位の植林(植草、植灌木)がなされるべきである。
筆者:ボリジギン・セルゲレン(BORJIGIN Sergelen)、1971年中国内モンゴル・ホルチン生まれ、1994年内モンゴル師範大学卒業、来日。現東京大学大学院法学政治学研究科博士一年生、政治専攻。2000年5月、内モンゴル沙漠化防止植林の会(NGO)を設立、代表を務める。
(http://www2.neweb.ne.jp/wd/sergelen/desert.html )中国内モンゴル・ホルチン
砂地において、「ヒト・動植物共存モデル」地域作りに取り組んでいる。










 遠山正瑛(1906-2004年)
遠山正瑛(1906-2004年)
 内藤湖南「支那論」
内藤湖南「支那論」

 竹内実氏
竹内実氏