都月満夫の絵手紙ひろば💖一語一絵💖
都月満夫の短編小説集
「出雲の神様の縁結び」
「ケンちゃんが惚れた女」
「惚れた女が死んだ夜」
「羆撃ち(くまうち)・私の爺さんの話」
「郭公の家」
「クラスメイト」
「白い女」
「逢縁機縁」
「人殺し」
「春の大雪」
「人魚を食った女」
「叫夢 -SCREAM-」
「ヤメ検弁護士」
「十八年目の恋」
「特別失踪者殺人事件」(退屈刑事2)
「ママは外国人」
「タクシーで…」(ドーナツ屋3)
「寿司屋で…」(ドーナツ屋2)
「退屈刑事(たいくつでか)」
「愛が牙を剥く」
「恋愛詐欺師」
「ドーナツ屋で…」
「桜の木」
「潤子のパンツ」
「出産請負会社」
「闇の中」
「桜・咲爛(さくら・さくらん)」
「しあわせと云う名の猫」
「蜃気楼の時計」
「鰯雲が流れる午後」
「イヴが微笑んだ日」
「桜の花が咲いた夜」
「紅葉のように燃えた夜」
「草原の対決」【児童】
「おとうさんのただいま」【児童】
「七夕・隣の客」(第一部)
「七夕・隣の客」(第二部)
「桜の花が散った夜」
刑事ドラマや映画では「刑務所」のことを「ムショ」と呼ぶことがあります。
これは「刑務所」を省略した言葉かと思っていましたが、そうではないようです。
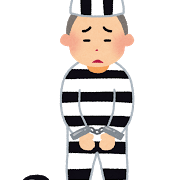
「ムショ」は刑務所のことを指す言葉であり、そこから「刑務所」の略のようにも思えるが実は違う。
 日本で「刑務所」という言葉が生まれたのは1922年(大正11年)のこと。それよりも以前に「監獄」のことを「ムショ」と呼んでいた。
日本で「刑務所」という言葉が生まれたのは1922年(大正11年)のこと。それよりも以前に「監獄」のことを「ムショ」と呼んでいた。
ではなぜ監獄のことを「ムショ」と呼んでいたかというと、当時、監獄で囚人に出されるご飯が白米100%ではなく麦が6割、米が4割の麦飯であった。
そこから「六四(むし)よせば」と呼ぶようになり、その略で「ムショ」となったというのは俗説です。
1915年(大正4年)に京都府警察部が発行した警察用語集「隠語集覧」に「むしょ」は「むしよせばの略」という記載がある。また、江戸時代には牢屋のことを虫籠のようであったことから「虫寄場(むしよせば)」と呼んでいた。

|
む‐しょ 刑務所をいう俗語。「むしょ帰り」 [補説]監獄をいう「虫寄場(むしよせば)」の略。 デジタル大辞泉の解説 |
ちなみに、現在の刑務所ではクリスマスにケーキが出て、番号で呼ばれることはなく名前で呼ばれる。また、パピープロジェクトとして受刑者が盲導犬候補の子犬を育てる教育プログラムがある。

北海道網走市には「網走監獄博物館」があります。私も何度か行ったことがありますが、ああいったところには収容されたくありません。
まっとうに生きている人間には関係にないところですが、「ムショ」の語源が意外なものだったので記事にしました。
昨日の雑学クイズ問題解答
雑学クイズ問題の答えは「B.虫かごのこと」でした。
|
雑学クイズ問題 神社に玉砂利が敷いてあるのは何故なのか? A.歩きづらいので、参拝者がゆっくり歩く B.歩くと音が出るので賽銭泥棒除け C.川に見立てて身を清めるため D.わからない 答えは明日の記事で解説します。 |
 |
虫かご カッコイイ!! アイゲージ 全面金網貼りで観察しやすい!出し入れ簡単♪ *僅少在庫になりました! |
| クリエーター情報なし | |
| 池田工業社 |



















