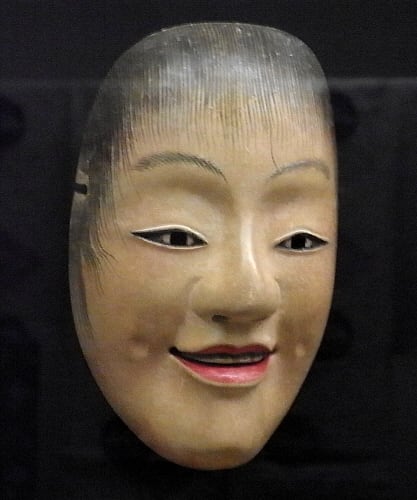最近、旅をしていない。
と、言いつつ、私はもうすぐ旅に出るのだが・・・。
夫婦揃って出かけるのが難しい家庭環境。
いつも旅先で水を汲んでくるのだが、それも底をついた。
近い所でどこか・・・?
室生の大師水、R168十津川手前の水、ごろごろ水・・・。
思いつくのはそれぐらいしかない。
ずぼらっちさんに聞いていた「ごろごろ水」を汲みに行く事に。

新しい水汲み場になってから来るのは初めて。
日曜日とあって汲みに来る人がいっぱい。
駐車待ちの車が何台か停まっていて、その後続につく。

1時間以内の駐車で300円の駐車場料金を支払えば、水はいくらでも汲める。
車の駐車スペースの背後に水が出る蛇口があり、車まで運ぶ必要がなくとても便利。
その蛇口前の駐車スペースが空くのを車内で待ち、空けば係員が誘導してくれる。
上の写真は、車とは離れた汲み場だが、順番待ちをしなくても汲める場所。
ポリタンクを運ぶ台車も用意され、私はここで汲み始めるが、
すぐに蛇口前のスペースが空いた。

車とは離れた汲み場で、ポリタンクがずらりと並ぶ。
車1台につき蛇口は1箇所の使用との約束事。

塩ビの蛇口から冷たい水がどんどこと・・・。
2Lのペットボトルはすぐに満杯。
ペットボトル78本に水を頂く。

来た道を戻らず、ずぼらっちさんに教えて頂いた林道経由で吉野へ向かう。
杉木立が美しい道を走る。

何?この鉄橋は・・・?
走り過ぎて振り返ると滝が見えた。
大天井滝はこれだな。
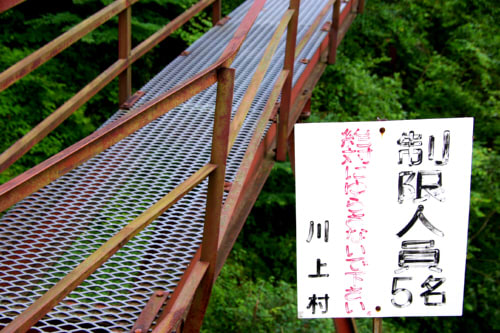
一度に5人以上は通れない。
高くはないが、結構揺れる。

3段になって流れ落ちる大天井滝。

陽に照らされた上部はきらきら輝く。

高原洞川林道から吉野大峰林道へ入り、眺めも良いが運転手は路面から目が離せない。

いたる所で落石が見られる。

林道は全面舗装だが、ところどころ、砂利道のように思えるぐらい大小の落石があり、
大きくえぐられた路肩もあった。
通行止めのカラーコーンが道の半分に置かれているが、
完全に道路をふさいではいない。
通行止めの看板も何箇所かで見た。
走るなら自己責任で・・・と、いうところかな。
吉野~大峰、修験者達が修行する奥駈道というのがあるが、
この林道は、さながら車の奥駈道。
緊張を強いられる道だった。
吉野の水分神社あたりへ出た時は、ほっとしたが吉野も細い道が続く。
桜の頃のあの混雑がうそのような静かな吉野。

R169下市にある、ずぼらっちさんお勧めの「よしなや」で遅い昼食。

ねぎたまうどん定食を注文。
これが出てくるのがめちゃくちゃ早い。
待たされるのが嫌いな大阪人でも驚く早さ。
自家製の柿の葉寿司が3つとデザートバナナがついている。

こしがあり、ふっくら柔らかいもちもちうどん。
四国のうどんのような硬さはなく、私には初めての食感のうどん。
昔、一度だけ食べた事のある水沢うどんは、こんなだったかなぁ・・・?
汲んできた水がなくなれば、又、「ごろごろ水」と「よしなや」のセットで行こう。