今のような 機械化されていない頃の五反百姓の家に産ま れ、高校まで田圃の手伝いをしていた呑百姓の小倅です。
そのくせ、今頃になって、そうだったのかと驚かされる記事がありました。と言うのも、連作は良くないというのは聞い ていまし たが、それが、稲作には当てはまらないというものです。そういえば、稲は毎年作っていました。それを当然と思って、それが不思議 とも思ってませんでした。我ながら、その観察眼の無さに、今更ながら呆れてしまいます。
北國新聞社より 2016/10/13
きょ うのコラム『時鐘』
ことしも「豊作(ほうさく)」である。16年産米(ねんさんまい)の作況(さっきょう)指数(しすう)は全国平均(ぜ んこ くへいきん)103で「やや良(りょう)」、北陸(ほくりく)だけなら107の「良」となった。39年ぶりの高水準(こうす いじゅん)だという
天候不順(てんこうふじゅん)で水害(すいがい)も多(おお)く、ひどい年(とし)だったとの印象(いんしょう)があっ た。 が、被害(ひがい)は一部地区(いちぶちく)にとどまり、秋(あき)になると国全体(くにぜんたい)で「まずまず」の作柄 (さくがら)に落(お)ち着(つ)く。毎年(まいとし)、作況指数が公表(こうひょう)されるたびに同(おな)じ感慨 (かん がい)を覚(おぼ)える。「水稲(すいとう)は強(つよ)い」と
農業(のうぎょう)には連作障害(れんさくしょうがい)がおきる。同じ作物(さくもつ)を同じ田畑(たはた)に植(う) え続 (つづ)けると収穫(しゅうかく)が落(お)ちたり病気(びょうき)が出(で)やすくなる現象(げんしょう)だ。だから年ごとに植える作物を変(か)え る。障害を避(さ)けるための農民(のうみん)の知恵(ちえ)である
ところが、水稲は延々(えんえん)と同じ田に植え続ける。極端(きょくたん)に言(い)えば二千年(にせんねん)続く連 作であ る。それで連作障害が出ないのは「水(みず)の力(ちから)」(北陸農政局(ほくりくのうせいきょく))だという。稲(い ね)は水の運(はこ)んでくる養分(ようぶん)で育(そだ)ち、水は田んぼの垢(あか)を流(なが)し続ける。土(つ ち)は 水のおかげで年ごとに蘇生(そせい)しているのである
水田(すいでん)と稲の関係(かんけい)はまるで神話(しんわ)だ。瑞穂(みずほ)の国(くに)とは「水(みず)の穂 (ほ)」のことか。古代(こだい)の人々(ひとびと)はこの謎(なぞ)を知(し)って稲づくりを始(はじ)めたのだろう か。 多分(たぶん)わかっていたと思(おも)う。大変(たいへん)な伝統(でんとう)の力である。
本当に、こんなこと考えもしませんでした。やはり、頭の悪いのは、どうしようもないようです。それにしても、先人の 凄さに改 めて驚かされます。
もし、稲作が連作が効かないものだったら、飢饉が度々起こっていたと考えると、やはり、知っていたのでしょうね。そ の米を主 食にしてくれた先人に改めて礼を言いたくなります。
と言うことで、サーチしてみました。
ウィキペディアより 連 作
分り易く教えてくれるブログがありました。
ツナギのお米マ ガジンよ り 2015/04/07
稲 は連作障害がおこらない!?
みなさん連作障害という言葉を聞いた事はあるでしょうか?あまり馴染みがない言葉ですかね?同じ場所に同じ作物を連続 で栽 培すると、生育が極端に悪くなったり、収穫量が減ったり、病害虫が発生しやすくなるといった現象が発生します。これを連作障 害と言います。
作物を栽培すると、土中にあるその作物が好む養分が使われ欠乏しやすくなります。その作物を好む病原菌が土中に増えて いき ますし、土中の養分バランスも悪くなります。そして翌年も同じ作物を植えるとさらにその傾向が進み、作物が育ちづらくなって きます。
連作障害を防ぐために畑では輪作を行い、毎年作る作物を変える事で対応していきます。では田んぼではどうでしょうか? お米 農家さんからは、よく「先祖代々伝わる田んぼでお米を作っている」と聞きますが、稲は同じ土地で毎年作り続けることができま す。野菜では発生する連作障害がなぜ稲にはおこらないのでしょうか。
田んぼに水を張ることがポイント
田んぼで連作障害が起こらない理由は、「水を張っているから」です。
河川や用水から田んぼに流れ込む水に含まれる養分(山の落ち葉や窒素・リン酸等)を利用できます。水を入れる事で毎年多 くの 養分が田んぼに補給されることになります。また、水の影響で土の中にたまる有害物質が洗い流され、過剰な成分や有害な成分を 流し出し、雑草の発生を抑えてくれます。田んぼに水をためることで、土壌中の酸素が微生物によって使われてしまい、土の 中は 酸欠状態になり、有害な微生物や菌類が死滅してしまいます。酸性だった土が次第に中性になり、稲が育ちやすい環境になってき ます。微生物の活動が鈍くなり根や葉などの有機物の分解がゆっくり進むため、長い時間稲に養分がいきわたります。
気温の変化からも守ってくれる
水は温まりにくく冷めやすい性質があり、水を張ることで温度の急激な上昇を防ぐことができます。稲を寒さから守ってあ げた り、夏の暑い時期には深水や掛け流しをすることで高温障害をおさえる役割を担ってくれます。何百年にもわたり、同じ土地で米 を作り続けることができる理由は、「田んぼに水を張る」という大発明のおかげなのです。
もうすぐ田植えの時期ですが、太陽の光がキラキラ映える田園風景には、こんなチカラが隠れていたのです。ツナギでご紹 介し ている農家さんたちの自慢の水田には、どれも綺麗な水が流れ込んでいます。この水こそが美味しいお米の必須条件なのでしょ う。
その稲を作るために先人は田圃を作らなければなりません。そう考えると、ねずさんが教えてくれた古墳の話を思いだし ます。
ねずさんと学ぶシラス国の物語よ り 2016/03/13(日)
古 墳のお話
改めて、素晴らしい国に産まれたものだと感謝せずにはいられません。こんな国が嫌いな人達を沢山育てた、教育の恐ろ しさを思 わずにいられません。
一日も早く目を覚まし、先人が作ってくれた日本を取り戻しましょう。
最新の画像[もっと見る]










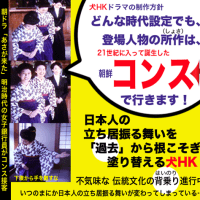
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます