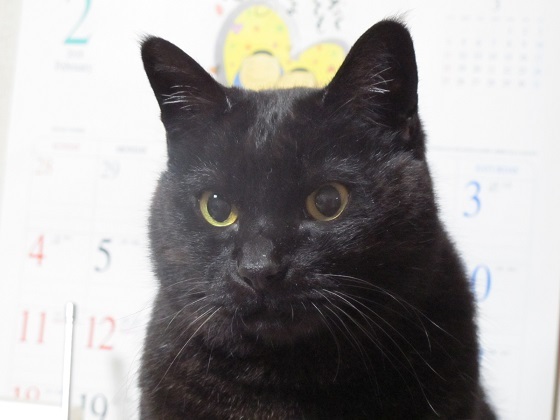前に紹介した六波羅蜜寺から歩いてすぐの、
京都最古の禅寺、建仁寺の開山が栄西です。
一般には「えいさい」と読まれているけど、
寺の伝えでは「ようさい」と読むのだそうです。
遣唐使が廃止(894年)となり、国内の戦乱もあり、
喫茶の風習が衰退していった。
このような状況の中、
栄西が1191年、宋から持ち帰った茶の種を
九州の背振山に蒔いたり、
栂尾の明恵上人にお茶の種を贈ったり、
「喫茶養生記」を著し、茶の効用や作法など喫茶法を普及し、
お茶の栽培や茶を喫すことを奨励したことで
喫茶の風習を再び広げるきっかけをつくりました。
そこで栄西は『茶祖』と言われています。
建仁寺の境内にはお茶の木がたくさんありました。
茶碑も建っていました。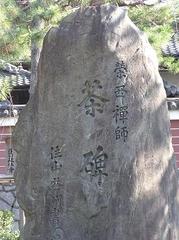
四月二十日には茶祖栄西を偲んで、
「建仁寺茶礼」が行われるのだそうです。
これは寺の方丈に集まった客に
僧から抹茶の入った台付きの天目茶碗と菓子が配られ、
続いて、注ぎ口に茶筅がはめてある浄瓶を左手に持った僧が、
客の前に立ち、右手で茶筅を取り、
客が差し出した茶碗に湯を注ぎ、
右手の茶筅で点茶し客にお茶を供するというもの。
誰でも参加できるのかな?
仕事が休みだったら行ってみたいな・・・・・
建仁寺は俵屋宗達の風神雷神でも有名。
自由に写真撮影OKでした・・・・・・・・何て心の広い!!
と思ったら、レプリカでした。
法堂の天井には平成十四年に
創建800年を記念して描かれた「双龍図」。
いずれも見応えがありました。
この二つの画は後ほど紹介しますね。お楽しみに・・・・