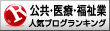昨日に引き続き全国介護事業者協議会理事長馬袋氏が「介護労働者の確保・定着等に関する研究会」での発言の話題。
彼は研究会席上、特定事業所集中減算の創設に伴い、チームケアが難しくなった、介護報酬の体系のなかにケアを難しくする部分があると指摘している。
私見としては今の介護報酬体系にケアを促進する要素は少ないが、阻害する要素は現報酬体系にはないとみている。
たとえば「特定事業所集中減算」について、この要件の考え方はアセスメントを行い、ケアプランを作成する段階でサービス提供事業所の意向が働き、本来のアセスメントに基づかないケアプランに変更が加えられる結果として一定の事業所に集中する現象をとらえての対策とみているが、一方では該当の地域でのサービス提供事業者の内容が他の事業所と比較して優れている、お客様から支持されている事業所が限られている、信頼のおける事業所が他にないという事情などの場合には必然的に特定の事業所の利用が多くであろうし、ケアマネジメントが確実に実行されているのであればこの減算の設定には納得がいかないことになる。
このような考え方から「特定事業所集中減算」を判断するときには、この減算をもってチームケアの実現が妨げることに直結しないのではないかと考える。
彼の立場は居宅だけを見ているものとは違う観点にあるわけだが、居宅の立場から、居宅に限定して介護報酬を見ると議論すべきはケアマネジメントを適正に評価しているか、さらにはケアマネジメントが確実に実行されることを保証しているかという観点での議論になる。
さすれば議論すべきは「特定事業所」要件であり、現状、全国3万の居宅が稼働している中でこの「特定事業所」加算取得事業者は0.03%以下という事態こそ議論する必要があるだろう。
彼は研究会席上、特定事業所集中減算の創設に伴い、チームケアが難しくなった、介護報酬の体系のなかにケアを難しくする部分があると指摘している。
私見としては今の介護報酬体系にケアを促進する要素は少ないが、阻害する要素は現報酬体系にはないとみている。
たとえば「特定事業所集中減算」について、この要件の考え方はアセスメントを行い、ケアプランを作成する段階でサービス提供事業所の意向が働き、本来のアセスメントに基づかないケアプランに変更が加えられる結果として一定の事業所に集中する現象をとらえての対策とみているが、一方では該当の地域でのサービス提供事業者の内容が他の事業所と比較して優れている、お客様から支持されている事業所が限られている、信頼のおける事業所が他にないという事情などの場合には必然的に特定の事業所の利用が多くであろうし、ケアマネジメントが確実に実行されているのであればこの減算の設定には納得がいかないことになる。
このような考え方から「特定事業所集中減算」を判断するときには、この減算をもってチームケアの実現が妨げることに直結しないのではないかと考える。
彼の立場は居宅だけを見ているものとは違う観点にあるわけだが、居宅の立場から、居宅に限定して介護報酬を見ると議論すべきはケアマネジメントを適正に評価しているか、さらにはケアマネジメントが確実に実行されることを保証しているかという観点での議論になる。
さすれば議論すべきは「特定事業所」要件であり、現状、全国3万の居宅が稼働している中でこの「特定事業所」加算取得事業者は0.03%以下という事態こそ議論する必要があるだろう。