都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。
はろるど
熱狂の日音楽祭2006 「モーツァルト:ホルン協奏曲第3番」他 5/5
ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン 熱狂の日音楽祭2006
モーツァルト ディヴェルティメントK.137
ホルン協奏曲第3番K.447
ディヴェルティメントK.138
演奏 ベルリン古楽アカデミー
ホルン ヴァーツラフ・ルクス
2006/5/5 13:00 東京国際フォーラムホールB7(ダ・ポンテ)
ベルリン古楽アカデミーの演奏と言えば、私の愛聴盤はバッハなのですが、この日はモーツァルトの愉しい管弦楽曲と、ルクスとのコンビによるホルン協奏曲で楽しませてくれました。「熱狂の日音楽祭」コンサートの第1弾です。
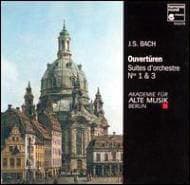
ともかく印象深かったのは、2曲目のホルン協奏曲第3番でした。独奏ホルンはチェンバロ、またはオルガン奏者としても知られるというヴァーツラフ・ルクス。楽器はもちろんナチュラルホルンです。この曲は一般的なホルンで演奏されると、とても素朴で長閑な印象を与えますが、それがナチュラルホルンという不安定な楽器にかかると、一転してオーケストラとぶつかるかのようなスリリングな展開を見せてきます。まさにロイトゲープとモーツァルトの掛け合い。ナチュラルホルンとオーケストラの漫才です。
ルクスは、殆ど残響のないこのホールB7にて楽器と格闘します。忙しなく朝顔へ手を出し入れして、何とか楽器から音を出そうとするその必至な姿。もちろんバルブはありません。細かいパッセージはまさに手に汗を握る展開です。第1楽章のカデンツァの息を飲むような音の連なりと、それを演奏し終わった時の安堵感。演奏者の息遣いが間近に聴こえてきました。目まぐるしく表情が変化する第3楽章のロンドにおいても、時にオーケストラへ優しく寄り添い、また時にはいがみ合うようにしてホルンを奏でていく。賑やかな、あっという間の15分間でした。
ディヴェルティメントでは初めのK.137が秀逸です。もっとインテンポにて曲へ切り込むように演奏するのかと思いきや、意外にもソフトタッチのヴァイオリンを主導にして、曲の輪郭を丁寧になぞっていきます。オーケストラの後列にて、何やら得意げに存在を誇示する二人のコントラバス奏者。彼らが自己主張すると、オーケストラ全体に良い意味での緊張感をもたらします。全身を揺らしながら楽しそうに楽器を操る様子。それは演奏にもすぐに伝わります。平板な表現ではすぐに退屈になってしまうこの機会音楽を、安定した合奏力にてしっかりと聴かせてくれました。モーツァルト初期のロココ調の軽やかさ。それをたっぷり味わえる内容だったと思います。
「こんな楽団でシンフォニーの25番や31番を聴ければ。」と思ってしまうほど充実したコンサートでした。さすがのベルリン古楽アカデミー。決して無茶をしないで、古楽器演奏の王道をいくようなスタイルで楽しませてくれます。至福の一時でした。
モーツァルト ディヴェルティメントK.137
ホルン協奏曲第3番K.447
ディヴェルティメントK.138
演奏 ベルリン古楽アカデミー
ホルン ヴァーツラフ・ルクス
2006/5/5 13:00 東京国際フォーラムホールB7(ダ・ポンテ)
ベルリン古楽アカデミーの演奏と言えば、私の愛聴盤はバッハなのですが、この日はモーツァルトの愉しい管弦楽曲と、ルクスとのコンビによるホルン協奏曲で楽しませてくれました。「熱狂の日音楽祭」コンサートの第1弾です。
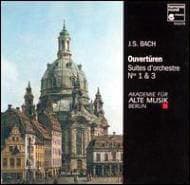
ともかく印象深かったのは、2曲目のホルン協奏曲第3番でした。独奏ホルンはチェンバロ、またはオルガン奏者としても知られるというヴァーツラフ・ルクス。楽器はもちろんナチュラルホルンです。この曲は一般的なホルンで演奏されると、とても素朴で長閑な印象を与えますが、それがナチュラルホルンという不安定な楽器にかかると、一転してオーケストラとぶつかるかのようなスリリングな展開を見せてきます。まさにロイトゲープとモーツァルトの掛け合い。ナチュラルホルンとオーケストラの漫才です。
ルクスは、殆ど残響のないこのホールB7にて楽器と格闘します。忙しなく朝顔へ手を出し入れして、何とか楽器から音を出そうとするその必至な姿。もちろんバルブはありません。細かいパッセージはまさに手に汗を握る展開です。第1楽章のカデンツァの息を飲むような音の連なりと、それを演奏し終わった時の安堵感。演奏者の息遣いが間近に聴こえてきました。目まぐるしく表情が変化する第3楽章のロンドにおいても、時にオーケストラへ優しく寄り添い、また時にはいがみ合うようにしてホルンを奏でていく。賑やかな、あっという間の15分間でした。
ディヴェルティメントでは初めのK.137が秀逸です。もっとインテンポにて曲へ切り込むように演奏するのかと思いきや、意外にもソフトタッチのヴァイオリンを主導にして、曲の輪郭を丁寧になぞっていきます。オーケストラの後列にて、何やら得意げに存在を誇示する二人のコントラバス奏者。彼らが自己主張すると、オーケストラ全体に良い意味での緊張感をもたらします。全身を揺らしながら楽しそうに楽器を操る様子。それは演奏にもすぐに伝わります。平板な表現ではすぐに退屈になってしまうこの機会音楽を、安定した合奏力にてしっかりと聴かせてくれました。モーツァルト初期のロココ調の軽やかさ。それをたっぷり味わえる内容だったと思います。
「こんな楽団でシンフォニーの25番や31番を聴ければ。」と思ってしまうほど充実したコンサートでした。さすがのベルリン古楽アカデミー。決して無茶をしないで、古楽器演奏の王道をいくようなスタイルで楽しませてくれます。至福の一時でした。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )










