都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。
はろるど
「目白バ・ロック音楽祭」 いよいよ開幕まであと10日!
「翠松庵no散歩道」のるるさんに教えていただけるまで全く知らなかったので、私がここで偉そうに紹介するのもおこがましいのですが、初夏の目白を飾る音楽の祭典「目白バ・ロック音楽祭」が、いよいよ来月2日から始まります。私も一公演だけ予定していますが、未知の音楽祭なのでとても楽しみです。(17日に目白聖公会で行われる、寺神戸亮のチェロ組曲を聴く予定です。)
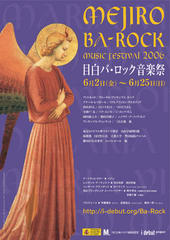
東京の音楽祭と言えば、このブログでもしつこく追っかけた「熱狂の日」がすぐに思い当たります。ゴールデンウィークの東京都心にて怒濤のように繰り広げられた巨大な祭典。その抜群の企画力や集客力は、二回目でありながら、既にクラシックコンサートを超えた大イベントとして認められたところです。そしてこの「目白バ・ロック音楽祭」も、昨年に引き続いての二度目の開催。テーマはもちろんバロック音楽です。喧噪と賑わいに包まれた「熱狂の日」とは逆に、目白の静寂に囲まれた控えめな音楽祭のイメージがわいてきます。小さくともキラリと光るような音楽祭かもしれません。


会期は6月2日から25日までの約一ヶ月間です。予定されているコンサートは約15。二、三日に一度のペースでバロック音楽が高らかに鳴り渡ります。そしてこの音楽祭の最大の特徴は、おそらくその会場にあるでしょう。単なるコンサートホールで音楽を演奏することにとどまらない、目白界隈の多くの由緒ある施設を取り込んだ企画。その一例として、東京カテドラル聖マリア大聖堂(丹下建築の名作としても有名です。)や目白聖公会、または自由学園明日館などを挙げれば十分です。まさに趣きある目白の風を感じとれるような、街歩きの醍醐味すら味わえる音楽の祭典。バロック音楽の似合う街目白。そんなキャッチセールスすら聞こえてくるような音楽祭です。
チケット価格も3000円から5000円前後と、一般的なコンサートよりは若干抑えられています。無知な私は参加アーティストの方をあまり存じ上げないので、おすすめのコンサートなどを無責任に書くことは出来ませんが、まずは建物見たさに、さらには目白の雰囲気を楽しむために、気軽に参加してみるのも良いと思います。また目白界隈では、商店街による各種イベントもあるとのことです。地元が一つとなった手作り感のある音楽祭。住民の方がこのイベントにかける思いも伝わってきます。初夏の東京の暑さを和らげる涼し気なバロックの調べ。それをまず目白にて楽しむのは如何でしょうか。
集客を第一にしたイベントではないようです。各会場の定員はかなり少なくなっています。まずはチケットの残席を確認されることをおすすめします。
関連リンク
目白バ・ロック音楽祭公式サイト
ブログ「目白バ・ロック音楽祭」
ぴあによるチケット残席情報(主催のアルケミスタへ問い合わせるのも確実です。)
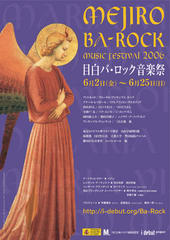
東京の音楽祭と言えば、このブログでもしつこく追っかけた「熱狂の日」がすぐに思い当たります。ゴールデンウィークの東京都心にて怒濤のように繰り広げられた巨大な祭典。その抜群の企画力や集客力は、二回目でありながら、既にクラシックコンサートを超えた大イベントとして認められたところです。そしてこの「目白バ・ロック音楽祭」も、昨年に引き続いての二度目の開催。テーマはもちろんバロック音楽です。喧噪と賑わいに包まれた「熱狂の日」とは逆に、目白の静寂に囲まれた控えめな音楽祭のイメージがわいてきます。小さくともキラリと光るような音楽祭かもしれません。


会期は6月2日から25日までの約一ヶ月間です。予定されているコンサートは約15。二、三日に一度のペースでバロック音楽が高らかに鳴り渡ります。そしてこの音楽祭の最大の特徴は、おそらくその会場にあるでしょう。単なるコンサートホールで音楽を演奏することにとどまらない、目白界隈の多くの由緒ある施設を取り込んだ企画。その一例として、東京カテドラル聖マリア大聖堂(丹下建築の名作としても有名です。)や目白聖公会、または自由学園明日館などを挙げれば十分です。まさに趣きある目白の風を感じとれるような、街歩きの醍醐味すら味わえる音楽の祭典。バロック音楽の似合う街目白。そんなキャッチセールスすら聞こえてくるような音楽祭です。
チケット価格も3000円から5000円前後と、一般的なコンサートよりは若干抑えられています。無知な私は参加アーティストの方をあまり存じ上げないので、おすすめのコンサートなどを無責任に書くことは出来ませんが、まずは建物見たさに、さらには目白の雰囲気を楽しむために、気軽に参加してみるのも良いと思います。また目白界隈では、商店街による各種イベントもあるとのことです。地元が一つとなった手作り感のある音楽祭。住民の方がこのイベントにかける思いも伝わってきます。初夏の東京の暑さを和らげる涼し気なバロックの調べ。それをまず目白にて楽しむのは如何でしょうか。
集客を第一にしたイベントではないようです。各会場の定員はかなり少なくなっています。まずはチケットの残席を確認されることをおすすめします。
関連リンク
目白バ・ロック音楽祭公式サイト
ブログ「目白バ・ロック音楽祭」
ぴあによるチケット残席情報(主催のアルケミスタへ問い合わせるのも確実です。)
コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )
ラ・プティット・バンド 「バッハ:ブランデンブルク協奏曲第4番」他 5/19
ラ・プティット・バンド&シギスヴァルト・クイケン東京公演
J.S.バッハプログラム
2つのヴァイオリンのための協奏曲 BWV1043
ブランデンブルク協奏曲第5番 BWV1050
6声のリチェルカーレ(音楽の捧げ物より) BWV1079
オーボエとヴァイオリンのための協奏曲 BWV1060a
ブランデンブルク協奏曲第4番 BWV1049
監督 シギスヴァルト・クイケン
演奏 ラ・プティット・バンド
2006/5/19 19:00~ 東京オペラシティーコンサートホール2階
「古楽界のパイオニア」(パンフレットより)であるラ・プティット・バンドとクイケン。そんな彼らが真っ向勝負にてバッハを演奏します。時流に乗らないで、あくまでも独自のスタイルを貫く演奏団体のコンサートです。

これが正統的、もしくは伝統的な古楽演奏とでも言うのでしょうか。ともかくラ・プティット・バンドは、明らかに広過ぎたこのホールにおいて、あまり響かない古楽器を控えめに鳴らしながら、まるで楽譜上の音符をなだらかになぞるように端正に演奏していきます。ひたすら淡々と鳴り続けるバッハの調べ。ブランデンブルクがまるでミニマルミュージックのように聴こえてきました。今をときめくイタリアンバロックとは全く隔絶した別の世界。遠いバロックの響きを、聴衆に媚びることなくそのまま提示する。組み立てられた音楽の遺跡。禁欲的で、異端を許さないような、厳格なバロックがここに残っていました。コンサートホールの時間の流れが止まってしまった。この場だけすっぽりと数世紀前にワープしてしまったような気配さえ漂います。まさにかつて誰もが見たであろう、あの音楽室に飾られていた厳めしい肖像画のバッハです。あの物々しいバッハがここに甦りました。

肩からひもで吊るしたヴァイオリンを奏でるシギスヴァルト。失礼ながら彼は、お世辞にも指の良く動くヴァイオリニストとは言えません。むしろ所々ギコギコと響き渡るような美しくない音すら奏でてくれます。クイケン一派では、明らかにサラの方が技巧に長けているでしょう。またオーボエのボージロー。彼のふくよかなオーボエはシギスヴァルトとは一線を画していました。その点、シギスヴァルトと上手く絡み合っていたのは、これでもかというほど抑制的に演奏されたチェンバロです。この二者が合わさって、奇妙に説得力を持った音楽を生み出してくる。シギスヴァルトは朴訥に音楽を語ります。音楽に誠実さを感じること。先日このホールで聴いたビオンディのスーパーエンターテイメント・バロックの対極にある、全く飾らないバロック音楽が表現されていました。最後のブランデンブルクの4番やアンコール曲(4番の第3楽章をもう一度。)にこそ、ライブ特有の熱気が感じられましたが、初めの5番などは非常に冷めた眼差しで音楽を象ります。また、6声のリチェルカーレがこのコンサートの白眉であったのも、それがラ・プティット・バンドの怜悧なアプローチに合致する曲だったからではないでしょうか。リチェルカーレとは、イタリア語で吟味する、または探し求めるという意味だそうですが、まさにラ・プティット・バンドは楽譜を吟味して、バッハのエッセンスを手探りで呼び覚まします。聞き手にもそんな姿勢が求められていたのかもしれません。
率直に申し上げて、彼らの演奏にはある種の古さを感じたのですが、古楽器演奏への自負と、それに裏打ちされた明確なアプローチには唸らされるものを感じました。古楽への求道者。ラ・プティット・バンドはそんな稀有な存在なのかもしれません。興味深いコンサートでした。
J.S.バッハプログラム
2つのヴァイオリンのための協奏曲 BWV1043
ブランデンブルク協奏曲第5番 BWV1050
6声のリチェルカーレ(音楽の捧げ物より) BWV1079
オーボエとヴァイオリンのための協奏曲 BWV1060a
ブランデンブルク協奏曲第4番 BWV1049
監督 シギスヴァルト・クイケン
演奏 ラ・プティット・バンド
2006/5/19 19:00~ 東京オペラシティーコンサートホール2階
「古楽界のパイオニア」(パンフレットより)であるラ・プティット・バンドとクイケン。そんな彼らが真っ向勝負にてバッハを演奏します。時流に乗らないで、あくまでも独自のスタイルを貫く演奏団体のコンサートです。

これが正統的、もしくは伝統的な古楽演奏とでも言うのでしょうか。ともかくラ・プティット・バンドは、明らかに広過ぎたこのホールにおいて、あまり響かない古楽器を控えめに鳴らしながら、まるで楽譜上の音符をなだらかになぞるように端正に演奏していきます。ひたすら淡々と鳴り続けるバッハの調べ。ブランデンブルクがまるでミニマルミュージックのように聴こえてきました。今をときめくイタリアンバロックとは全く隔絶した別の世界。遠いバロックの響きを、聴衆に媚びることなくそのまま提示する。組み立てられた音楽の遺跡。禁欲的で、異端を許さないような、厳格なバロックがここに残っていました。コンサートホールの時間の流れが止まってしまった。この場だけすっぽりと数世紀前にワープしてしまったような気配さえ漂います。まさにかつて誰もが見たであろう、あの音楽室に飾られていた厳めしい肖像画のバッハです。あの物々しいバッハがここに甦りました。

肩からひもで吊るしたヴァイオリンを奏でるシギスヴァルト。失礼ながら彼は、お世辞にも指の良く動くヴァイオリニストとは言えません。むしろ所々ギコギコと響き渡るような美しくない音すら奏でてくれます。クイケン一派では、明らかにサラの方が技巧に長けているでしょう。またオーボエのボージロー。彼のふくよかなオーボエはシギスヴァルトとは一線を画していました。その点、シギスヴァルトと上手く絡み合っていたのは、これでもかというほど抑制的に演奏されたチェンバロです。この二者が合わさって、奇妙に説得力を持った音楽を生み出してくる。シギスヴァルトは朴訥に音楽を語ります。音楽に誠実さを感じること。先日このホールで聴いたビオンディのスーパーエンターテイメント・バロックの対極にある、全く飾らないバロック音楽が表現されていました。最後のブランデンブルクの4番やアンコール曲(4番の第3楽章をもう一度。)にこそ、ライブ特有の熱気が感じられましたが、初めの5番などは非常に冷めた眼差しで音楽を象ります。また、6声のリチェルカーレがこのコンサートの白眉であったのも、それがラ・プティット・バンドの怜悧なアプローチに合致する曲だったからではないでしょうか。リチェルカーレとは、イタリア語で吟味する、または探し求めるという意味だそうですが、まさにラ・プティット・バンドは楽譜を吟味して、バッハのエッセンスを手探りで呼び覚まします。聞き手にもそんな姿勢が求められていたのかもしれません。
率直に申し上げて、彼らの演奏にはある種の古さを感じたのですが、古楽器演奏への自負と、それに裏打ちされた明確なアプローチには唸らされるものを感じました。古楽への求道者。ラ・プティット・バンドはそんな稀有な存在なのかもしれません。興味深いコンサートでした。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )










