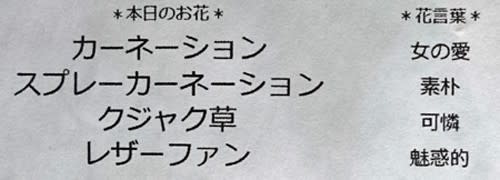坂井孝一『承久の乱』(中公新書2517、2018年12月25日中央公論新社発行)を読んだ。
表紙裏にはこうある。
一二一九年、鎌倉幕府三代将軍・源実朝が暗殺された。朝廷との協調に努めた実朝の死により公武関係は動揺。二年後、承久の乱が勃発する。朝廷に君臨する後鳥羽上皇が、執権北条義時を討つべく兵を挙げたのだ。だが、義時の嫡男泰時率いる幕府の大軍は京都へ攻め上り、朝廷方の軍勢を圧倒。後鳥羽ら三上皇は流罪となり、六波羅探題が設置された。公武の力関係を劇的に変え、中世社会のあり方を決定づけた大事件を読み解く。
表紙の副題には(奥付にはない)「真の『武士の世』を告げる大乱」とある。
巻末には、関係略年表や当時の日本地図があり、本文の要所には関係人物の系図載せられている。
「はじめに」
「承久の乱」は、「倒幕」ではなく、「北条義時追討」が目的であった。
後鳥羽上皇は芸能・学問に秀でた有能な帝王であった。
実朝は将軍として十分な権威・権力を保ち、後鳥羽の朝廷と親密な協調関係を築いていた。
保元の乱
鳥羽院は崇徳天皇をだまして退位させ、3歳の近衛天皇を即位させた。近衛天皇が17歳で死去すると、まさか天皇になるとは思わず今様(民衆の流行歌謡)に熱中していた雅仁親王(のちの後白河天皇)を選んだ。評判のよい親王の子・守仁親王への中継ぎだった。
鳥羽院は新天皇を守るため、天皇方へ源義朝、平清盛、足利義康(足利氏の祖)などを集めていた。鳥羽院が亡くなると、保元元年(1156)、崇徳、藤原頼長、藤原忠実、源為義、源為朝、平忠正らが、院方に奇襲をかけたが、兵力差が大きく敗れた。
「武者の世」が到来した。
平治の乱
平治元年(1159)、藤原信頼・源義朝は、平清盛が熊野詣での間、院御所に夜襲をかけた。清盛は逆襲し、クーデターを鎮圧、信頼、義朝は殺され、源頼朝は伊豆國伊東に配流された。
清盛独裁へ。
平氏から源氏へ
8歳で践祚した高倉天皇の父・後白河は、1168年、清盛政権のもとで本格的院政を開始した。
1180年頼朝が伊豆で挙兵。平家が安徳天皇、三種の神器と共に都落ちした。後白河院は4歳の尊成を践祚さけ、後鳥羽天皇とした。神器なき践祚だった。
平氏は壇ノ浦で滅亡するが、神鏡「八咫鏡(やたのかがみ)」は船内で確保され、神璽(しんじ)「八尺瓊勾玉(やさかのまがたま)」は浮かび上がったが、宝剣「天叢雲剣(あめのむらくものつるぎ)」は安徳とともに沈んでしまった。
頼朝は本格的武家政権・鎌倉幕府を12世紀末に樹立した。
後鳥羽院政開始
1198年、19歳の後鳥羽は為仁親王に譲位し、土御門天皇が4歳で践祚し、後鳥羽の院政が開始した。後鳥羽院は、儀礼や制約から解放され、自由を謳歌し、才能を覚醒した。
後鳥羽は自ら撰歌・分類・配列・詞書作成などに積極的に関与し、『新古今和歌集』を完成させた。
承久の乱勃発
当時、誰も武士だけでやっていけると思わなかった。源実朝は、後鳥羽院に心酔し、皇子を次期将軍に迎えることを考えていたし、後鳥羽も応えようとしていた。しかし、実朝が甥の公暁に暗殺されてしまった。
後鳥羽院は、幕府をコントロールできない状況にイラつき、元凶の北条義時を討つことを企てた。倒幕という考えまではなかった(この点は最近では定説らしい)。
鎌倉幕府は幕府の危機として御家人たちを鼓舞し、調停と幕府の根本的対立となった。
1221年、幕府は大軍を出撃させ、勝利し、六波羅探題を置いて朝廷をコントロールした。後鳥羽は隠岐の島に流され、そこで19年過ごし、1239年に没した。なお、北条義時は承久の乱の3年後の1224年に没している。
坂井孝一(さかい・こういち)
1958年、東京都生まれ。東京大学文学部卒。同大学大学院博士課程単位取得。博士(文学)。専攻、日本中世史。現在、創価大学文学部教授。
著書に『曽我物語の史実と虚構』、『源実朝』、『人をあるく 源実朝と鎌倉』など。
私の評価としては、★★★☆☆(三つ星:お好みで)(最大は五つ星)
朝廷と武士のさまざまな細かい攻防が要領よく説明されている。同時に全体の流れも明快に書かれていて解り易い。
ただ、とくに朝廷を巡る様々な人の名とその複雑な企てがかなり詳しく記述されていて、複雑怪奇さに頭がついていかない。2回目以降は平、藤原などの苗字が省略されていて、似たような名が多くて混乱する。
著者は歴史学者にもかかわらず、和歌などに自信があるようで、後鳥羽の文学的才能の説明にかなりなページを割いている。素人の考えと決めつけて、私は斜め読みした。
中世では皇位継承を「践祚(せんそ)」といい、その後、新天皇が高御座(たかみくら)と呼ばれる王座に登って皇位についたことを内外に表明する「即位」の儀と区別した。
この本では、今回久しぶり登場の「上皇」と同一視しないように、(後鳥羽)「上皇」は中世一般的に用いられていた「院」と表している。