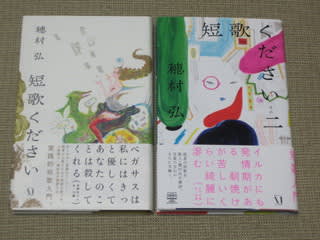穂村弘 2011年 メディアファクトリー
「その二」は2014年3月、メディアファクトリー
きのうから歌人つながり、っていうか、こっち先読んだんだったか、これは短歌を集めた本。
書店で、「その二」が新しく出てるのをみて、3年前に最初のが出てるのを知った、あいかわらず情報が遅れてる私。
とりあえずそろえて買って、順番に読んだ。
「実践的短歌入門」って帯にあるけど、“本の情報誌『ダ・ヴィンチ』”の人気連載であり、読者投稿コーナーである「短歌ください」の書籍化だという。
そんな雑誌、そんな連載、あるってまったく知らなかったけど。
というわけで、歌を詠むのは読者、たぶんアマチュア。
毎回、お題が決まってて、それ以外に自由詠もあり。
そこに穂村弘が講評をくわえる。想像どおり、けっこうおもしろい。
短歌だけを一冊まるまる続けて読もうとすると、けっこう疲れるもんだけど、この構成は疲れない、飽きない。
穂村弘は、「オートマチックな表現を避けろ」なんていつも言ってたと思うけど、本書のなかで繰り返して出てくるのは、「怖い歌は、いい歌だ」という評。
怖いったって、単純なホラーならいいってわけぢゃない、もちろん。
以下は、第一巻で、「怖い歌は、いい歌」と評されたものの例。
あんかけのあん煮立つような音させてぼこりと夫が寝入る木曜
この街の6時のサイレンは半音くるっていると言った先生
かおりんに似た人を見た十秒間見つめ続けた声が違った
あとから出た「その二」のほうには、そのものずばり「恐怖」をテーマにして作品を募った回があった。
その冒頭には、>楽しい歌がいい歌とは限らない。悲しい歌がいい歌とも限らない。でも、怖い歌は必ずいい歌。不思議ですね。って著者の宣言がある。
そこで最初にとりあげられてる歌は、以下のようなもの。
父の小皿にたけのこの根元私のに穂先を多く母が盛りたる
>これは怖い。ってあるんだけど、見た瞬間にはわからない私には、この怖さがわかんないと短歌わかんないのかな、と不安になる。
別の「パニック」というお題の回にも、もちろん怖い歌はある。
過去に一度自分の名として母の名を書いたことあり四角い部屋で
って、これはわかりやすい怖さだとは思う。
怖い歌ってこと以外にも、ときどき鋭い解説があって、「近代以降の短歌には、このような(世界の)細部の見つけ合いみたいなところがある」と明かしてくれている。
そんな例は、
図書館の駐輪場にあるチャリに札がついてる「僧侶専用」
みたいなおもしろい発見のもの。
ちなみに、二冊をとおして、私が個人的に気に入ったのは(あくまでパッと見だけの感覚ではあるが)、自由題作品のひとつ。
行ったのか待てば来るのかバス停で本当のことはわからずにいる
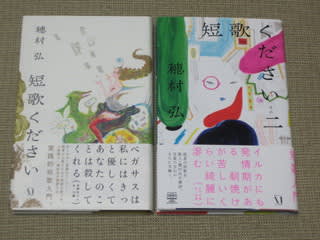
「その二」は2014年3月、メディアファクトリー
きのうから歌人つながり、っていうか、こっち先読んだんだったか、これは短歌を集めた本。
書店で、「その二」が新しく出てるのをみて、3年前に最初のが出てるのを知った、あいかわらず情報が遅れてる私。
とりあえずそろえて買って、順番に読んだ。
「実践的短歌入門」って帯にあるけど、“本の情報誌『ダ・ヴィンチ』”の人気連載であり、読者投稿コーナーである「短歌ください」の書籍化だという。
そんな雑誌、そんな連載、あるってまったく知らなかったけど。
というわけで、歌を詠むのは読者、たぶんアマチュア。
毎回、お題が決まってて、それ以外に自由詠もあり。
そこに穂村弘が講評をくわえる。想像どおり、けっこうおもしろい。
短歌だけを一冊まるまる続けて読もうとすると、けっこう疲れるもんだけど、この構成は疲れない、飽きない。
穂村弘は、「オートマチックな表現を避けろ」なんていつも言ってたと思うけど、本書のなかで繰り返して出てくるのは、「怖い歌は、いい歌だ」という評。
怖いったって、単純なホラーならいいってわけぢゃない、もちろん。
以下は、第一巻で、「怖い歌は、いい歌」と評されたものの例。
あんかけのあん煮立つような音させてぼこりと夫が寝入る木曜
この街の6時のサイレンは半音くるっていると言った先生
かおりんに似た人を見た十秒間見つめ続けた声が違った
あとから出た「その二」のほうには、そのものずばり「恐怖」をテーマにして作品を募った回があった。
その冒頭には、>楽しい歌がいい歌とは限らない。悲しい歌がいい歌とも限らない。でも、怖い歌は必ずいい歌。不思議ですね。って著者の宣言がある。
そこで最初にとりあげられてる歌は、以下のようなもの。
父の小皿にたけのこの根元私のに穂先を多く母が盛りたる
>これは怖い。ってあるんだけど、見た瞬間にはわからない私には、この怖さがわかんないと短歌わかんないのかな、と不安になる。
別の「パニック」というお題の回にも、もちろん怖い歌はある。
過去に一度自分の名として母の名を書いたことあり四角い部屋で
って、これはわかりやすい怖さだとは思う。
怖い歌ってこと以外にも、ときどき鋭い解説があって、「近代以降の短歌には、このような(世界の)細部の見つけ合いみたいなところがある」と明かしてくれている。
そんな例は、
図書館の駐輪場にあるチャリに札がついてる「僧侶専用」
みたいなおもしろい発見のもの。
ちなみに、二冊をとおして、私が個人的に気に入ったのは(あくまでパッと見だけの感覚ではあるが)、自由題作品のひとつ。
行ったのか待てば来るのかバス停で本当のことはわからずにいる