男女共同参画の形成の促進に関する施策として、アファーマティブアクション(ポジティブアクション)は、採用しうる施策なのかどうか。
『ジェンダーと法』の講義において、いかの問題が課題として出されました。
******** 『ジェンダーと法』講義 課題************
Y県では、公立高校における男女共同社会の実現を目指して「基本計画」を改定し、教頭全体における女性の比率が20%になるまでの間、次のルールに従って教頭を任用することにした。
男性Xが220点、女性Aが202点であった場合において、それぞれ①、②、③の適用をうけて、XではなくAが任用された場合、XとYの立場から、主張と反論を、憲法の問題として考えてください。
①毎年、合格者の3割を女性にするように割り当てる(クオーター制)
②「選考試験」において成績が同等である場合には、女性であることをプラス要素として重視する。
③「選考試験」の成績順で任用すると、女性が一人も任用されない結果となる場合、女性の候補者の中で最も成績がよい者に対して20点を加点する。
***************************
<現段階の自分なりの着目点>
いろいろ、問題点はあろうかと思います。
*公立高校での「基本計画」改定のプロセス
1)「男女共同参画会議」などの会議を経て、民主的に作成されたか。
*公立高校での教頭選考試験の現状分析
1)教頭選考試験の受験者の状況はどうか。もともと、受験者の割合の男女比が大きく乖離しているのではないか。合格者よりも、受験者の割合の比を是正するのが先ではないか。
2)教頭になることをためらわせるような、職場環境なのではないか。
*教頭における女性の割合が20%という目標についての問題点
1)女性の割合が20%であることで、男女共同参画がどれだけ促進することの寄与度はどのように評価し、その評価基準でどの程度実際に促進するといえるのか。
*このルールにおける問題点
1)20点を与えるということの、その20点の根拠。
2)③の基準が採用される場面は、①の合格者のうちの女性3割を達成できない場面であり、制度内の矛盾がある。
*高校における男女共同参画のために他の有効な手段がある点
1)教頭に占める女性の割合を20%にすることよりも、女性教員の提案を吸い上げる手法を取り入れることなど他の手段のほうが、より有効に目的達成に貢献するのではないか。
*Xが侵害された権利
1)自分の実力を、不当に評価され、自分より下の成績のものが、本来、その制度がなければつくことができた教頭のポストに、制度があったため、つくことができなかった。
自己の実力が正当に評価されるという権利を侵害された。
*社会が侵害された権利
1)男性教師と女性教師を実力を同等にするには、女性教師の得点に20点を加算して可能にすることができるという設定で、制度が作られている。
このことは、女性教師は、男性教師より20点分のもともとの実力の差があることを認めることにつながる。
「男女能力差別」を肯定している点で、社会が目指す男女平等原理に反している。
最新の画像[もっと見る]
-
 有機野菜を学校給食に取り入れていくこと、今回の予算特別委でも議論させていただきました。品川区乗り出すのですね。
7日前
有機野菜を学校給食に取り入れていくこと、今回の予算特別委でも議論させていただきました。品川区乗り出すのですね。
7日前
-
 次の感染症パンデミックに備えること、絶対にやなねばなりません。学び・経済・生活を、再び止めないように。
7日前
次の感染症パンデミックに備えること、絶対にやなねばなりません。学び・経済・生活を、再び止めないように。
7日前
-
 次の感染症パンデミックに備えること、絶対にやなねばなりません。学び・経済・生活を、再び止めないように。
7日前
次の感染症パンデミックに備えること、絶対にやなねばなりません。学び・経済・生活を、再び止めないように。
7日前
-
 次の感染症パンデミックに備えること、絶対にやなねばなりません。学び・経済・生活を、再び止めないように。
7日前
次の感染症パンデミックに備えること、絶対にやなねばなりません。学び・経済・生活を、再び止めないように。
7日前
-
 次の感染症パンデミックに備えること、絶対にやなねばなりません。学び・経済・生活を、再び止めないように。
7日前
次の感染症パンデミックに備えること、絶対にやなねばなりません。学び・経済・生活を、再び止めないように。
7日前
-
 「教養は、どこへ?」と、問われたら。
1週間前
「教養は、どこへ?」と、問われたら。
1週間前
-
 「教養は、どこへ?」と、問われたら。
1週間前
「教養は、どこへ?」と、問われたら。
1週間前
-
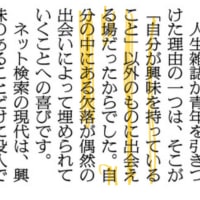 「教養は、どこへ?」と、問われたら。
1週間前
「教養は、どこへ?」と、問われたら。
1週間前
-
 自分にとっての問いでもあり続けます。横断歩道の歩車境界の段差をゼロにすること。それを行う自治体もある。
1週間前
自分にとっての問いでもあり続けます。横断歩道の歩車境界の段差をゼロにすること。それを行う自治体もある。
1週間前
-
 千代田区官製談合は、対岸の火事ではない。
1週間前
千代田区官製談合は、対岸の火事ではない。
1週間前
「子育て・子育ち」カテゴリの最新記事
 子どもの権利を権利を守る。基礎的自治体である中央区の役割は、非常に大きい。
子どもの権利を権利を守る。基礎的自治体である中央区の役割は、非常に大きい。 性差別・性暴力とアドボカシー 0か月0日の赤ちゃんの死をいかに防ぐか
性差別・性暴力とアドボカシー 0か月0日の赤ちゃんの死をいかに防ぐか 子どもの意見表明が大切にされることの重要性について
子どもの意見表明が大切にされることの重要性について 子どもの権利が守られていることを、チェックするには。
子どもの権利が守られていることを、チェックするには。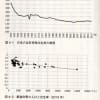 少子化の実情、人口が多いところほど、合計特殊出生率が低くなっている。
少子化の実情、人口が多いところほど、合計特殊出生率が低くなっている。 自由闊達なる意見交換が、昨日9/26も、子ども・子育て会議でなされました。
自由闊達なる意見交換が、昨日9/26も、子ども・子育て会議でなされました。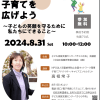 今週8/31(土)午前10時開催、子育て講演会『体罰によらない子育てを広げよう~子...
今週8/31(土)午前10時開催、子育て講演会『体罰によらない子育てを広げよう~子... 次期第3期中央区子ども・子育て支援事業計画(2025~29)策定へ。基本理念「子ども...
次期第3期中央区子ども・子育て支援事業計画(2025~29)策定へ。基本理念「子ども... いよいよ入園・入学式。もしも小1の壁というものがあるならば、私たち小児科医も一...
いよいよ入園・入学式。もしも小1の壁というものがあるならば、私たち小児科医も一... こども基本法が本年2023年4月に施行されたところですが、子どもの権利条約の精神が...
こども基本法が本年2023年4月に施行されたところですが、子どもの権利条約の精神が...

















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます